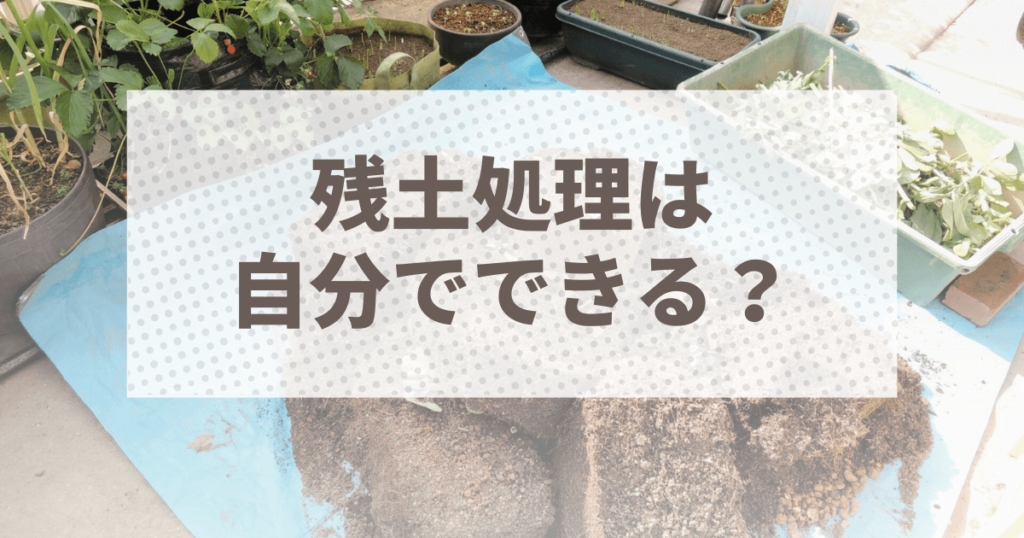
エクステリアをリフォームすると発生するのが「残土」と呼ばれる不要な土です。通常、残土は外構工事業者が処分してくれます。
しかしDIYなどで発生した残土の処理を処分業者に頼むと、費用がかかってしまいます。
そのため、費用を少しでも抑えるために残土を自分で処理したいと考える方も少なくないでしょう。
そこでこの記事では、自分で残土処理する方法や注意点について解説します。
残土処理を自分でする方法

残土が発生したら、できるだけ安く処分したいですよね。では、自分で残土処理したい場合、どのような方法で行えば良いのでしょうか。
ここでは、個人でできる残土処理の方法を4つ紹介するので、メリットとデメリットを照らし合わせて検討してみましょう。
敷地内で処分する
自宅の庭に土の部分や花壇があり、残土が多すぎない場合は、敷地に撒いて再度活用する方法があります。
花壇に撒くときは土壌改良剤と混ぜると、比較的簡単に土の性質が植物の生育に最適な状態になります。
土壌改良剤は、腐葉土、バーク堆肥、牛糞堆肥などが代表的なものです。庭木用や野菜用など、目的に合ったものを入れるようにしましょう。
なお、庭に直接土を撒きたくない場合は、土嚢袋に残土を詰めて土嚢として、大雨や台風の時に役立てられます。
ジモティーを活用する
ジモティーを利用して土をほかの人に譲る方法もあります。ジモティーとは地域密着型の商品を譲ったり売ったりできるサービスです。
手数料が不要で、自宅に取りに来てくれることを条件として物を譲れるので、無料で手間がかからずに土を処分できます。
庭をDIYしたいと考えている人のなかには、できるだけコストを抑えて土を大量に手に入れたいと考えている人もおり、実際にジモティーでは庭土の譲渡が行われています。
費用をかけずに必要な人に残土を譲れる一方で、欲しい人が現れるまでずっと土を保管していなければならないというデメリットもあることは留意しておきましょう。
造園業者やホームセンターに引き取ってもらう
残土を受け入れてくれる造園業者やホームセンターが近くにあれば、引き取ってもらう方法もあります。
インターネットで検索して、残土受け入れをしている造園業者を探してみましょう。受け入れ場所や受け入れ料金については問い合わせし、業者の案内に従って持ち込みます。
ホームセンターは、最近では残土の受け入れをしていない店舗が多く、受け入れをしていても土を購入した人に限定するなど、条件を設けているところもあります。
また、残土受け入れが有料の店舗もあるので注意が必要です。事前に問い合わせて残土受け入れを行っている店舗に持ち込みましょう。
不要品回収業者に依頼を検討する
費用はかかりますが、残土処理を不用品回収業者に依頼すると、処分に関する問題を簡単に解決できます。
残土を自分で処理しようとする場合、自分で袋詰めしたり、運搬したりして処分しなければなりません。
不用品回収業者に依頼すれば自分で土を運ぶ手間もかからず、すぐに処分できるため、時間的なコストや手間を省けます。
特にDIYで庭をリフォームして残土が出た場合は、この方法が有効だといえるでしょう。
依頼を検討している場合は複数の業者から相見積もりをとり、料金と作業内容を比較して決めると失敗を防げます。
そもそも残土が発生するシーンとは?

残土は通常、土木工事や建築工事で発生します。では、個人宅では残土はどのような場面で発生するのでしょうか。
ここでは家庭で残土が発生するケースを紹介しています。大量の土の処分に困ることがないよう、事前にどのようなときに残土処理が必要なのか知っておくと安心です。
家庭菜園やガーデニング
家庭の日常生活で主に発生する残土は家庭菜園や花壇、観葉植物から出る土です。植物の生育のためには栄養分の高い土や清潔な土を使用する必要があり、古くなった土が不要になる場合があります。
ある程度は新しい土と古い土を混ぜて使えますが、土が増える一方となり、一定量を処分したくなるケースもあるでしょう。
また、引っ越し等でプランターや鉢を整理する際に不要な土が大量に発生することもあります。
外構工事・庭づくり
建物の建設工事だけでなく外構工事でも、基礎をつくるときに土地から残土が発生します。
土間コンクリートやカーポート、フェンスなどを設置する際、土を掘り、地中に基礎をつくらなければなりません。そのときに、基礎の要積分の土が不要な残土として発生するのです。
余った土は、少量であれば庭に撒けば問題ありませんが、外構工事のように大量に残土が発生した場合、庭に残土を敷くと水はけの悪い庭になってしまいます。
水はけが悪いと大雨の際に床下浸水の原因となってしまったり、道路や隣の敷地に土砂が流出したりするおそれがあるため、残土は適切に処分する必要があります。
災害用の土嚢
水害や台風対策のために用意した土嚢を処分したくなるケースもあるでしょう。土嚢は放置すると石が混入したり雑草が生えたりしてしまいます。
また、袋が破れて中の砂が流出し、掃除に手間がかかる場合も。大量にあると処分にも手間がかかるため、早めの対応が大切です。
使用後の土嚢は脱水、乾燥させてから業者に回収してもらいます。処分費用は土嚢袋1つで200~300円が目安です。あらかじめ個数を数えておき、業者に金額の見積もりを依頼すると良いでしょう。
残土を処分するときの注意点

残土は条例などにより、処分に一定のルールが設けられています。勝手に処分すると罰則の対象となる場合があるので、十分注意が必要です。
以下で紹介する点に注意し、市区町村が定めた規定に則って正しく処分してください。
残土の種類によって処分方法が異なる
残土には第1種~第4種と泥土(でいど)の5種類に分類され、種類によって処分方法が異なります。
- 第1種建設土:砂、小石。構造物の埋戻し、裏込材として使用。
- 第2種建設土:砂質土、礫質土。土の硬さを示すコーン指数800以上のもの。道路の盛り土などに使用。
- 第3種建設土:砂質土、粘性土でコーン指数400以上のもの。水面の埋め立てなどに使用。
- 第4種建設土:砂質土、粘土、有機質土でコーン指数200以上のもの。水面の埋め立てのみで使用。
- 泥土:強度が低い泥状の土で、コーン指数200未満のもの。
第4種に向かうにつれて柔らかく強度が低くなります。数字が大きいものほど処分費用が高くなり、リサイクルプラントによっては受け入れ不可の場合があります。
このほか、標準仕様のダンプには積載できないほど水分のあるものが汚泥です。
残土を一般ごみとして捨てられる自治体はほとんどない
土は一般ごみのような「廃棄物」ではなく「自然物」として扱われるため、分別ごみとして取り扱っていない自治体がほとんどです。
ただし、市区町村によっては条件を定めて回収している場合があります。受け入れている地域でも、一度に出せる量が決まっていたり、家庭の園芸で出た土に限定していたりするので注意が必要です。
地域によって残土回収の可否、回収料金など、ルールが異なります。事前に住まいの地域の自治体の窓口に問い合わせておくと安心です。
山林などに残土を捨てるのは不法投棄になる
残土を山林など自然の場所に捨てるのは違法です。不法投棄は大きな社会問題となっていることから罰則が強化されています。
個人が不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方、法人は3億円以下の罰金の対象です。
また、不法投棄を前提として残土や不用品、コンクリートガラなどの収集・運搬を行った場合も3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課されます。
不法投棄を知りながら手伝った場合も罰則の対象となるため、業者に依頼する場合は残土を正しく処分している業者の選択は必須となります。
残土処分場に持ち込みも費用が発生する
産業廃棄物処理場は残土の受け入れに対応しているところもありますが、自分で持ち込んだ場合でも費用が発生する点には注意が必要です。
残土の処理費用は地域により異なりますが、一般的に1トン当たり1,500~1,800円が相場となります。自分で処分場に持ち込む場合、トラックのレンタル料や運搬の手間がかかります。
そのため、料金はかかっても業者に依頼した方が、トータルコストが安く済むケースも少なくありません。
残土処理を自分でやるか業者に任せるかは、手間や労力も考えて検討すると失敗を防げるでしょう。
まとめ

住宅のエクステリアリフォームを外構工事業者に任せていれば、残土処理まで業者が行うため安心です。
しかし、DIYでエクステリアをリフォームする場合やガーデニングなどで発生した残土は自分で処理する必要があります。
土や砂は通常、一般ゴミでは出せないので、事前に自治体のルールを調べておき、適切に処分することが大切です。
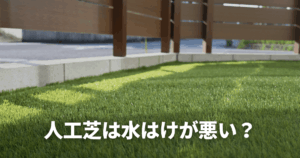
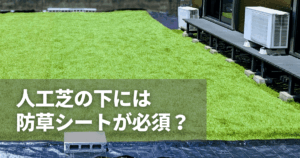
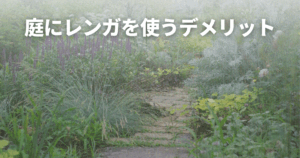
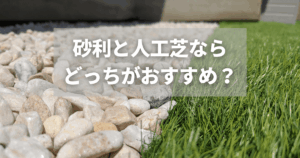
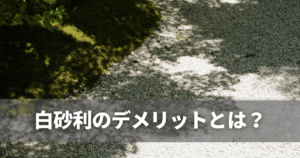
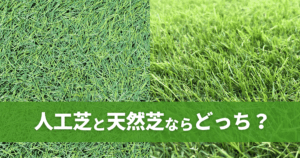
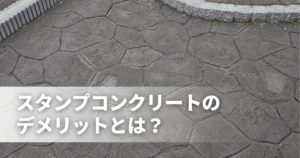
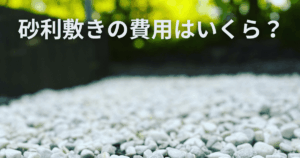

コメント