
所有している建物を解体工事で取り壊す場合、取壊し費用を経費にできるかどうか分からないという人も少なくないでしょう。解体費用は決して安くないため、正しく申告することが税金対策につながります。
この記事では、解体工事の費用が経費計上できるかどうかの判断基準、申告手続きのポイント、知っておきたい控除制度などについて解説します。
確定申告で解体費用は経費や控除の対象になる?

建物の解体費用は経費や控除の対象になるのでしょうか。結論からいえば事業用に使われている建物は経費にできる可能性があります。
以下で判断方法について詳しく説明しているので、どれに該当しているのかチェックしてみましょう。
経費計上・所得控除されるかどうかは目的で大きく変わる
解体費用を経費として取り扱えるかどうかは、取り壊しの目的に応じて異なります。経費にできるのは所得税法により、事業目的の賃貸物件や事務所を取り壊して新しく建て替えた場合です。
一方で、自分で住む目的で家を建て替える場合や、新しく購入した土地で建て替えを行う場合の解体費用は経費にはできません。
また、自分が所有している建築物を取り壊し、土地を売却する場合は、解体費用は譲渡費用として取り扱います。
土地が売れたら売却代金から取得費と解体費用や仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた売却益(譲渡所得)が課税の対象となります。
家事費かどうかを見極めることが重要
家事費とは、いわゆる生活費のことで、所得税における必要経費にはできません。
自宅を取り壊して賃貸アパートを建設するなど、事業用の建物に建て替える際の支出は「家事費」として取り扱われ、経費にはならないので注意しましょう。
また、事業用の建物を取り壊し、新しく生活用の建物を建てる場合は、解体の目的によっては家事費になります。
たとえば、建物が老朽化していたり災害により破損してしまったりするなど、外部要因によって仕方なく取り壊したり、自宅に建て替えたりする場合は、費用として経費にできます。
一方で、特に外部要因はなく、事務所や店舗を取り壊して自宅に建て替えたい場合は家事費となり、経費にはできません。
解体費用が経費・控除できるケース

解体費用が確定申告で経費や控除の対象となるのは大きく3つあり、売却のために自宅を解体する場合、不動産所得を得るための賃貸用の建物を解体する場合、災害等で損壊した家を取り壊す場合です。一つずつ見ていきましょう。
住宅を売却するために解体する場合
自分が所有する建物を解体して更地にし、土地を売却する場合は「譲渡費用」として、売却代金から解体費用を差し引けます。
この場合は建物が居住用でも事業用でも同じ取扱いです。このとき、解体費用だけでなく、建物滅失登記にかかった費用も譲渡費用として計上が可能です。
なお、譲渡費用は、経費として計上するのではなく譲渡所得の計算から算出し、税金を支払います。
譲渡所得を求める式は以下のとおりで、特別控除を差し引いても譲渡所得がプラスになる場合に課税されます。
- 譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
税率は不動産の所有期間が5年以下の場合は39.63%、5年を超える場合は20.315%です。
賃貸物件など事業用資産を解体する場合
賃貸物件や事務所、商店などを中心とした、事業用・業務用の建物を解体する場合は解体費用を経費に算入できます。
このときの仕訳は借方が、解体の目的が建物の撤去なら固定資産除去損、建て替えなら建設仮勘定となり、貸方が預金、建物です。
賃貸物件は、マンション、アパートの場合は10室以上、戸建ての場合は5棟以上の事業規模で事業用物件とみなされます。
ただし、数については実態で判断されるため、必ずしも上記の戸数でなくても事業的規模とみなされる場合もあるので、税務署に確認するとよいでしょう。
災害で損壊した住宅の解体
災害で損害を受けた場合や老朽化など、外的要因により建物を解体する場合は、自宅、事業用に関わらず経費として計上できます。
具体的には解体、後片付けなどの撤去費用の仕訳は「災害損失」となり、損金となります。
災害損失とは災害により資産が滅失・損壊した場合に用いる勘定科目です。災害損失を計上すると税金の控除や還付を受けられる可能性があります。
災害は自然災害や人為的災害を指しますが、範囲や関係性については判断が難しいのが現実です。また、計上できるのは災害で直接影響があったものに限られます。
解体費用を計上できる場合の確定申告手続き

解体費用を経費として計上できる場合は、確定申告手続きを行い、所得税などの控除を受けましょう。
正しく申告を行うためには以下のポイントを押さえることが大切です。また必要に応じて税理士などのサポートを受けると安心です。
必要となる書類一覧
解体費用を確定申告で所得控除されるには、領収書等の原本の添付が必要です。このとき、契約書など取引を証明する書類も添付できますが、見積書は資料にとどまるため、添付する必要はありません。
さらに、不動産を売却して利益が発生した場合の確定申告では以下の書類が必要です。
- 売買契約書
- 譲渡所得の内訳書
- 不動産の取得費用を確認できる書類
- 不動産の譲渡費用を確認できる書類
- 登記事項証明書
確定申告の申告期間はおよそ1か月間です。できるだけ早めに書類を揃え、スムーズに申告を済ませましょう。
経費・控除を申告する際の注意点
解体工事の確定申告では目的に合った勘定科目を選ぶことが大切です。
また、解体後に土地を売却した場合は特別控除を適用できない点に注意しなければなりません。通常、譲渡所得は最大50万円の特別控除を受けられます。
しかし不動産売買による譲渡所得は50万円の特別控除の適用外です。そのほか、確定申告は原則として、不動産売買によって20万円を超える譲渡所得が発生した場合は申告不要です。
申告不要でも税務署から確認の連絡がくる場合があります。これはあくまでも確認なので、申告不要な事実があればその通りに伝えれば問題ありません。
解体後に土地を売却する際に活用したい特例

建物の解体後に土地を売却する場合、特例を利用すると税金対策になります。
以下に代表的な控除、特例を紹介するので、条件に合う場合は積極的に活用して節税につなげましょう。
居住用財産の3,000万円特別控除との併用
土地を売却するときに、譲渡所得(売却益)があると税金がかかりますが、3,000万円の特別控除の適用を受ければ、売却益3,000万円までは課税額をゼロにできます。
譲渡所得は譲渡費用を差し引くことで、解体費用など売却する際にかかった経費との併用が可能です。
ただし、住宅ローンとの併用はできない点には注意が必要です。新たに購入する不動産で住宅ローンを利用する場合、3,000万円の特別控除の適用を受けた場合は住宅ローン控除は適用できません。どちらがお得かよく考えて決めるようにしましょう。
相続した空き家を解体して売却する特例
同じく3,000万円の控除を利用できる制度に「空家特例」というものがあります。
空家特例とは相続で引き継いだ物件の家屋を取り壊すか、リフォームしてから売却する場合、譲渡所得から3,000万円の控除を受けられるという制度です。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除との違いは、居住用財産控除の場合は「自分が住んでいたマイホーム」を売却した場合に控除が受けられる制度、一方で、空家特例は「相続で取得した土地や家屋」を売却した場合に控除が受けられる制度です。
また、居住用財産控除は戸建て住宅のほかマンションも対象となりますが、空き家特例は戸建てのみが対象なので注意しましょう。
参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
解体費用を確定申告するときのよくある質問
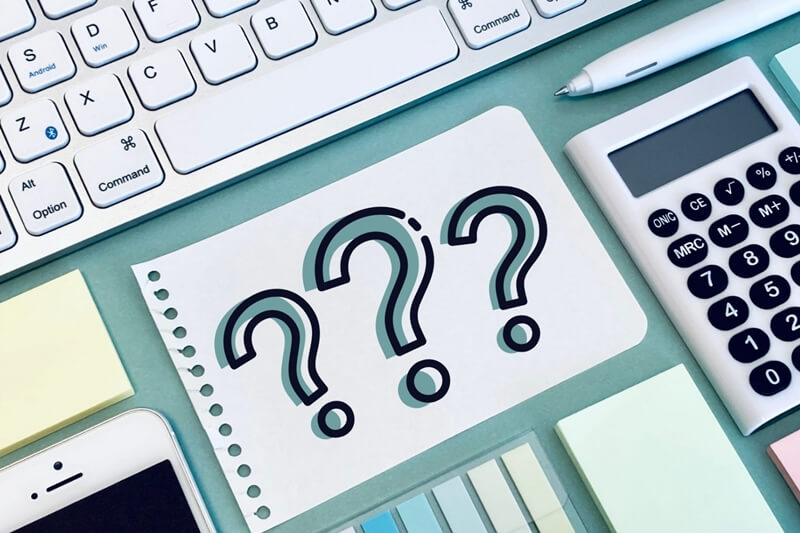
ここでは、所有する建物の取り壊し費用を確定申告するときによくある質問とその回答を紹介します。
建物の解体を検討している場合は事前に確認しておき、節税対策もしっかり行っておきましょう。
解体費用と修繕費はどう違うの?
解体費は目的に応じて勘定科目が異なりますが、そのうち、建物の修繕が目的の場合は「修繕費」として取扱います。
災害などの復旧以外では、修繕するために建物をすべて取り壊すことはほぼないため、一部のみ取り壊すケースが一般的です。
解体の仕訳は、主に建物の撤去が目的の場合は「固定資産除却損」に計上します。建替えが目的の場合は「建設仮勘定」、土地利用目的で中古家屋つきの土地を購入し建物を解体する場合は「土地」、解体後に新築する予定で費用を先に支払う形にするときは「前払金」です。
解体費用を分割払いした場合はどうなる?
建物の解体費用はローンを利用して支払うことも可能です。ローンで貸付を受ければ手元に資金がなくても建物を解体できます。
注意点は、建物の解体費用は住宅ローン控除の対象外だということです。そのほか、仲介手数料、印紙代などの諸費用も金額にかかわらず控除の対象外になります。
さらに、住宅購入費用のための借入で、返済期間が10年以上でも、親族や知人からお金を借りた場合も控除は適用されません。
住宅ローン控除を利用したい場合は、要件をしっかりチェックしておきましょう。
まとめ

建物の解体費用は、目的によって経費にできるものとできないものがあり、解体することで固定資産税額にも影響が出ます。
正しく経費計上するために、会計上または申告書作成で分からないことが出てきたら専門家に相談して対応することが大切です。
不明な点は税務署の無料相談会を利用するか、経理の実務が複雑な場合は税理士に相談するとよいでしょう。

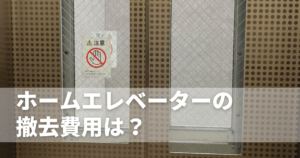
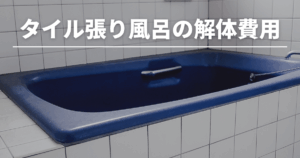
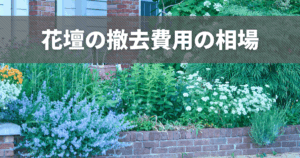

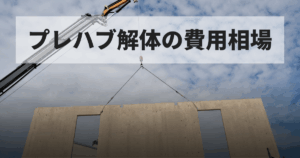
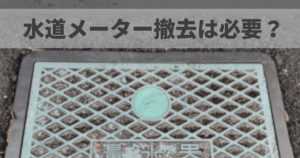
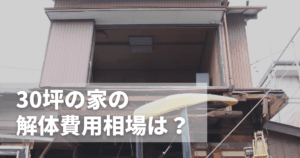


コメント