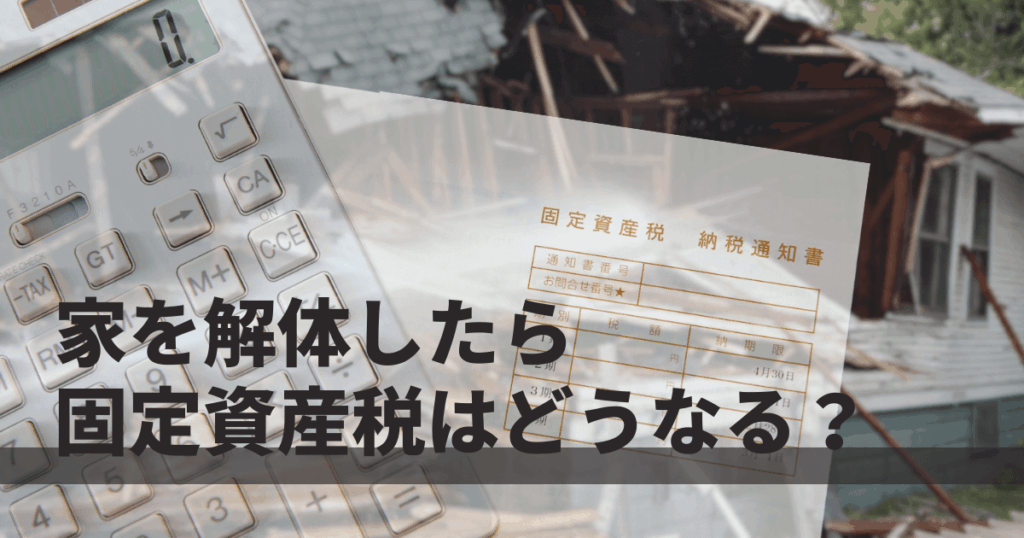
空き家を解体すると固定資産税が増額することを懸念して、解体を決断できないという方は少なくないでしょう。確かに住宅を解体すると土地の固定資産税支払額が増加するのが一般的です。
ただし、自治体の減免制度の利用やその後の土地活用の方法によっては節税も可能です。
この記事では、住宅を解体した場合の固定資産税や、負担を軽減するための事例を紹介します。
家を解体したら固定資産税はどうなる?

家を解体すると建物にかかる固定資産税はなくなります。しかし一方で、土地にかかる固定資産税と都市計画税は上昇するのが一般的です。
ここでは、固定資産税の仕組みから更地にするとなぜ固定資産税が高くなるのかまで解説するので、住宅の解体による税金への影響を知っておきましょう。
固定資産税の基本的な仕組み
固定資産税は、固定資産といわれる土地や家屋、事業用の機械などに対して課税される地方税のひとつです。
不動産物件では戸建て住宅だけでなく、マンションでも土地と家屋の両方に課税されるため、マンションの所有者も固定資産税を支払わなければなりません。
税額は各自治体が評価額を決定し、その金額をもとに算出します。
計算式は、以下になります。
- 固定資産税額=課税標準額×税率1.4%
算出された固定資産税は、固定資産税課税台帳に登録されている人が納付しなければなりません。納付書が郵送されるので、納期限までに納付します。固定資産税は滞納すると延滞金が発生するため注意が必要です。
更地は住宅用地の特例が適用外
住宅を解体して更地にすると、住宅用地の特例が適用外となり、固定資産税と都市計画税の課税額が高くなります。
土地に建物が建っている場合は住宅用地の特例措置により、敷地面積200㎡以下の部分について固定資産税は固定資産税評価額の6分の1、都市計画税は固定資産税評価額の3分の1となります。
200㎡を超える部分についての負担額は固定資産税は評価額の3分の1、都市計画税は3分の2です。
解体により建物の固定資産税はかからなくなるため、固定資産税の総額が必ずしも高くなるとは限りません。土地の評価額が低い場合は家屋を解体することによって固定資産税の支払額が低くなるケースもあります。
解体すると翌年から固定資産税は上昇する
家屋を解体した場合、固定資産税額は翌年から更地の状態で計算されます。これは、固定資産税額は1月1日時点の評価額によって決まるためです。
たとえば、1月10日に解体工事をした場合、更地の固定資産税の支払いは翌年からとなります。つまり、家屋を解体して固定資産税が増額することが予測された場合、1月1日以降に解体すれば、高い固定資産税の支払い時期を遅らせられます。
反対に、解体によって固定資産税が低くなることが予測される場合は年内に解体すると、固定資産税の支払い額を節約できるでしょう。
このように、固定資産税額の増減に合わせて解体時期を決めると節税が可能です。
家を解体するときのポイントと注意点

家屋を解体したときは必要な手続きを行わなければなりません。また、補助金制度を活用すれば解体費用を安くすることもできます。
ここでは、解体の際のポイントや注意点を紹介します。
活用できる助成金・補助金、優遇制度もある
老朽化した空き家を解体する場合は、助成金・補助金を活用できる場合があります。そのなかでも代表的なものが、老朽危険家屋解体撤去補助金です。
老朽化危険家屋解体撤去補助金は、国の空き家再生等推進事業の一貫として国と自治体が連携して解体費用を支援する制度です。
補助金を受け取るには耐震診断を受け、自治体の認定を受けなければなりませんが、一般的に解体費用の5分の1から2分の1程度が支給されるため、解体する物件が該当する場合は申請することをおすすめします。
老朽化危険家屋解体撤去補助金のほかにも、自治体によってさまざまな助成金や優遇制度が用意されています。解体を検討している場合は自治体の窓口に相談してみるとよいでしょう。
解体後は建物滅失登記の手続きが必要
建物を取り壊したときには法務局で建物滅失登記が必要です。建物滅失登記は、建物を解体や災害等で失った際にその事実を登記簿上で更新する手続きです。
建物滅失登記は、解体した建物の所有者または登記名義人が、滅失した日から1か月以内に法務局で手続きしなければなりません。建物滅失登記を行っていないと、土地を売却できなかったり誤って固定資産税を課税されるリスクがあるので、忘れずに行いましょう。
滅失登記手続きは、自分でも行えますが、土地家屋調査士に代行してもらえます。
空き家解体後でも固定資産税を減免する自治体もある

空き家問題が深刻化していることから、近年では空き家解体後も固定資産税を減免する自治体が多くなっています。
減免を受けるにはいくつかの条件があるので、制度について事前にしっかり確認しておきましょう。
固定資産税の減免制度とは
各地方自治体では老朽化した空き家の解体を促すため、空き家解体後の土地の固定資産税を一定期間減免する制度を設けています。
空き家が放置されている原因の一つに、解体後に固定資産税の支払額が増加することが挙げられます。所有者に解体したい気持ちがあっても、固定資産税の負担額が上がることを懸念して空き家をそのままにしているケースは珍しくありません。
このような空き家所有者の事情に対応するために、自治体が支援しているのがこの制度です。
対象となる空き家
解体後に固定資産税の減免制度を受けられる空き家は、基本的に住宅用地の特例が解除されていない物件です。
自治体に特定空き家に認定されると住宅用地の特例が解除され、減免制度を受けられなくなるため注意しましょう。
自治体によっては要件を「特定空家等のうち、勧告を受けていないこと」としているケースもありますが、これは上記と同じ意味で、住宅用地の特例が解除されていないことを示しています。
自治体の調査の結果、特定空き家に指定されると、まずは助言・指導が行われます。この時点ではまだ住宅用地の特例は解除されません。
しかし改善されないと勧告となり、特例の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されず、減免制度も受けられなくなります。
減免される期間の目安
固定資産税が減免される期間は、地方自治体により異なりますが一般的に2~10年です。1月1日時点で固定資産税評価額が決まるので、解体した翌年から適用されます。
一方で売買等、相続以外で土地の所有者が変わったときや営利目的で土地を利用することになった場合、土地に建物を建築して居住用として利用した場合、土地にゴミや雑草があふれるなどして周囲に悪影響を及ぼしている場合は減免が期間内でも終了となります。
空き家を解体して更地にするメリット

では、空き家を解体して更地にするとどのようなメリットがあるのでしょうか。
以下に代表的なメリットを紹介するので、空き家を解体するか迷っている場合は検討の材料にしましょう。
家の維持管理費用が必要なくなる
空き家を解体してしまえば、建物を管理する手間と費用が不要になります。
土地に建物が建っていると、定期的にメンテナンスしなければなりません。掃除では水や電気を使うため、光熱費もかかります。
また、屋根や外壁は次第に劣化していくので、およそ10年に1回を目安に塗り替えが必要です。空き家は防犯対策も必要なため、庭の草むしりや掃除も重要です。
とはいえ、空き家に頻繁に訪れて手入れをしなければならないのは面倒でしょう。遠方にある空き家はなかなか足を運べないということも珍しくありません。このような手間を解消するためには、建物を解体して更地にしてしまった方がよいでしょう。
買主が見つけやすくなる
土地の売却を検討している場合、建物が残っている状態よりも更地になっていた方が買い手が見つかりやすい傾向があります。
老朽化した住宅が建っている土地は、買主が解体して新たに住宅を新築する必要があるため、その分費用がかかってしまいます。よほど土地の条件が良い場合でなければ購入を躊躇されたり、販売価格の値引交渉をされたりしやすくなるでしょう。
ただし、建物が古くなくきれいな状態の場合は建物付きでも買い手がつきやすいケースもあります。どちらが有利か迷っている場合は、不動産業者などに相談して決めるとよいでしょう。
特定空家に指定されると固定資産税は高くなる
適正な管理がされていない空き家は特定空き家に指定され、住宅用地の特例が解除されることで、固定資産税額は更地と同等の最大6倍となります。
特定空き家の認定基準は、以下の通りです。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家でも管理していれば特定空き家に指定されることはないので、解体の予定がない場合は定期的にメンテナンスをしておきましょう。
空き家解体後の固定資産税を安くする方法

ここでは空き家解体後に固定資産税を節税するための事例を紹介します。
解体後の土地活用や固定資産税の支払いでお悩みの場合は、土地に合った活用方法を取り入れて賢く税金対策をしましょう。
公益のための固定資産とする
私有地でも公益性の高い土地は固定資産税が減免されます。代表的なものに私道や公園がありますが、町会事務所や各種学校なども公益のための固定資産です。
マンションやアパートなどの集合住宅を建てた敷地の一部を公園にして誰でも楽しめる憩いの場として活用するのも一つの方法です。
公益性の高い固定資産の減免基準は市町村ごとに異なります。検討している場合は市町村の窓口で相談しておくとよいでしょう。
解体の時期を見極める
上でもご紹介した通り、固定資産税の支払額が決まる賦課期日は1月1日です。そのため、解体の時期を調節すると税金を抑えられるケースがあります。
解体により税額が増加しそうな場合は年が明けてから、反対に税額が減少しそうな場合は年内に解体工事を完了できるようにするとお得です。
また、解体工事は業者の閑散期に依頼すると解体費用を抑えられる場合があります。解体工事業者の閑散期は一般的に6~9月、12~1月です。
ただし、年内に解体工事を完了させたい場合は11月以前の受け付けとしている業者も多いので、事前に営業担当者に確認しておくとよいでしょう。
駐車場として活用する
駐車場は複雑な設備がないため、建物よりも評価額が低いことが多く、固定資産税を節税しやすいといえます。
駐車場は形式によって必要な設備が異なり、税額にも差が出ます。駐車場の形式は大きく分けてコインパーキング式と月極契約式の2つです。コインパーキング式は精算機やロック板などの設置、アスファルト舗装などが必要なため、固定資産税が高額になる傾向があります。
一方で、月極駐車場は賃料が銀行振込などとなり、精算機を設置する必要がなく、砂利敷きにロープで仕切りを引くといった簡易なものでも問題ありません。その場合、固定資産税は安くなります。
建て替えてアパートにする
空家を解体して賃貸用アパートを建設すれば、土地と建物両方に対して固定資産税の節税が可能です。アパートが建っている土地は、小規模住宅用地の特例が適用になり、200㎡以下の部分については固定資産税が6分の1になります。
さらに、新築でアパートを建てた場合、税額が3年間は2分の1になります。これは、新築の場合は当初の固定資産税の負担が大きいため、それを軽減するのが理由です。
アパート経営は、固定資産税が優遇されるだけでなく、賃料による定期収入も見込めるので、更地のままにしておくよりもお得といえるでしょう。
解体後に土地を売却する
空き家を解体してから、できるだけ早く土地を売却できれば、固定資産税の支払いを短期間にすることができます。
ただし、解体し更地にしてから買い手がつかない状態が長期間続くと、上昇した固定資産税を支払い続けることになるでしょう。
そこで、更地渡しという建物が建った状態で売りに出し、売買契約後に更地にして引き渡しする方法もあります。この場合なら固定資産税が引き上げられる前に売却できるため、固定資産税を節税できるでしょう。
まとめ
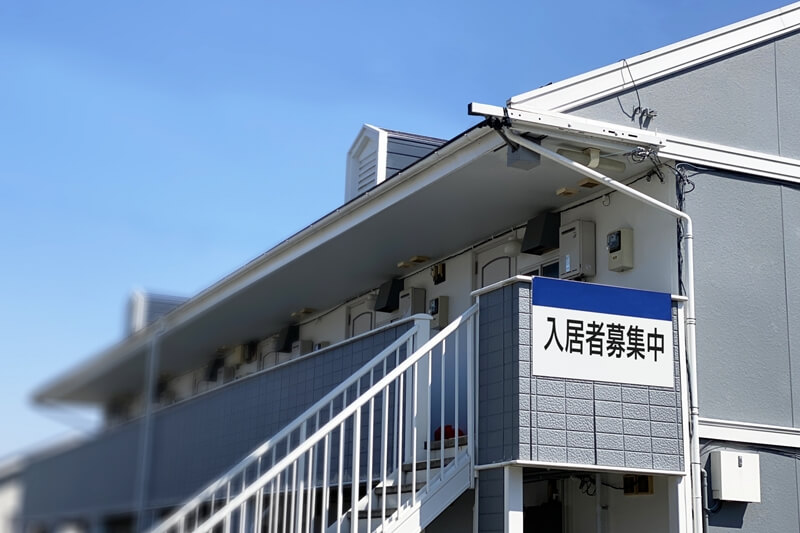
住宅を解体して更地にすると住宅用地の特例措置がなくなり、土地にかかる固定資産税が高くなります。
ただし、土地の評価額が低いなど、条件によっては固定資産税の負担額が低くなる場合があるだけでなく、アパートや駐車場経営をするなど、税金負担に関する不安の解決策はさまざまあります。
事前に自治体の窓口や専門家、解体業者に相談して、最適な方法を検討しておくと安心です。









コメント