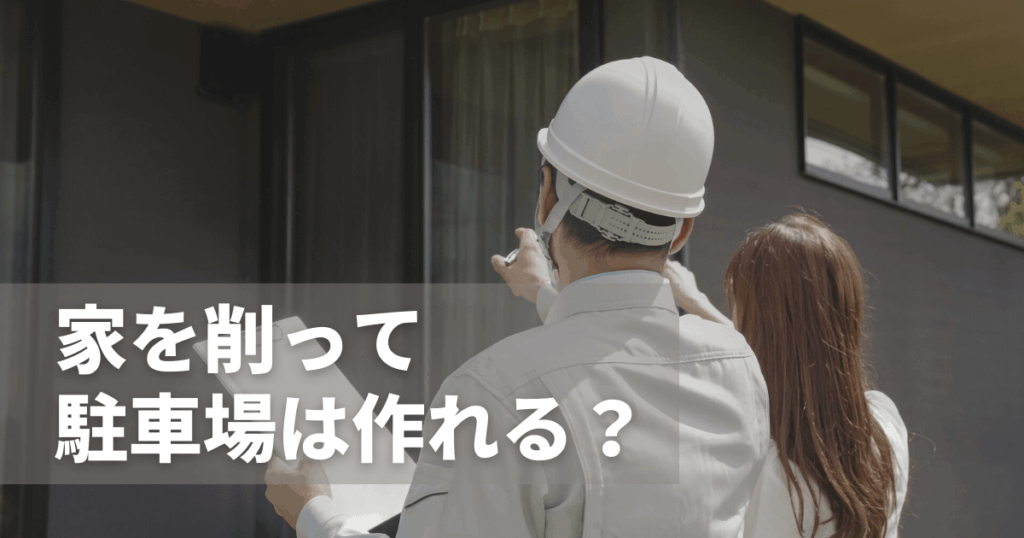
駐車場がほしいけど敷地が狭くて停められない場合、家を削る減築工事を行ってスペースを確保する方法があります。ただし、減築して駐車場をつくるときにはいくつか確認事項や注意点があるため、慎重に行わなければなりません。
この記事では、家を削って駐車場をつくる際に気をつけておきたいことを紹介します。
家を削って駐車場は可能なの?

家を削ってできたスペースを駐車場にすることは、もちろん可能です。ただし、いくつか注意しておきたい点があるので、後悔しないためにしっかりチェックして決断しましょう。
道路条件の確認
家を削って駐車場を作る場合、接道義務や間口の幅など道路条件の確認が重要です。接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合に、原則として敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、という決まりです。
家を減築したことによって接道義務を満たせなくなった場合、建物の建て替えができなくなる場合があるため注意しておかなければなりません。
また、駐車場を作る場合は前面道路の幅・間口に注意が必要です。車を駐車するためには、前面道路が幅4mの場合、道路面の間口は3.6m以上にしたほうがよいでしょう。前面道路の幅が狭い場合は、駐車場の間口をさらに広げるなどして対策します。
参考:建築基準法 第四十三条
構造の負荷を確認
建物を削る範囲が大きい場合は、構造の負荷を確認し、建築確認申請を行う必要があります。
減築リフォームでは原則として建築確認申請は不要とされています。これはただ面積を減らすだけであれば耐震性は落ちませんし、同じ外壁材、屋根材で仕上げれば耐火性能も変わらないためです。
しかし、二階建ての建物の二階部分を減築する場合などは、壁や柱、梁などを削ることになり、耐震性などに影響を及ぼす可能性があるため、確認申請で建物の構造を確かめる必要があります。
また、減築と同時に10㎡を超える増築をした場合にも確認申請が必要です。
外構・排水と車両動線
駐車場を作る場合、外構設備や動線について配慮すると利便性が高まります。敷地内への他者の侵入を防ぐため、駐車場にはカーゲートやポールチェーン、フェンスなどの外構設備を設置すると安心です。
また、地面をコンクリートやタイルで舗装した場合、雨水が地面に吸収されにくくなり、水たまりができやすくなります。水はけを良くするため、駐車場に傾斜を設けて排水されやすくする設計が必要です。
さらに、車両の出し入れの動線、車から玄関までの人の動線を意識したレイアウトにすると、駐車場が使いやすくなります。
税務・登記の扱い
減築工事は床面積が変わるため、登記申請が必要です。
床面積の変更があった日から1か月以内に申請する必要があるので、あらかじめ準備しておきましょう。登記申請により固定資産税が新しい床面積に対してかかるため、支払額を軽減できます。
減築したスペースを四隅を壁で覆われたガレージにした場合は固定資産税の対象となりますが、土間コンクリートを打設しただけでは固定資産税の対象にはならないので、節税したいなら工事後の駐車場のスタイルにも注意が必要です。
駐車場作りが難航しやすいケース

土地の条件によっては駐車場を設置する際に特殊な対応をしなければならないケースがあります。
ここでは駐車場づくりで気をつけておいた方がよいケースを紹介するので、自宅の条件と照らし合わせて確認してみましょう。
2項道路で大きなセットバックが必要
いわゆる2項道路に面している場合、セットバックが必要となり、駐車場として利用できる面積が狭くなるケースがあります。
2項道路とは、建築基準法第42条2項で定められた道路のことで、「みなし道路」とも呼ばれるものです。
建物は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりませんが、古い道路など、幅員4m未満の道路の場合は道を広げるために自分の土地の一部を道路として提供しなければならず、これをセットバックと言います。
セットバックは拒否できず、さらにその分は道路として提供するため、駐車場にはできません。セットバックが必要な場合は、駐車場として十分なスペースが確保できるか確認が必要です。
参考:建築基準法 第四十三条
乗入れ予定位置が交差点に近い
交差点近くなどの土地では車の乗入れ位置に制約が出る場合があるので、事前に確認が必要です。
規制により乗入れ口が設置できない場所の代表例は以下のような場所です。
- 交差点の中および交差点の側端(停止線がある場合は停止線)または曲がり角から5m以内
- 横断歩道から前後5m以内
- バス停車帯内部、バス停から前後10m以内
- トンネルから前後50m以内
- 横断歩道端の昇降口から5m以内
- 地下道・地下鉄の出入口から5m以内
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後10m以内
また、乗入れ口の設置場所は、原則として一箇所であることを知っておきましょう。
実質的に大掛かりな構造改修が必要
一見駐車場を増設するだけの工事のつもりが、外構の構造を大きく変える必要があり、想定以上にコストがかかってしまうケースがあります。
例えば、駐車スペースのためにアプローチや外階段を大幅に移動させなければならないケースでは、門扉の位置やブロック塀、玄関ドアの庇の位置など、外構全体を大幅に変更しなければならない場合があります。
とくにスペースに余裕がない場合は、外構デザインを変更する必要があるかどうか、よく検討しましょう。
敷地の高低差が大きい
敷地の高低差が大きい場所に駐車場を設置する場合、法律の確認や地盤の工事が発生するため、平坦な土地に駐車場を施工する場合よりも確認事項が多くなります。
2m以上の高低差のある土地で擁壁の新設や改修をする場合、多くの自治体で規制の対象となります。該当する土地では事前に自治体への申請が必要です。
さらに、高低差がある土地では、地盤をしっかりと締め固め、土留め工事を行い土の流出を防ぎます。このような、段差が大きく擁壁工事が必要な場合は工事費用も高額になる傾向があるため、事前にいくつかの業者から見積もりを取り、比較検討が必要です。
構造安全の要点

家を削る場合、構造の安全を確保できていなければ工事を進められません。以下に減築リフォームでとくに重要な構造のポイントを解説します。
基本的には業者がしっかりと確認しながら施工してくれますが、施主としても知っておくと打ち合わせもスムーズに進むはずです。
耐力壁・柱・梁を触る場合の補強設計
減築リフォームの途中で、建物の劣化やシロアリ被害が発覚した場合、追加工事が必要です。柱が腐食していた場合や基礎が劣化している場合、そのままリフォームを進めると耐震性に問題が発生するおそれがあるため、補修工事を行います。
また、すべての建物で自由に減築できるわけではなく、耐震性や劣化状況、建ぺい率などの制約や技術的な限界があるのも現実です。減築を検討している場合は事前に専門家や自治体へ相談することをおすすめします。
開口位置の最適化(たわみ・ねじれ・雨仕舞い)
家を削った部分の壁の開口部は、大きさや位置を適切に計画して建物のたわみやねじれを最小限にしなければなりません。
開口部は耐力壁の剛性を削るため、建物の面としての強さが低下してしまいます。そのため、新しい壁を作る場合は既存の梁、桁、土台の腐食やシロアリの有無を確認してから、確実に接合します。
減築工事では、削った部分に新しい外壁や屋根を取り付けなければなりません。そのとき、つなげた部分から雨漏りしないように雨仕舞いなどで対策して防水性を確保します。
専門家に依頼すべき検討範囲
減築に関して構造体の補強や確認申請の必要性については専門家に判断を仰ぎましょう。
減築で建物の耐震性が低下することのないよう、適切な補強が必要です。補強に関しては業者が建物の状態や図面を確認したうえで適切に行ってくれます。
確認申請は減築工事については基本的に必要ありません。しかし、大規模な修繕に該当する場合は確認申請が必要になる場合があります。また減築と増築を同時に行う場合は原則として増築とみなされ、確認申請が必要です。
どのような場合に確認申請が必要かどうかは分かりにくいこともあるので、業者に任せましょう。
駐車場リフォームの費用を抑えるコツ

家を削って駐車場にリフォームする場合、想定以上に費用がかかる場合があります。
ここでは、駐車場リフォームの費用を節約するコツを紹介するので、予算内に工事を完成させるための参考にしてください。
メリハリをつけて整備する
駐車場を設置する際は費用をかける部分とかけない部分のメリハリも大切です。たとえば、駐車場の門扉をシャッターにする代わりに床材は単価の安い砂利や砕石にするなどすると費用を抑えられます。
シャッターと砂利なら防犯性が高い外構にできます。一方で砂利は車を傷つけることもあるので、大切な車を安心して出し入れしたいならコンクリートやアスファルトで舗装したほうが安心です。
エクステリアの素材を選ぶときは住む人の外構の使い方を整理して、外観イメージと利便性を比較して選択すると満足度が高まります。
複数社から見積もりをとる
減築リフォームは通常のリフォーム工事や解体工事よりも作業項目が多く、内容も複雑になります。そのため、複数社から相見積もりを取り、十分に検討して業者選びをしましょう。
高低差がある土地などで擁壁工事などが発生する場合は、土木工事も可能な会社または土木工事業者と連携している解体業者に見積もりを依頼するとスムーズです。見積もりを依頼する場合は業者のホームページで施工事例の写真などをチェックし、経験のある業者に問い合わせると安心です。
また、工事費用は予算の1~2割ほど予備費としてとっておくと、いざ解体してから不具合が発覚した場合にも慌てずに済みます。
駐車場を作るときによくある質問

ここでは、駐車場を設置する際によく挙がる質問とその解答・注意点を紹介します。
家を削る工事はスペースを有効活用できる一方で、一度施工したらもとに戻せないというデメリットもあります。後悔なく駐車場をリフォームするためにも、あらかじめ疑問を解消しておきましょう。
家を削らずに駐車場を確保できる代替案は?
外構にある程度のスペースがある場合は無理に家を削る必要はありません。庭が道路に面しており、スペースがある場合は駐車場の拡張工事は比較的簡単です。
また、塀やフェンスを撤去して、車を停める角度を工夫するだけでも駐車スペースを確保できるケースもあります。
外構設備の変更に伴い、隣家と隣接する場所を工事するときは隣家へ声をかけ、承諾を得てから工事しましょう。駐車場を拡大することで隣家に圧迫感を与えたりすると苦情やトラブルが起こった場合の責任問題に発展するため十分注意が必要です。
擁壁を削って駐車場を作る費用はいくらですか?
擁壁を削って駐車場をつくる費用は、屋根のないオープンの1~2台用のカースペースで約200万円が目安です。堀込車庫を造る場合は1台分のスペースで約300万円が相場となります。
作業の流れとしては、石垣などの擁壁撤去・掘削工事のあと、コンクリート吹付などで法面保護、排水設備を設置し、床面を舗装します。
擁壁を削る場合、庭と擁壁を解体して道路と同じ高さにそろえます。擁壁が高ければその分費用も高額になります。高低差のある駐車場では階段やスロープも必要です。
高低差のある庭に駐車場を作る費用はいくらですか?
道路よりも高い場所に住宅がある家の庭に駐車場を施工する場合、上でご紹介したように擁壁工事が必要な場合は200万円程度費用がかかります。
反対に道路よりも低い土地に駐車場を設置する場合は、造成工事で盛り土をするのが基本的な方法です。盛り土工事の費用は傾斜の大きさによって大きく変わりますが、1㎡あたり約7,000円以上かかります。
駐車場の形式としてはビルトインガレージが一般的で、費用相場は車1台分で約200~400万円です。
カーポートやゲートは同時に建てても問題ない?
減築と同時にカーポートを設置すると増築扱いとなり、建築確認申請が必要になる可能性があります。カーポートも建築物とみなされるため、とくに10平米を超えるカーポートや、防火地域・準防火地域に設置する場合は、建築確認申請が必要になる可能性が高いため注意が必要です。
一方、カーゲートは同時に設置しても確認申請は必要ないのが一般的です。駐車場や外構全体のデザインと統一したタイプを選べば、敷地全体にまとまりが生まれるでしょう。
家を削って外構設備を設置したい場合は、必要な手続き等について業者に確認しながら進めると安心です。
売却時の資産価値への影響は?
減築すると売却時の価格が下がる可能性があります。その理由は、減築すると建物の床面積が小さくなり、不動産評価額が下がる可能性が高まるためです。中古物件の売却時は新築よりも価格が落ちるとはいえ、減築により想定以上に評価額が下がる場合もあります。
将来自宅を売却する予定がある場合は、販売価格への影響を考慮し、減築ではなくリノベーションをしたりメンテナンスをしたりしながら家を維持する選択肢も考慮するとよいでしょう。
まとめ

家を削って駐車場を設置すると、使わないスペースを有効活用できるだけでなく、建物の耐震性がアップするなどのメリットがあります。
工事を計画している場合は、業者に現地調査を依頼したうえで庭のリフォームと減築両方の見積書を出してもらい、比較して考えることをおすすめします。また、業者に助成金などについても相談しながらどの方法が納得いくか、よく考えて決めると後悔のないリフォームができるはずです。









コメント