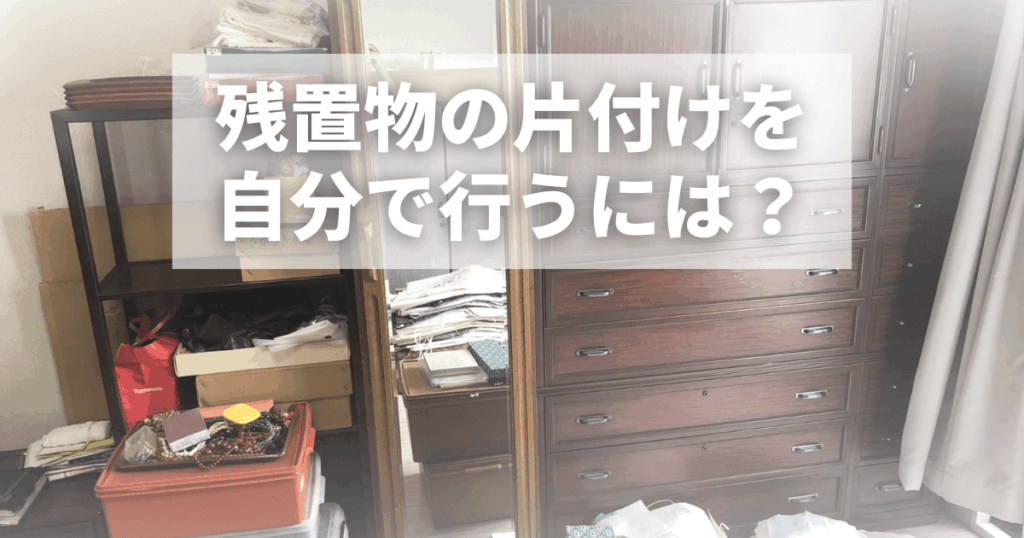
解体工事では着工前までに残置物を撤去して家の中を空にしなければなりません。もちろん、解体業者に依頼すれば撤去してもらえますが、残置物の量に応じて費用がかかります。
費用を削減しようと、自分で片付けようと考える方も多いかと思いますが、どのようにすればよいのでしょうか。今回は解体工事前の家財道具の片付け方法や注意点を解説します。
自分で残置物を整理するときの基本知識

まずは自分で残置物を整理するときに知っておきたい基本的な情報を紹介します。解体工事を計画している場合は以下の項目をチェックして、早めにスケジュールを立てるようにしてください。
最低限の費用は発生する
自分で残置物を撤去する場合、解体業者に依頼する場合に比べて大幅に費用を削減できますが、最低限の処分費用が発生することは理解しておきましょう。
たとえば、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目は、購入した店舗に引き取ってもらう必要があります。リサイクル料金はメーカーによって異なるものの、以下の通りです。
- エアコン:972円~
- 液晶・プラズマテレビ(16型以上):2,916円~
- 冷蔵庫(171L以上):4,644円~
- 洗濯機:2484円~
これら全てを回収してもらうと、最低でもおよそ11,000円かかることになります。事前に処分するものの数を確認しておき、費用の目安を計算しておくとよいでしょう。
3ヶ月前から片付け始める
残置物を自分で撤去する場合、遅くとも3ヶ月前から取り組むことをおすすめします。粗大ごみの回収は自治体によっては2ヶ月待ちという地域もあり、直前に申し込んでも対応してもらえないケースも珍しくありません。
とくに、引越しシーズンなどの繁忙期は希望の日に予約できないこともあるため、早めに連絡しておく必要があります。
さらに、家の中のものを処分する際はごみの種類ごとに分類しなければならず、想定以上に時間がかかることもあるでしょう。片付けはスケジュールに余裕を持って始めることが大切です。
期限を決めて片付ける
片付けは期限を決めて行うことがポイントです。解体工事に伴う片付けの場合、着工日までに残置物を処分すれば問題ありません。しかし、万が一トラブルが発生したときのために余裕を持って片付けを完了させた方がよいでしょう。
解体業者の営業担当者と相談して、いつまでに片付けを終わらせるか決めておき、スケジュールが遅れるようであればサポートしてもらうなど、対応方法を決めておくと安心です。
自分で残置物を撤去する流れとポイント

ここでは、残置物を自分で撤去・処分する際の流れを紹介します。ポイントを押さえて取り組むことで、限られた時間のなかでスムーズに片づけが進むので、計画する際の参考にしてください。
処分物の仕分け(可燃・粗大・リサイクル)
まず、家の中の荷物を必要なものと処分するものに分け、処分するものをさらに売却できるものと廃棄するものに分けます。
廃棄するものは可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、リサイクルに分別します。可燃ごみはその名の通り焼却処理可能なごみです。不燃ごみは、焼却できない素材でできたものや焼却すると有害なガスを発生させる可能性があるごみです。
粗大ごみは家具やふとん、自転車などの大型のごみで、おおむね一辺の長さが30cm以上のものを指します。
リサイクルしなければならないのはエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目です。そのほかパソコン、スマートフォンなどの小型家電もリサイクルが推奨されています。さらに使える家具や家電はリサイクルに回せます。
各自治体のゴミ出しルールの確認
ごみを出す前に自治体のゴミのルールを確認します。ごみの出し方、分別方法は地域によって異なるため、自治体のウェブサイトで確認すると確実です。個別の相談は市町村の担当部署の窓口に問い合わせてください。
可燃ごみと不燃ごみ、危険物は自治体が指定する収集日に指定の場所に出します。これらの一般ごみは地域によっては専用のゴミ袋を購入する必要がありますが、回収は基本的に無料です。粗大ごみは事前に申し込み、有料で回収されます。
家電リサイクル法対象品の処分
家電リサイクル法の対象となるエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目は、定められた方法に従って処分しなければなりません。
処分の方法は、以下のいずれかです。
- 家電量販店に引き取ってもらう
- 指定引取場所に自分で持ち込む
- 市町村の指定業者に収集を依頼する
購入した販売店が分かる場合は販売店で家電リサイクル券を記入したうえで料金を支払い、引き取ってもらいます。指定引取場所に持ち込む場合は事前に郵便局で家電リサイクル券の記入と料金の支払いが必要です。
指定業者に収集を依頼する場合は、引き取り時に家電リサイクル券を記入し料金を支払います。指定業者は市区町村のウェブサイトで確認できます。
粗大ごみの申込方法と回収費用の目安
粗大ごみは多くの場合、ごみ処理券を購入して回収を申し込み、指定された日にごみ処理券を対象のごみに貼って出します。粗大ごみの対象となる大きさや出し方は自治体によって異なるので、事前に確認しておきます。
粗大ごみの処理手数料は地域によって異なりますが、ごみの大きさにより、400~3,200円程度が目安です。自治体のウェブサイトに掲載されている料金表を確認のうえ、ごみ処理券を購入します。
ごみ処理券は、券面が数種類あり、合計して処理費用となるように組み合わせて使用するのが一般的です。
軽トラックのレンタルや運搬のコツ
自分でごみ処理施設に運ぶ場合、運搬するものの大きさによっては軽トラが必要になります。軽トラはレンタカー会社で借りられ、費用は店によって異なるものの、1日5,000~1万円程度が相場です。
また、荷物を積む際に必要なロープやブルーシートは、レンタカー会社のオプションで借りられることもあるので事前に聞いておきましょう。
荷台に積み込む荷物は高さ180cmまで、長さ190cmまでです。積み込むときは背が高く大きいものをはじめに積み、運転席に寄せてロープでしっかりと固定します。また、バックミラーが見えるように確認しながら積み込みましょう。
無料で回収してもらえるリユースサービスの活用
不用品回収業者やリサイクルショップなどを活用して残置物を撤去するのも賢い方法です。無料で回収してもらえるだけでなく、使える家電やきれいな家具があれば査定金額も高くなり、収益につながります。
リサイクルショップは衣類やおもちゃ、日用品、お酒などを総合的に買い取りしており、家のなかのものを一括で片付けられる点が大きなメリットです。
そのほか、模型やフィギュアのようなホビー関連用品や、骨董品、着物などは専門の業者に買い取ってもらった方が買取額が高くなる可能性があります。
また、フリマアプリで売却したり、知人に譲渡したりする方法もあるので、手間や売却益などを考慮して上手に使い分けるとよいでしょう。
自治体が回収できない残置物は専門業者に相談
事務所や事業所の閉鎖などに伴う什器や備品などは、一般ごみとは異なり産業廃棄物に該当するため、自治体では回収できません。そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ専門業者に依頼して処分します。
また、物件を退去した前入居者が残した荷物など、元の所有者がいる残置物も自治体は廃棄物として回収できません。この場合はまずは前入居者や連帯保証人に連絡を取り、処分の同意を得る必要があります。
確実に残置物を処分するための注意点

解体工事では着工までに確実に残置物を処分していないと、撤去作業に余分な作業費と人件費がかかるため、追加料金の対象となってしまいます。
直前になって片づけが間に合わず慌てることのないように、以下の点に注意して早めに対応しておくことが大切です。
1度で片付かないことを想定しておく
片付けは一度では終わらないことは想定しておきましょう。「うちは荷物が少ないから」と思っていても、意外と家の中には家財道具があるものです。判断に迷うものや思い出の品が出てくると、余計に時間がかかってしまいます。
また、大量の一般ごみを一気に出すと近隣住民がごみを出すスペースがなくなるため、配慮して数回に分けて出すこともあるでしょう。
片付け作業は想定以上の時間と労力がかかることを想定して、早めに計画を立てる、場合によってはプロの片づけ業者に相談するなどしましょう。
粗大ゴミ回収の予約は余裕をもって行う
粗大ゴミの回収を予約する際は、早めに予約しましょう。粗大ゴミはすぐに回収してもらえるわけではありません。
自治体によって受付の締切日が収集日の3日前や7日前などと決められているので、事前に確認したうえで予約手続きをするようにしましょう。
繁忙期は2か月待ちになるケースもあるので、数か月前から準備を進めておくと慌てずに済みます。
粗大ゴミは原則として当日の朝出します。回収時間は自治体によって異なり、回収の状況によって時間が前後する可能性があるので、収集日当日も余裕を持って搬出作業をすることがスムーズに粗大ゴミを処分するコツです。
ルールに従って仕分け・持ち込みをする
ごみを出すときは、大型の粗大ごみ、一般ごみに関わらず、ルールに従って処分しましょう。
一般ごみを地域のルールに従わずに出した場合、ごみが回収されずに放置され、周辺環境を悪化させるだけでなく、近隣住民とトラブルになるリスクがあります。
ルールを守らない状況が続くと、自治体から指導、勧告、命令される可能性があるので十分注意が必要です。
処分するものが多岐にわたり、分別するのが大きな負担となっている場合は、プロの片づけ業者への依頼を検討するのも一つの方法です。
複数の業者から見積もりを取り、比較検討して考えてみるとよいでしょう。
貴重品は丁寧に確認する
片付けの際に貴重品を誤って捨てないように注意が必要です。とくに家族で手分けして片付け作業をする場合は、大切なものを処分してしまわないように情報を共有しておきましょう。
貴重品はリストにしておくと安心です。あらかじめ紙などに書き出しておき、まず最初に貴重品をピックアップする作業から始めると誤廃棄を防げます。
そのほか、売れそうなものが見つかったらとりあえず査定に出してみると、意外な金額で買い取ってもらえる可能性があるため、すぐに捨てずに取っておくことをおすすめします。
自力撤去ではなく業者へ頼るべき判断基準

残置物の撤去は、個人では難しいケースもあります。専門家の知識が必要な場合や危険な場合もあるので、以下に該当するようなケースでは無理せず、専門業者に依頼しましょう。
遺品整理を伴うケース
相続した実家を解体するためなど、残置物の片付けが遺品整理を伴う場合は、業者に依頼したほうが負担を軽減できたという事例が多くあります。
遺品整理は故人との思い出の品を処分する必要があるため、感情的に大きな負担となる場合があります。その場合はプロのスタッフに任せることで、大切なものを残しながら、効率よく整理できるでしょう。
自分の手で整理したいものがある場合は業者と片付けの範囲や部屋を分けることも可能なので、見積もりの際に相談すれば対応してくれるはずです。
大型家財や特殊な処分物が多い場合
大型の家具や電化製品など自分で運搬するのは困難なものがある場合は、無理せずに専門業者に依頼してください。大型の家財道具は移動させるだけでも困難なうえ、建物から出すには大変な労力がいります。
とくに一人で片付け作業をする場合は、危険なのでプロに依頼しましょう。実績豊富な業者に見積もりを依頼し、見積書の作業内容の内訳をよく確認したうえで契約すると、失敗を防げます。
相続や売却に関わる法的リスクを避けたい場合
相続や売却に伴うリスクやトラブルを避けたい場合は、遺品整理業者などの専門業者に処分を依頼したほうが安心です。
業者に任せれば、他の相続人から「遺品を隠した」「不当に売却・処分した」と疑われるリスクを避けられます。
また、相続した空き家を放置していると、安全面や衛生面でトラブルが発生する可能性があり、相続人には修繕や清掃などの管理義務が生じます。
空き家が老朽化してる場合や、使い道がない場合は早めに荷物を整理して解体したほうがよいでしょう。
残置物撤去に関するよくある質問

ここでは、解体工事に伴う残置物撤去に関してよくある質問とその解答を紹介します。
解体工事費用に関わる事柄もあるため、事前にチェックしておき、お得に解体工事を実施しましょう。
解体前なら中の荷物も業者にお願いできる?
解体工事前に依頼しておけば、解体業者に残置物の撤去を依頼できます。残置物の撤去も解体工事業者に依頼すれば、着工日を気にせずに一括で片付けと建物の解体ができる点がメリットです。
ただし、解体業者に残置物の撤去を依頼すると、自分で処分やリサイクルに出す場合に比べて費用が高額になることは理解しておきましょう。
また、追加費用の発生を避けるためには、残置物の量を正確に伝えることが大切です。現地調査で現場と間取り図をしっかりと見てもらい、残置物の量を把握してもらってください。
ゴミ屋敷レベルでも自力で残置物撤去できる?
ゴミ屋敷レベルの残置物の量でも自力で片付けは可能です。しかし、ゴミの量や室内の状況によっては個人では対応が難しい場合もあります。これは、ものが多いとゴミの仕分けも大きな手間となるのが理由です。
目安として床が見えている程度のゴミの量であれば、個人でも対応可能と言われています。それ以上のごみがある場合や大型の荷物がある場合は、費用がかかっても業者に依頼したほうが安心です。
まとめ

解体工事に伴う残置物撤去を自分で行う場合は、スケジュールに余裕を持って行いましょう。また、大型の家具や家電がある場合などは運搬作業に危険が伴うため、無理をせずに業者に依頼することが大切です。
手間をかけずに解体と荷物の撤去を行いたい場合は、解体業者の残置物撤去費用と、不用品回収業者などの別の業者の見積もりを比較検討して決めるとよいでしょう。









コメント