
目隠しフェンスを設置して家族のプライバシーを守りたいと考えたときに、気をつけておきたいのがフェンスの高さです。
外構フェンスの高さは法律でルールが定められており、基準の範囲を超えた高さのものは設置できません。かといって低すぎるフェンスは目隠しの役割を果たしてくれませんよね。
この記事では、目隠しフェンスの高さに関する規制や、フェンスの最適なサイズの決め方を紹介します。

目隠しフェンスの高さに関する法律規制

目隠しフェンスの高さは法律でどのように規定されているのでしょうか。
ここでは、法律による高さ規制を紹介するので、基準を超えたフェンスを設置しないよう、しっかりとチェックしておきましょう。
建築基準法による高さ制限
目隠しフェンスをブロック塀の上に設置する場合のフェンスの高さは、建築基準法により、2.2mが上限です。
つまり、ブロック塀の高さ+目隠しフェンスの高さ=2.2m以下でなければなりません。なお、ブロック塀は縦筋、横筋を入れる必要があり、ブロックの高さが1.2mを超える場合は控え壁による補強が必要です。
独立基礎の目隠しフェンスの場合は、必ずしも2.2mが上限ではありません。三段支柱の構造などであれば、
- 独立基礎の高さ+目隠しフェンスの高さ=2.9m
上記まで可能な場合がありますが、自治体によりルールが変わるので事前に確認が必要です。
民法上の規定(境界線付近の設置)
隣家との境界線上に目隠しフェンスを設置する場合、隣人と協議できていない際は、高さは2m以内と民法で定められています。
フェンスの素材についてとくに規定は設けられていませんが、隣家に圧迫感を与えない、日当たりを確保できる素材を選ぶことが大切です。
ご近所トラブルを避けるためにも、設置の際は事前に隣家の了承を得てから工事を開始するようにしましょう。
また、フェンスは境界線から50cm以上離して設置しなければならない点も民法で定められているので、設置場所に注意が必要です。
自治体ごとの条例や規制
目隠しフェンスなど外構設備の新設やリフォームに関して、自治体ごとに条例や規制が設けられている場合があります。
法的に大丈夫だと思っても条例で設置が制限されるケースもあるので、事前に調べておくことが大切です。
条例や法律は頻繁に改正されることが多く、新しくルールが追加されていることもあるので、不安な場合は自治体の窓口に確認しておくと安心です。
また、長く営業を続けていて実績のある外構工事業者は法律にも詳しいので、相談するとよいでしょう。
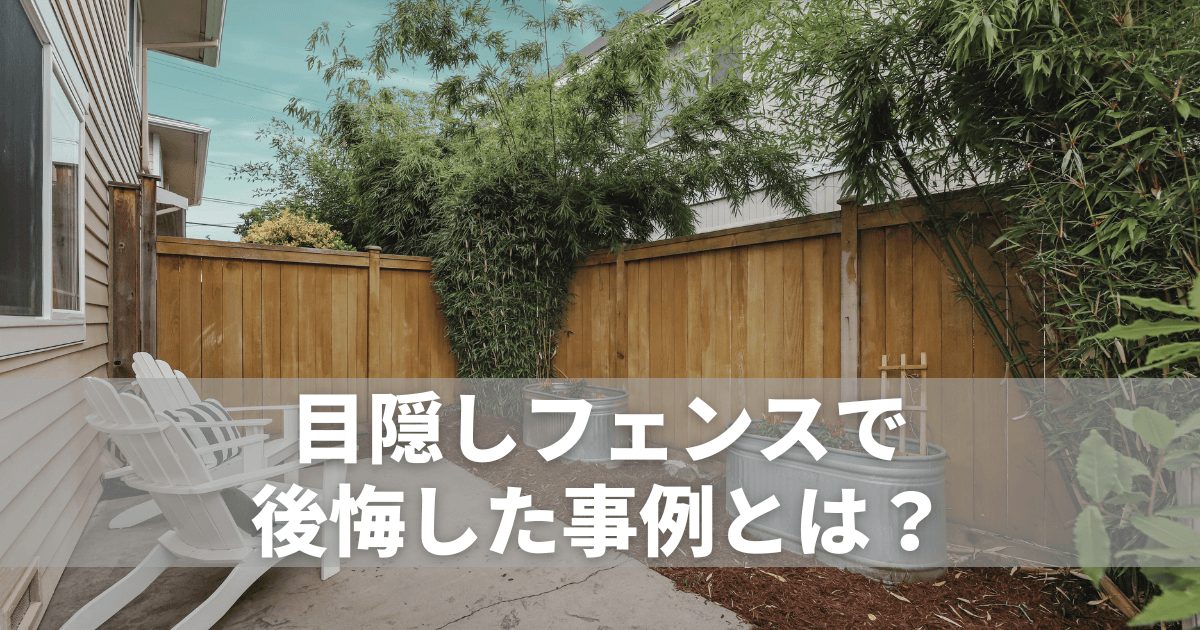
目隠しフェンスの高さを決定する際のポイント

目隠しフェンスの高さはどのように決めればよいのでしょうか。
ここでは、高さを決めるときに考えておきたいポイントを紹介するので、一つずつチェックして後悔のないフェンスを設置しましょう。
設置する目的の明確化
目隠しフェンスの設置を検討している場合はまず、目的を明らかにしましょう。
「道路側からの視線を遮りたい」「隣家の視線が気になる」「お風呂など水回りを使用しているときのプライバシーを確保したい」など、フェンスを使って解消したいお悩みを整理してみます。このとき、紙に書き出しておくと目的も明確になるはずです。
お悩みを外構工事業者に伝えてアドバイスを受けるのもおすすめです。プロの目線から目的に応じたフェンスを提案してもらうと、フェンス選びも簡単になるでしょう。
敷地の状況と周囲環境の考慮
目隠しフェンスの高さは自分の敷地と周囲の敷地との高低差も考慮する必要があります。隣家よりも自宅の地盤が高い場合、低めのフェンスでも十分目線を遮れます。
一方で、隣家よりも自宅の地盤が低い場合は、高さのあるフェンスが必要です。
隣家よりも自宅の地盤が低い場合の目隠しフェンスの設置は、可能な高さの上限のフェンスを設置しても十分な効果を得られないこともあり、難しいケースもあります。
このような場合は樹木を使って目線を遮る方法もあるので検討してみるとよいでしょう。
隣地との関係性とトラブル防止
外構工事をする際に忘れてはならないのが近隣住民との関係性です。とくに隣家との境界にフェンスを設置したい場合は、隣人とトラブルにならないように注意しましょう。
フェンスを設置する前には隣人に挨拶するだけでなく、どのようなデザインのフェンスを設置するか説明し、了承を得てから施工を開始することが大切です。
もし、既存のフェンスを交換したい場合、所有者を確認することを忘れてはいけません。
新築住宅を建設したときに設置したなど、自分が自分の敷地に設置したことが明確であれば問題ありませんが、中古住宅を購入したときからあった、境界線が分からない、という場合は境界線を確認し、所有者を明らかにする必要があります。
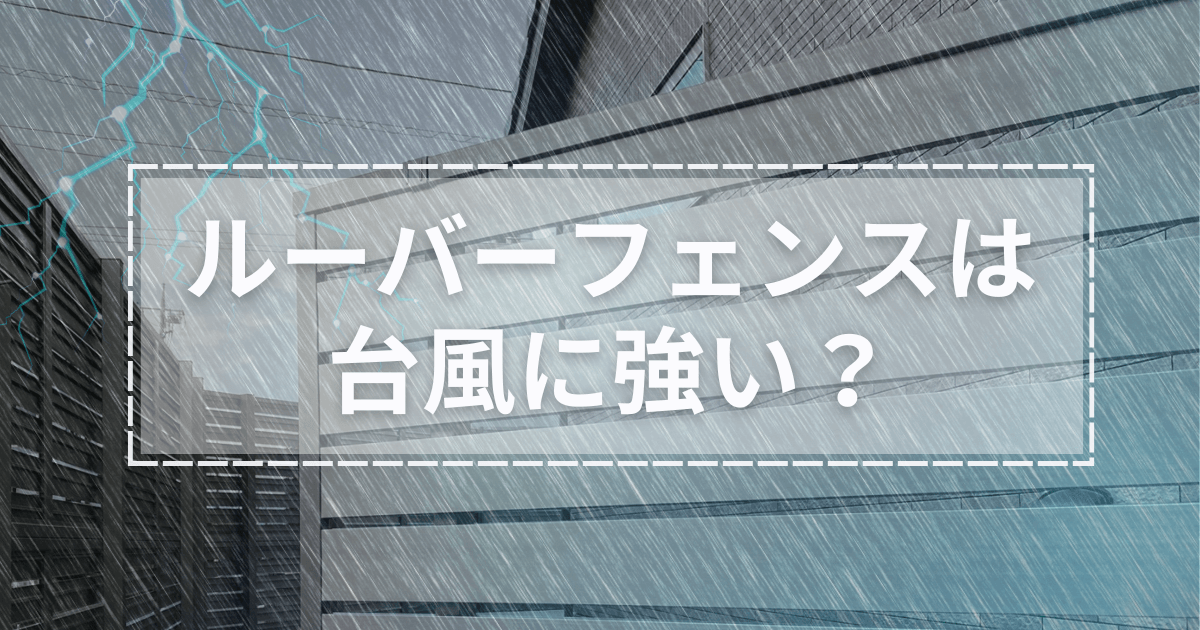
目的別の目隠しフェンスの高さの基準

フェンスは目的によって最適な高さが変わります。目的に応じた高さにしなければ、目線を遮れなかったり、反対に必要以上に高いフェンスを設置してしまい圧迫感を覚えたりすることもあります。
以下で挙げるケース別の高さ基準を参考に最適な高さのフェンスを設置してください。
ブロックの上に設置する
コンクリートブロック塀の上に目隠しフェンスを設置する場合、フェンスの高さは120cmが上限です。
ブロックとフェンスの組み合わせで高さを調節できるので、以下を参考に適切な高さを選択しましょう。
- ブロック4段(80cm)+フェンス80cm=高さ1.6m
- ブロック4段(80cm)+フェンス100cm=高さ1.8m
- ブロック5段(100cm)+フェンス100cm=高さ2m
- ブロック5段(100cm)+フェンス120cm=高さ2.2m
組み合わせによりコストも変わるので、外構工事業者に相談しながら決めると安心です。
座った状態の視線を遮る
屋外のウッドデッキや道路に面した室内に座った状態で、外からの視線を遮りたい場合のフェンスは、高さ120cm程度が目安です。
屋外でお茶やピクニックを楽しみたい場合は、しっかりと目隠しできるタイプのフェンスを設置すると、プライバシーを守りながら外の空間を楽しめるでしょう。
室内で過ごしているときに目線を遮りたい場合は、縦格子フェンスなど、見通しの良いフェンスで効果的に目隠しすると、室内の明るさと開放感も得られます。
防犯を主な目的とする場合
視線を遮りつつ防犯性の高いフェンスにしたい場合は、高さ2m前後が適しているといわれています。
ただし、隙間のない目隠しフェンスは一度侵入されてしまうと外から見えにくく、不審者にとって都合のよい隠れ場所になってしまいます。
そのため、隙間のあるフェンスを採用するなどして敷地内の見通しを確保することが大切です。このとき、横格子よりも縦格子にした方が足を掛ける場所が少なくなり、乗り越えにくいといえるでしょう。
立った状態の視線を遮る
立った状態でもプライバシーを確保したい場合は、フェンスの高さは180~200cmが目安です。
大人の男性の目線の高さは約160cm、女性の目線の高さは約140cmです。実際に立ってみてメジャーで測り、ベストな高さを決めると失敗を防げます。
リビングで立った状態の目線を遮りたい場合は、リビングの床面が地盤から40~50cm高いことを考慮して決めましょう。
立った状態の目線を遮りたい場合、フェンスが高くなりがちです。高いフェンスは圧迫感がでる場合もあるので、1m~2mくらいの植栽と組み合わせると、人工物ばかりにならず圧迫感を軽減できます。
高所からの視線を遮る
隣家の2階やマンションなど高いところからの視線を遮りたい場合は、背の高いフェンスを選びましょう。
ただ、目線の位置によってはフェンスだけでは視線をカットしきれず、あまり現実的ではありません。
庭でレジャーをするときはDIYでも設置できるシェードやオーニングを活用すると、長さの調整や、閉じることもでき、さらに必要に応じて日陰も作れるので便利です。
注文住宅の計画中でこれから建物と外構の設計を決める場合は、視線の位置にカーポートを配置して、カーポートの屋根で目線を遮る方法も有効です。

目隠しを高くするデメリットはある?

目隠し効果を高めたいからといって、目隠しフェンスを高くし過ぎると快適性が損なわれ、設置を後悔してしまうケースがあります。
ここでは目隠しフェンスを高くするデメリットを紹介するので、参考にしながら効果的に目線を遮りましょう。
日当たりが悪くなる
フェンスを設置する方向によっては日当たりが悪くなり、庭や部屋の中が暗くなってしまうこともあります。
日当たりが悪くなるとガーデニングの植物の生育が悪くなるほか、庭がジメジメしてカビや苔、虫が発生しやすくなり、不快感の原因となってしまうので注意しましょう。
フェンスにより日陰になる可能性がある場合は格子状のフェンスを設置すると、採光もできて快適です。
目隠しフェンスの日陰を隣家に作ってしまう可能性もあるので、隣家への影響も考慮したフェンス選びが大切です。
圧迫感や閉塞感がある
背の高い目隠しフェンスは圧迫感や閉塞感の原因となる場合がある点がデメリットです。
とくに狭いスペース全体を囲うように背の高いフェンスを設置すると開放感が損なわれ、エクステリアが狭く感じてしまうこともあります。
圧迫感を軽減するには、隙間の少ないフェンスは必要な場所のみに限定するなどして対策します。目線を遮りたい場所のみしっかりと目隠しをすれば風通しが良く、開放感のある外構になります。
フェンス以外にも植栽や部分的にスクリーンフェンスを設置するなどの方法もあるので、外構工事業者に相談してみましょう。
防犯対策が必要になる
上でも紹介しましたが、隙間がなく高さのある目隠しフェンスは乗り越えにくい一方で、一度侵入されてしまうと外から不審者が見えにくくなります。
外からの見通しが悪いと不審者は侵入さえしてしまえば、敷地内で行動しやすくなるので、かえって狙われやすい外構になってしまいます。
格子状のフェンスは日当たりの確保、圧迫感の解消とともに見通しをよくするためにもおすすめです。目線が気になる箇所には植栽を配置するなどして工夫すると、ストレスも軽減できます。
また、侵入経路になりやすい場所はフェンス周辺に化粧砂利を敷くと、おしゃれに防犯性を高められます。
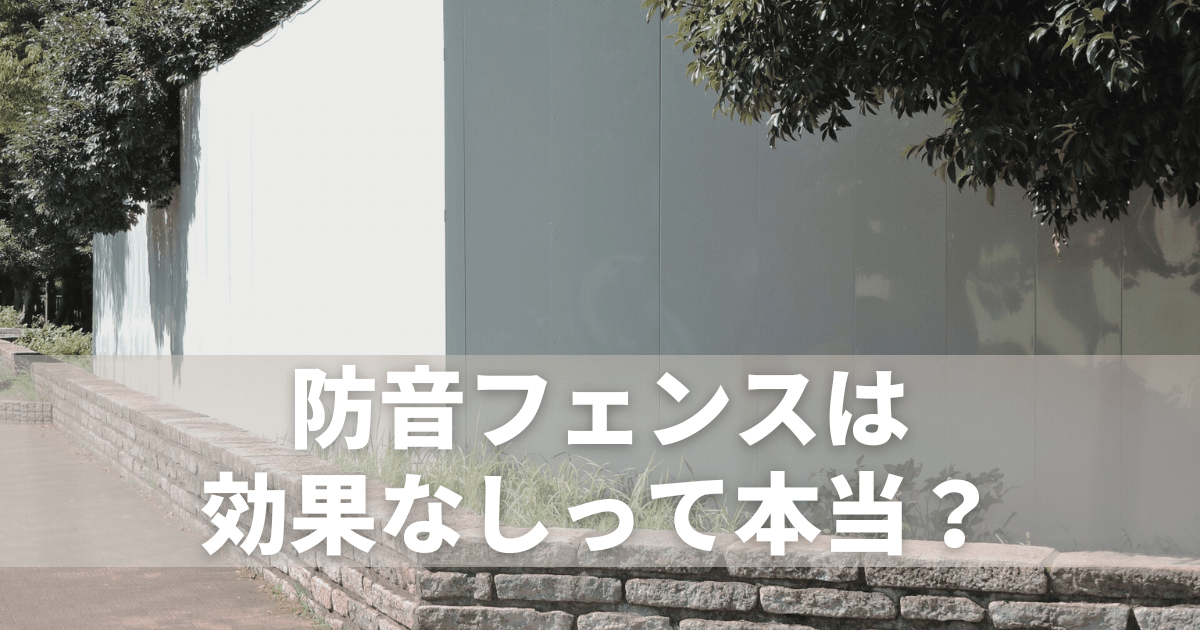
目隠しフェンス設置の注意点

ここでは目隠しフェンスを設置する際に注意しておきたいことを紹介します。
目隠し効果ばかりに注目していると見逃しがちなものばかりなので、設置を計画するときは忘れずに確認するようにしましょう。
ブロック基礎と独立基礎の違い
フェンスの工法にはブロック基礎と独立基礎があります。ブロック基礎はブロックを積んだ上にフェンスを設置する方法で、外構フェンスでは一般的な工法です。
ブロックはただ積むのではなく、土を掘り、砕石を敷いた上に鉄筋を組み、コンクリートのブロックベースを敷いたところにブロックを積みます。ブロックのなかにも鉄筋を配置する必要があり、強度が高い仕組みになっています。
独立基礎は地面にコンクリート製の基礎を設置し、上部にフェンスの柱を設置するタイプの基礎です。必要な根入れ深さの穴を掘り、基礎をモルタルで固定します。
ブロック基礎に比べて費用が安い点がメリットですが、風圧に弱いため、メッシュフェンスなど風通しのよいフェンスに向いています。
耐久性とメンテナンスの考慮
フェンス選びの際はフェンスの耐久性にも注目しましょう。フェンスは素材により、寿命に大きく違いがあります。
外構フェンスで広く使用されているアルミは、30年もつともいわれており、人気の素材です。色と形状の種類も豊富なので、迷ったらアルミ素材を選ぶのがおすすめです。
一方で、木製フェンスは雨や紫外線に弱いため、耐久性が低いというデメリットを持っています。長く使用するためには塗り替えなどのメンテナンスが必須です。
メンテナンスを怠るとフェンスが倒壊するなどして近隣住民や通行人へ被害を及ぼすおそれがあり、責任を問われてしまいます。
そのほか、交換の間隔が狭くコストパフォーマンスが低くなるため、できるだけ耐久性の高い素材を選んだ方がよいでしょう。
道路沿いでは死角への注意が必要
道路沿いの目隠しフェンスは死角が大きくならないよう注意が必要です。高さがあり、隙間のないフェンスを設置すると、車の出し入れの際に見通しを確保できず、危険です。
ある程度の通行量のある道路に面している場合や、角地は接触事故や転倒事故のおそれがあります。
自分だけでなく、隣人や通行する車が事故に遭ってしまう可能性を考えて、十分配慮したフェンスを設置しなければなりません。
玄関や門柱付近、駐車場の前のフェンスは、視界を確保するために、高さ1.2~1.5m未満を目安にしましょう。
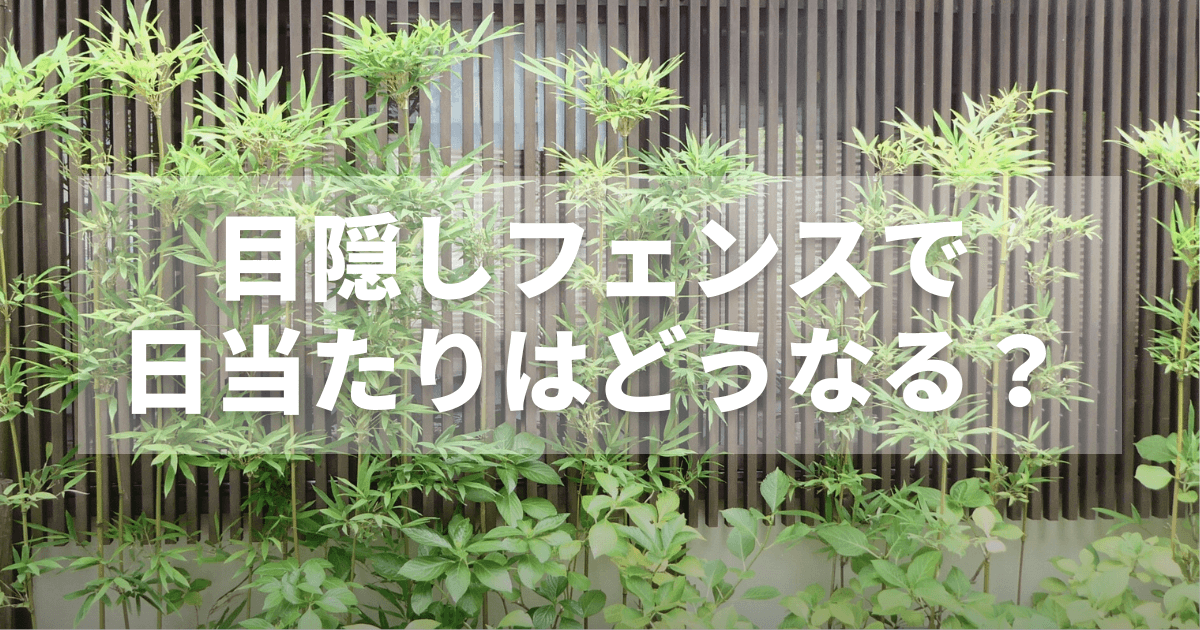
まとめ

目隠しフェンスは法律で高さに制限があります。住まいのプライバシーをしっかり守りながら、安全性と快適さを得るには、フェンスだけでなく、植栽やほかの外構アイテムを組み合わせると効果的です。
外構アイテムの有無で外構工事の満足度は大きく変わるので、まずは業者に気軽に相談、見積りを依頼してみるとよいでしょう。

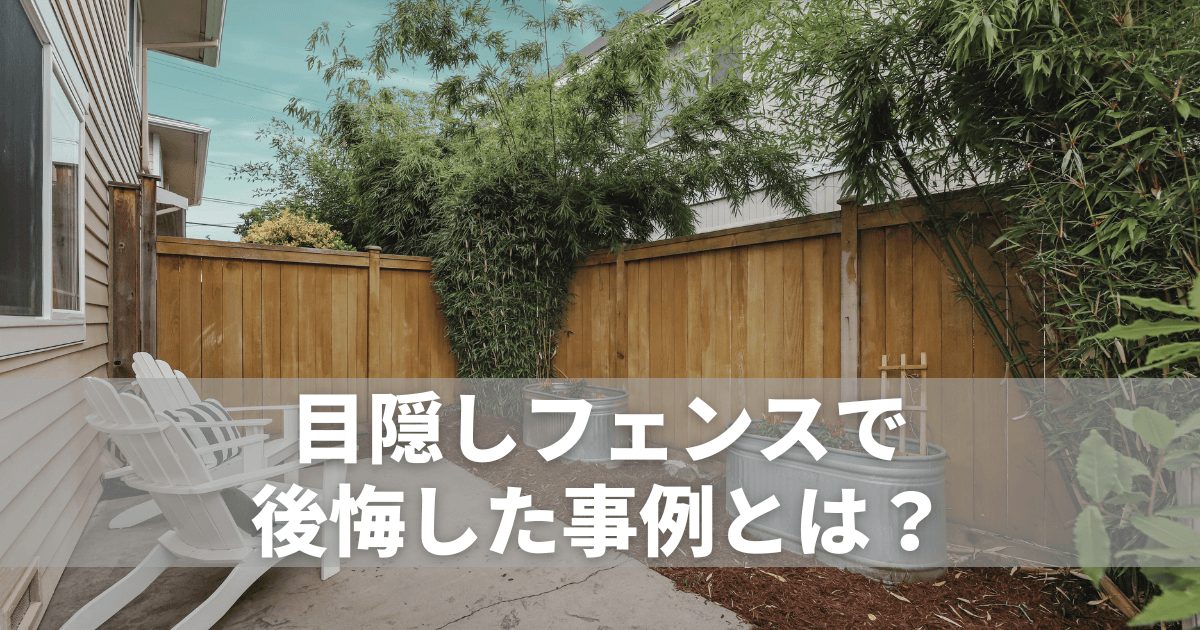
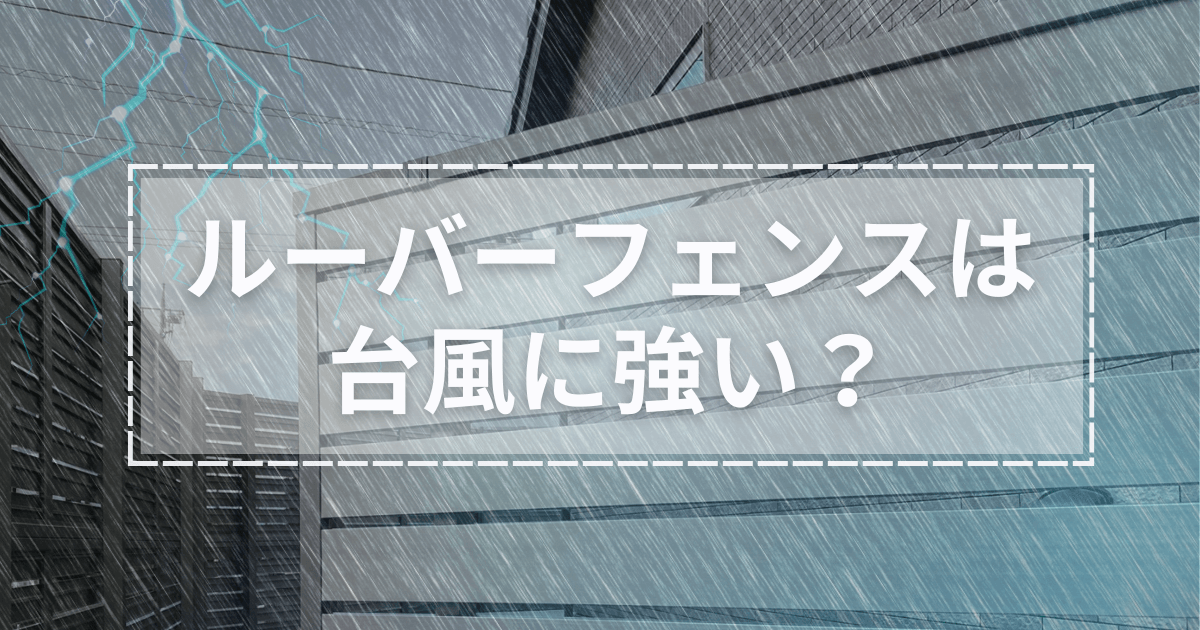
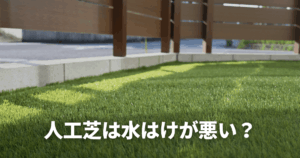
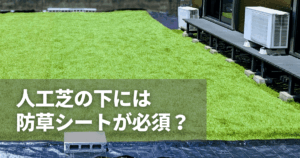
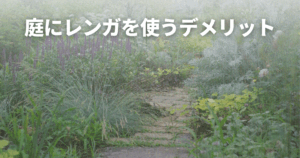
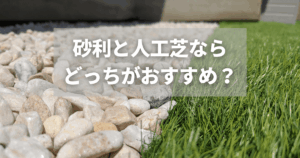
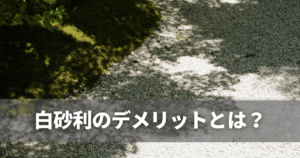
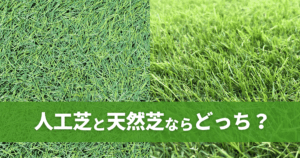
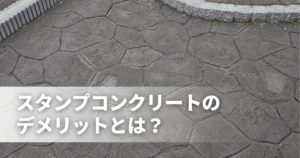
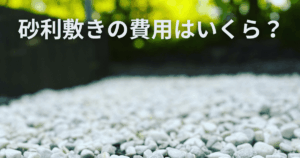

コメント