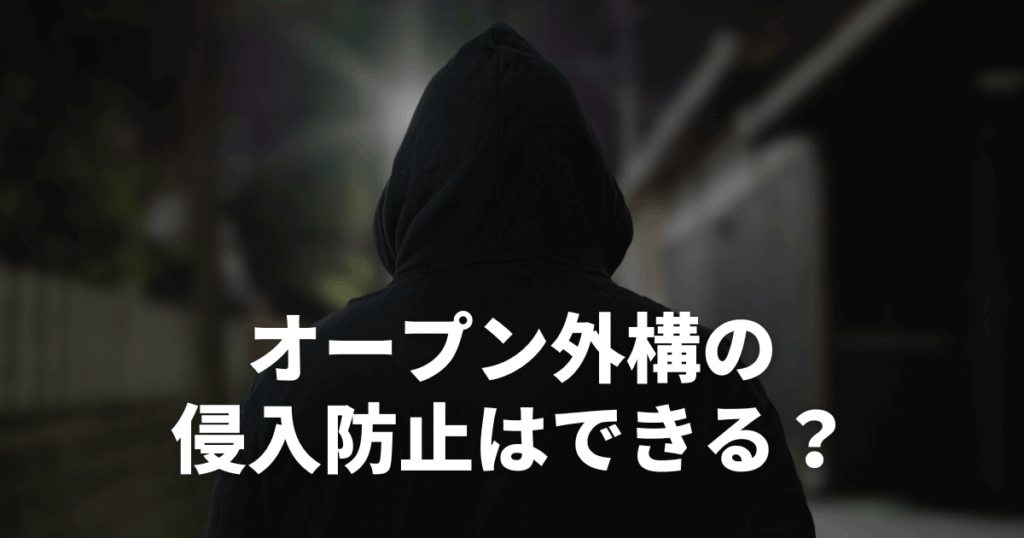
オープン外構は近年人気の外構スタイルですが、開放感がある一方で侵入リスクが高いというデメリットがあります。
塀やフェンスがないため、不審者が侵入しやすいほか、通行人がショートカットに使い、悪気なく侵入されてしまうこともあるでしょう。
この記事では、オープン外構への侵入を防ぐための対策を紹介するので、住まいに合った方法を検討してください。
オープン外構の侵入防止ができるアイデア

オープン外構への侵入対策にはどのようなものがあるのでしょうか。以下に主な対策を8個紹介します。それぞれ侵入防止の目的や効果が異なるため、適切なものを選びましょう。
防犯カメラを導入する
不審者やいたずらなど、故意の侵入を防ぐなら防犯カメラが有効です。
防犯カメラは、侵入者に対して防犯意識の高い家であることを伝える効果が期待できます。
最近では不審者を自動検出してスマートフォンに通知する機能を持つタイプもあるため、万が一被害を受けた場合でも速やかに対応が可能です。
防犯カメラは不審者をけん制する効果はありますが、威圧感があるため、近隣住民が嫌がるケースがあります。設置する際は、近所の人に説明したうえで取り付けた方がトラブルを避けられるでしょう。
植木鉢やプランターを設置する
手軽に侵入防止したいなら、植木鉢やプランターを外構に置く方法があります。
プランターはコストを抑えられ、手軽に微調節しながら適切な場所を決められる点が大きなメリットです。季節の花を植えれば、エクステリアを華やかに飾ることもできるでしょう。
一方で、境界線を示すことはできても完全には侵入を防げないこと、植物を定期的にメンテナンスする手間がかかったり、野良猫に荒らされたりする可能性があることは留意しておきましょう。
ポール・チェーンスタンドを設置する
ポール・チェーンスタンドを設置すれば、オープン外構の状態を維持しながら、必要なときはセミクローズ外構として道路と敷地を区切れます。とくに車の侵入や、近所の子どもの侵入などには高い効果を発揮する方法です。
ポール・チェーンスタンドには、置き型タイプと埋め込みタイプの主に二種類があります。
埋め込みタイプは使用しないときは地面に収納できるので、すっきりとした外観を維持できますが、コストがかかるため、使い勝手や使用頻度などを考慮して施工を検討するとよいでしょう。
センサーライトを設置する
夜間の侵入防止にはセンサーライトがおすすめです。外構の死角になる場所に設置することで、防犯性を高められます。それだけでなく、夜間に帰宅した際に手元や足元を照らしてくれるため、安心して出入りできるというメリットもあります。
センサーライトを設置する際は角度に注意が必要です。人が通るたびに点灯して隣家に光が当たってしまうと隣人が眩しく感じることもあるので、迷惑がかからない角度に調整しましょう。
ガーデンライトなどの夜間照明と上手に組み合わせて明るく見通しのよいエクステリアにすると夜間もおしゃれです。
いけず石を設置する
建物自体が、道が狭く交通量の多い道路に面している場合や、広くない角地では、車よけのためにいけず石を置く方法があります。
植栽の場合、その存在に気付かないと車に踏み潰されてしまう可能性があります。また、道が狭い場所ではフェンスを傷つけられてしまうこともあるでしょう。石が置いてあれば車の方が傷付くので、車が注意して通ってくれます。
いけず石は多くの場合自然な岩石ですが、加工されたものでも構いません。住宅に合ったデザインの石を選びましょう。
防犯用の砂利を敷く
防犯砂利を地面に敷き詰めることで、通行人の無断侵入や不審者の犯罪目的の侵入を防げます。
防犯砂利は上を歩くとジャリジャリと音が響く石です。敷いておくだけでも防犯意識の高い家と判断され、泥棒を寄せつけない効果があります。道路とは色が異なり、境界を明確にできる点や、雑草防止にも役立つ点もメリットです。
化粧砂利は防犯砂利ほどの大きな音は出ませんが、上を歩くと音が鳴るので効果的です。白や黒、グリーン、ピンク、黄色など、さまざまな色があり、住まいの雰囲気を大きく変えてくれるので、無機質な灰色の砂利に抵抗がある場合は化粧砂利を選ぶとよいでしょう。
生垣や植栽を活用する
敷地と道路の境界線に生垣や植栽を配置するのも効果的です。植栽は乗り越えようとするとガサガサとした音が出やすいので侵入防止に効果的です。
植栽を選ぶときは、適切な樹高の植物を選び、できるだけ常緑樹を植えるようにしましょう。生育が旺盛で大木になりやすい木は、こまめに剪定しなければ背が高くなりすぎて見通しが悪くなったり圧迫感が出たりします。
また、落葉樹を選ぶと、落ち葉の掃除が大変になるので、常緑樹を選んだ方が手間が少なく済みます。
境界線のデザインを工夫する
道路と敷地内の色や素材、デザインを変えて境界を明確にすることで侵入を防ぐ方法もあります。
敷地が道路と同じアスファルトやコンクリートの場合、通行人が住宅の敷地と気づかずにショートカットなどで侵入するケースがあります。
床面をタイルやレンガ、芝生などの道路とは異なる素材にすれば、不審者の侵入防止には効果が薄いですが、通行人や近隣住民に無意識に侵入されるリスクを防げるはずです。
オープン外構の基本知識と侵入リスクの実態

オープン外構はフェンスや門扉などの囲いを設けない外構スタイルで、とくに建売住宅を中心に広く採用されています。
ここでは、オープン外構の人気の理由や気をつけておきたいリスクについて解説します。
オープン外構が人気の理由
オープン外構の人気の最大の理由は、その開放感です。遮るものがなく、風通しがよく明るい庭と室内を実現できます。塀などを設置するスペースを取られる必要がないため、敷地を最大限に使える点も大きなメリットです。
それだけでなく、オープン外構は外構設備が少ない分、外構工事費用を安く抑えられます。予算が少ない場合でも、デザイン性の高い外構に仕上げられるのが、人気を高めている理由です。
犯罪の統計から見るオープン外構のリスク
一方で、オープン外構の侵入リスクには注意が必要です。
公益社団法人日本防犯設備協会の調べによると、住宅を対象とした侵入犯罪の手口は、2024年ではおよそ70%が空き巣です。一戸建て住宅への侵入手段は、無締まりが44%、ガラス破りが37.4%となっています。
不審者が侵入を諦める時間は、2分以内が17.1%、2分超5分以内が51.4%を占めており、侵入に5分以上かかると思わせるようにすることが、不審者に狙われない外構づくりの重要なポイントだということがわかります。
オープン外構はフェンスなどが存在せず、誰でも侵入できる構造です。とくに死角があると不審者に狙われるリスクが高くなる点はデメリットだといえるでしょう。
参考:住宅を対象とした侵入犯罪関連データ|公益社団法人 日本防犯設備協会
オープン外構のプライバシー対策

オープン外構で開放的な雰囲気を維持しながらプライバシー性を高めるには、以下のような方法があります。
視線が気になる場所や住まいとのバランスを考えて最適なものを採用することが、快適性向上に不可欠です。
部分的に目隠しフェンスを活用する
視線を遮りたい部分にだけ目隠しフェンスを設置すると、開放感を維持しながらプライバシーを守れます。
リビングへの目線を遮りたい、洗濯物を安心して干したい、などニーズに合わせて場所を決めるとよいでしょう。圧迫感を防ぎたいなら、縦格子フェンスのような隙間のあるフェンスと植栽を組み合わせて目隠しするのがおすすめです。
フェンスの高さは気になる目線に合わせて調節します。通行人の視線を遮りたい場合は140~200cm、車に乗っている人の視線を遮りたい場合は100~120cmが目安です。
スクリーンやパネルを設置する
部分的な目隠しには、スクリーンやパネルの設置が便利です。たとえば玄関からの出入りの際に視線が気になる、駐車場から屋内へ入るときに程よく目隠ししたい、という場合はピンポイントでスクリーンやパネルを設置することでセキュリティを高められます。
境界にフェンスを設置しなくても部分的に目隠しができるだけでなく、外構デザインにアクセントを加えることができるので、気になる場所に設置すると外観を損なわずにプライバシーを守れます。
家の間取りや導線を工夫する
オープン外構の快適性を確保しながらプライバシーを守るには、家の間取りを意識した外構レイアウトと導線の工夫が大切です。
おしゃれで快適な外構を実現するには、リビングと庭がつながったひとつの空間になるようなデザインを心がけましょう。
ただし、開放的なデザインは外からの目線が気になるので、植栽などでさりげなく目線を遮ると視覚的にも違和感なく、家族のくつろぎ空間を確保できるでしょう。
また、門から玄関へのアプローチ、駐車場から玄関への通路など、あらかじめ動線を考えて外構を設計するのもひとつのコツです。動線は直線ではなく、曲がり角やクランクを設けると、オープン外構に立体感が生まれ、限られたスペースを広く見せられるでしょう。
オープン外構の侵入防止対策を選ぶ際のポイント

オープン外構の侵入防止策は、上でもご紹介した通りさまざまな方法がありますが、どのように選ぶと後悔のない外構にできるのでしょうか。
ここでは、侵入防止策を選ぶときに押さえておきたいポイントを紹介します。
敷地の広さや形状
オープン外構への侵入対策は、敷地の広さや形状も考慮して計画することが大切です。
外構の間口が広く、侵入されやすい場合は花壇や植栽を配置して、侵入経路を限定するとよいでしょう。また、1階の道路に面した側に大きな窓がある場合は、シンボルツリーを植えることで視線を逸らせます。
隣家との境界が死角になる場合は、センサーライトを設置したり、境界付近に防犯砂利を敷くと、侵入防止に役立ちます。
周辺環境や交通量
外構プランを立てる際に、周辺の環境や交通量に配慮すると失敗を防げます。
外構デザインは、できるだけ周辺の住宅に合わせましょう。周囲と調和したデザインは統一感を生み、洗練された雰囲気に仕上がります。
また、隣接する道路の交通量、通行人の量、通学路の有無を知っておくと、駐車場の場所と車の侵入経路を決めるのに役立つでしょう。
人通りが多い場合は侵入されないよう、床材の色を変えたりプランターを置いたりして境界を明確にしておく、通学路の場合は子どもが侵入しないようにポールチェーンを設置するなど、事前に対策が可能です。
家族構成(小さなお子様やペットの有無)
オープン外構の安全対策は、家族構成を考慮することも大切です。小さなお子様やペットがいる場合、飛び出しの可能性があるため、しっかり閉められるタイプの門扉や、駐車場前にフェンスやポールチェーンを設置すると安心です。
また、ライフスタイルの変化によって家族構成が変わっていくことも考慮して、外構のレイアウトを考えておくとよいでしょう。
将来車いすを使用することを考えるなら、床面をできるだけフラットにしておき、門の間口も広めにしておくと安心です。
予算やメンテナンスの手間
オープン外構の侵入防止対策のプランを練るときは、予算を事前に決めておき、後々必要となるメンテナンスについても考えておきましょう。
限られた予算のなかで満足度の高い外構を完成させるには、優先順位を決めておくとスムーズです。
もし、予算オーバーになったら諦めず、外構工事業者に相談すると理想に近い代替案を提示してくれることもあるので、業者に理想を伝えておくのがおすすめです。
また、外構は経年により劣化するので、定期的なメンテナンスが欠かせません。メンテナンスの時期をあらかじめ予定しておき、リフォーム費用も準備しておくと、急な破損で慌てずに済みます。耐久性が高くメンテナンスの手間がかからない素材を選ぶことも大切です。
侵入防止対策ならセミクローズ外構もおすすめ

敷地への侵入防止対策や子どもの飛び出し対策には、セミクローズ外構が向いています。
クローズ外構に比べて設計がしやすくリフォーム費用も抑えられるので、オープン外構にストレスを感じている場合は検討してみるとよいでしょう。
セミクローズ外構のメリット
セミクローズ外構の最大のメリットはデザイン面と機能性のバランスがとれた設計を実現できる点です。外からの視線を遮りながら、住まい全体のイメージを洗練された雰囲気に演出することが可能です。
土地全体をフェンスや塀で囲うクローズ外構に比べて風通しがよく、日当たりを確保でき、自然な快適性を得られます。
オープン外構に比べて動線を限定できるので、防犯対策を講じやすい点も大きなメリットです。
注意点と設計時の工夫とは
セミクローズ外構を設計するときは、フェンスや門柱で遮る場所と開放する場所のバランスをとることが大切です。
外構設備で周囲を囲いすぎると、閉鎖的な雰囲気になるほか、外構が狭くなったような印象になります。
駐車場はオープンにし、玄関周りは安全性を高めるためにクローズにするなど、家族の外構の使い方をシミュレーションして、オープンにしたい部分とクローズにしたい部分を具体的に決めておくと失敗を防げます。
まとめ

オープン外構は開放感があり、狭い敷地でも広々と使える外構スタイルです。しかしその一方で、十分な侵入防止対策をしなければなりません。
複数のアイテムを組み合わせる、セミクローズ外構を検討するなどすれば、安全性の高い外構を完成させることが可能です。
オープン外構を検討している場合は、外構工事業者に理想のデザインだけでなく、不安な点や防犯面についてアドバイスをもらいながら計画していくと、理想のエクステリアに近づけるはずです。
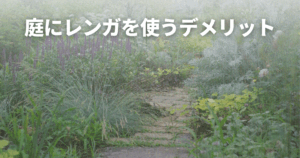
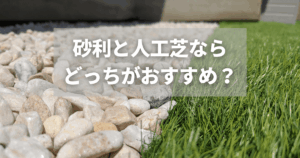
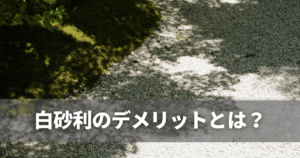
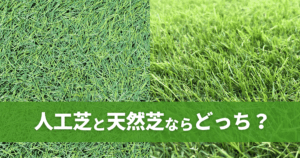
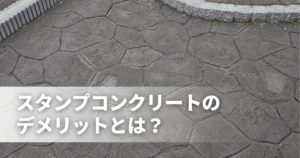
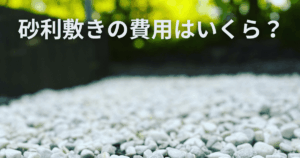
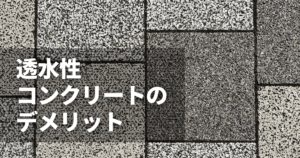


コメント