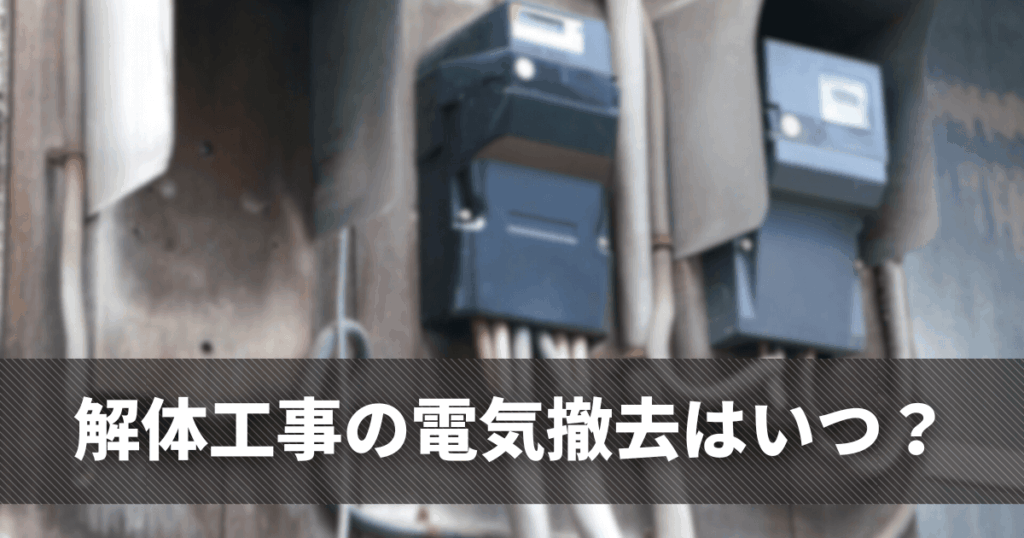
解体工事では、作業が始まる前までにライフラインを停止する必要があります。とくに電気は、知らずに電気が通っている電線を損傷させて大事故につながる、という事態も起こりかねません。
この記事では、解体工事の電気撤去について解説するので、解体工事を行う前にしっかりチェックしておきましょう。
解体工事における「電気停止・撤去」の基本知識

ここでは、解体工事をする際に電気の停止・撤去が必要な理由や撤去しなければならない設備などについて解説します。基本的な知識を押さえておき、安全な解体工事をするために役立ててください。
電気停止が必要な理由
電気が通ったまま解体作業を行うと、作業員が誤って電線に触れて感電してしまうおそれがあります。実際に電気が通った状態の電線を切断したことで死亡事故につながった事例も少なくありません。
また、解体作業中に活線状態の電気配線を損傷させたことによりショートし、火災事故が起こったというケースもあります。
電気は目に見えず、においもないため、非常に危険です。安全に作業するために、電気設備を撤去し、確実に電気が止まった状態で作業する必要があります。
対象となる設備
解体工事で電気を停止する場合は、電気の供給を止めるだけでなく、電気設備の撤去も必要です。対象となる電気設備は、引込線、電気メーター、アンペアブレーカーです。
これらが設置されたまま解体工事を行うと、感電事故につながる危険性があります。また、電線がついたまま作業すると、重機のアームが電線を巻き込んでしまうなど、大きな事故につながりかねません。
そのため、安全性を確保するために、確実に撤去してから解体工事を開始します。
電気設備の現状確認
電気設備の撤去作業中や解体工事中の事故を防ぐためには、電気配線がどこを通っているのかを事前に確認しておくことが大切です。活線状態の電気配線が残っている状態で解体工事を始めてしまった場合、大事故が発生するリスクがあります。
そのため電気事業者は、撤去工事の際にどこから電気が引き込まれているのか、使用中の配線や古い回路が残っていないか、使用していないはずの場所に通電している箇所はないか確認します。
電気の撤去をする際の手順

解体工事のために電気の引込線を撤去する場合の手順は以下の通りです。確実に電気を停止・撤去できるように、また業者と行き違いがないように、事前に流れを押さえておきましょう。
電力会社に連絡
解体工事の日時が決まったら、まず電力会社に電気停止の申し込みをします。電力会社に電話をかけるか、公式サイト内からWeb受付で申し込みます。
申し込みの連絡をする際には以下の項目が必要です。
- 契約者の氏名
- 住所
- 供給地点特定番号または電気メーター番号
- 撤去希望日と解体工事日
これらの情報をあらかじめメモしておくとスムーズです。
供給地点特定番号は、電気の契約場所を特定するために全国一律でつけられる22桁の番号で「電気ご使用量のお知らせ」に記載されています。電気メーター番号は、電気メーター正面部の「No.」から始まる番号です。
電力の使用停止手続き
電力会社に必要事項を連絡すると、使用停止手続きをしてもらえます。手続きの際は「解体工事を行う旨」を必ず伝えるようにしましょう。電気停止のみを伝えると、電力の供給のみを停止することになり、電柱からの引き込み線や電気設備の撤去はしてもらえません。
一般住宅への電気設備の撤去は遅くとも解体工事予定日の1週間前までに申し込む必要があります。工事が混み合っていると直前では対応できないケースもあるので、解体工事のスケジュールが決定したらすぐに申し込むようにしましょう。
電気設備の撤去
工事当日は電気設備と引込線の撤去を行います。これらの撤去作業は、電力会社が行います。
ここで撤去する電気設備は、電気メーターとアンペアブレーカーです。電気メーターは各住戸の電気の使用料を計るための装置で、多くの場合、屋外に取り付けられています。電気メーターは電力会社の所有物なので、電気停止の工事の際は、電力会社が引き取ります。
アンペアブレーカーは、契約アンペアを超えて電気を使用した場合にブレーカーを落として電気を遮断するブレーカーです。こちらも電力会社の所有物なので、電力会社が回収します。アンペアブレーカーの撤去は宅内作業となり、立ち合いが必要になる場合があります。
電気配線の撤去
電気設備の撤去と共に行うのが、引込線の取り外しです。
引込線とは、電柱から住宅に電気を引き込むための電線です。電柱から建物の軒先に取り付けられている引込線取付点までが該当し、その先は引込口配線を経て屋内配線となります。
電柱から引込線取付点までが電力会社の所有物となり、その先は契約者の所有物です。
引込線を撤去しなければ解体業者の重機が現場に近づけないため、建物につながっているすべての引込線を取り外します。
各電力会社への連絡方法

解体工事の際の電気の停止手続きは、契約中の電力会社に申し込みます。基本的に請求書に記載されている連絡先に問い合わせしますが、以下に主な電力会社の手続きページのURLを掲載するので、早めに手続き方法を確認しておいてください。
東北電力
解体工事による契約廃止、引込線・メーターの取外しは東北電力の下記ページから「ご契約のお申込み」ページに移動し、記載されている電話番号に電話するか、「東北電力のWeb手続きはこちら!」というバナーをクリックしてWeb申込みします。
参考:契約の廃止(家屋を解体する場合) – よくあるお問い合わせ|東北電力
東京電力
東京電力の停止はTEPCO公式サイトの下記のページに記載の電話番号に電話するほかに「カスタマーセンター」のリンクをクリックして、チャットで申し込むことも可能です。
参考:建物(家屋)を解体するので電気設備を撤去したい | 東京電力エナジーパートナー
中部電力
中部電力ミライズ公式サイトの各種手続きのページで「使用停止のお手続き」の該当する項目をクリックし、会員でない場合は「会員登録せずに申し込む」をクリックすると、申し込みページに進みます。
申し込みページのなかに「家屋の取り壊しはありますか?」という項目があるので「あり」にチェックを入れてください。
関西電力
関西電力の停止は、関西電力送配電公式サイトの下記のページにある「お問い合わせはこちら」のバナーをクリックし、チャット、メール、電話のいずれかで申し込みできます。
解体工事で電気の撤去をする際の注意点

解体工事に伴って電気設備を撤去する際は、いくつかの注意点があります。解体工事を予定している場合は、以下で紹介する注意点を押さえて、スムーズに準備を進めましょう。
余裕あるスケジュールで準備
電力会社への電気停止は、十分余裕を持って申し込むことが大切です。電力会社によって幅があるものの、基本的に連絡は希望日の2週間前までに行っておきます。
しかし、春の引越しシーズンなど、電気停止手続きが増える時期は希望通りに撤去工事ができない可能性もあるので、余裕をもって連絡を入れるようにしましょう。
とくに、解体工事後に土地の売却や住宅の建て替えなどを控えている場合、スケジュールが遅れないよう、早めに連絡することが大切です。
解体工事を行うことを電力会社へ通知
上でも解説しましたが、電力停止の申し込みの際は解体工事のために電力を停止したい旨を忘れずに伝えましょう。
電気の解約、停止を行うのは一般的に以下の3つのパターンがあります。
- 引っ越し
- 解約・停止
- 解体工事に伴う電気設備撤去
引越しや、電気設備をそのままにして解約・停止する場合は、電力会社に連絡すれば指定日に停止してもらえます。この場合、とくに撤去する電気設備もなく、基本的に立ち合いの必要はありません。
解体工事のために電気を停止する場合は、電気設備を撤去し、完全に電気を遮断する必要があります。そのほかの停止手続きとは異なるため十分注意しましょう。
電気以外のライフラインも撤去が必要
解体工事では、電気以外のライフラインの撤去も必要です。ガスは電気と同様、供給されたままの状態で解体工事を行うと、ガス管を損傷させて爆発などの大事故を引き起こす恐れがあるので、解体作業が始まる前までに必ず撤去しなければなりません。
そのほか、電話線、インターネット回線、テレビアンテナも工事前に解約・撤去の手続きが必要です。浄化槽がある場合、清掃業者に汲み取りを依頼する必要があります。
注意しておきたいのは水道です。水道は解体工事中に使用するため、停止しません。工事で使用した分の水道料金を施主が負担する場合、そのままでも問題ありませんが、業者が負担する場合は事前に水道局に連絡して清算手続きが必要です。
解体工事中の電気をどう確保する?

解体作業では工具や照明などの使用に電気が必要です。電気設備を撤去したあとの敷地内では、解体業者は仮設電源を使用することになります。ここでは、解体工事中の仮設電源について解説します。
なぜ仮設電源が必要なのか?
解体工事では作業を効率化するため、電動工具や照明設備などを使用します。電気を停止している解体現場では、何らかの方法で電気を確保しなければなりません。
小規模な工事現場では発電機を使用することもありますが、解体現場で必要となる電力を安定的に供給するには、発電機では限界があります。そこで、電力会社から直接電気を引き込める仮設電源を設置することで、電気を安定して使用することができ、作業の効率化につなげられます。
解体業者が仮設電気を設置する
仮設電気の手配は施主が行う必要はなく、解体業者が電気工事業者に手配します。仮設電気工事の作業は電気工事士の資格が必要なため、作業を行うのは電気工事士です。
設置の際は、設計に基づいて配電盤と電線を設置し、必要な場所にコンセントや照明を配置します。解体工事中は、施工の進捗に応じて設備の移動や増設も必要です。解体工事が完了し、電源が必要なくなったら仮設設備を撤去します。
費用は誰が負担する?
仮設電源の電気代は、施主が負担するのが一般的です。多くの場合、電気費用は「共通仮設費」として解体工事費用に含まれています。
ただ、業者によっては見積もり費用を安く見せるために見積書に仮設電源の費用を記載していないケースもあり、追加費用を請求されるため注意が必要です。
見積もりの際は、仮設電気の使用料金について見積書に記載されているか忘れずにチェックしましょう。記載されていない場合や、どこに記載されているのかわからない場合は、契約する前に業者に質問しておいてください。
解体工事の撤去に関するよくある質問

ここでは解体工事の電気設備撤去に関してよくある質問とその解答を紹介します。解体工事をスケジュールどおりに進めるためにも、疑問を解消してしっかりと準備を進めましょう。
電気の引き込み線を撤去するにはいくらかかりますか?
電気の引き込み線の撤去費用は基本的に無料です。ただし、地域や電力会社によっては費用がかかる可能性もあるので、事前に確認しておきましょう。また、電気の解約に関しても、電力会社の契約内容や料金プランによっては解約金が発生するケースもあるので、事前に確認が必要です。
解体工事後に新しく住宅を建てる予定がある場合は、新たに電気設備を設置しますが、新設工事には費用がかかる場合があります。建て替えを検討している場合は、電気設備の新設費用についても電力会社に問い合わせておきましょう。
解体工事で残していいものは何ですか?
解体工事では基本的にすべてのライフラインを停止しますが、水道は停止も撤去もしません。水道は解体工事中の粉塵の飛散を防ぐために使用するため、そのままにしておきます。
また、解体工事では境界杭も撤去しません。境界杭がなくなってしまうと、隣家との境界線が曖昧になり、トラブルの原因になってしまいます。万が一解体工事後に境界杭がずれていたり破損していることが発覚したら、速やかに解体業者に問い合わせ、対応してもらいましょう。
まとめ

解体工事では、電気を停止し、電気設備を撤去して安全に作業を開始できるようにしなければなりません。ライフラインの停止は施主が行う必要があるため、早めに電力会社に申し込むようにしましょう。
いつ、どの手続きをするかわからない場合は、解体業者の営業担当者に相談して、サポートを受けながら手続きしていくと安心です。









コメント