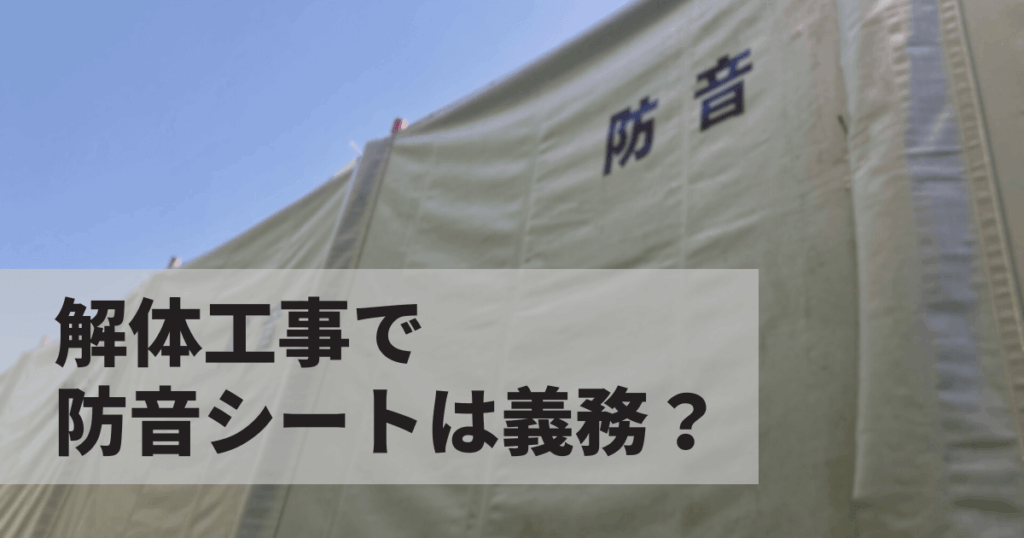
解体工事では騒音や振動、粉塵の発生はつきものです。とくに騒音は近隣住民にとってストレスになりやすいため、できるだけ配慮しておきたいという方も少なくないでしょう。
解体工事で発生する音の拡散を防ぐものに防音シートがありますが、必ず設置しなければならないのでしょうか。今回は、防音シートについてのルールや設置しない場合の注意点などについて解説します。
防音シートは解体工事で義務なのか?

解体工事現場では防音シートの使用は、法律で義務付けられているのでしょうか。ここでは、防音シートや養生シートの設置に関する法律上のルールや重要性について解説します。
防音シートは法律で義務付けられていない
解体工事で防音シートの設置は義務ではありません。たとえば粉塵対策のために散水を行っていた場合、シートを設置していないとが違法行為に問われるかといえばそうではありません。
また、解体現場の家屋から近隣住宅まで距離が離れている場合、防音シートは設置しなくても問題ない場合があります。
ただし、国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」には「防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける」「養生シート等は、隙間なく取り付ける」と基準が示されており、防音シートまたは養生シートの設置が望ましいことが分かります。
「特定建設作業」では防音対策の実施義務が生じる
特定建設作業のように大きな音や振動が出る工事では、騒音や振動に関する規制基準を守らなければなりません。
騒音基準法では特定建設作業を行う場合、騒音が作業現場の敷地の境界線において85dBを超えてはならない、と定められています。
参考:騒音規制法 第十五条
作業により85dB以上の音が出る場合は、現場内の壁面に防音シートを張ったり、騒音を発生させる建設機械の周辺を吸音材で囲ったりして対策しなければなりません。
騒音規制法で定められた騒音の大きさや作業時間などの制限に違反し、かつ改善命令に従わなければ5万円以下の罰金の対象となるため、防音シートでの対策は重要です。
参考:騒音規制法 第三十条
自治体条例で防音シート設置を指導されるケースも
防音シートの設置は法律で義務付けられたものではありませんが、自治体の条例や近隣住民への配慮のために事実上義務化されている場合があります。
騒音規制法や振動規制法は基本的なものとなっており、より細かいルールは各自治体が条例という形で規制しています。
大きな騒音を出す作業を行う場合には条例により届出を義務付けていたり、防音シートなどによる騒音対策を求めていたりするのが一般的です。自治体によってルールが異なるため、解体業者は自治体の規定に従って施工を行っています。
法的義務がなくても「契約上の義務」になることが多い
防音シートや養生シートの設置には法的な縛りはありませんが、契約上の義務やトラブル防止のために設置する業者も多くいます。
防音シートは騒音や粉じんの飛散を防止するだけでなく、がれきや工具の落下防止にも役立つものです。足場の上から廃材や工具を落下させて、通行人をケガさせたり隣家の塀や外壁を傷つけてしまうリスクを最小限に抑える効果が期待できます。
周辺住民が被害を訴えれば、損害賠償請求に発展するおそれもあります。そのため、安全の確保と近隣住民へ配慮するために設置するのが一般的です。
防音シートを設置しないとどうなる?

防音シートは法律で義務化されていませんが、設置しないとどのようなデメリットがあるのでしょうか。ここでは、防音シートを設置しないことで起こりうるリスクを紹介します。
近隣からの騒音・粉じん苦情が発生しやすい
防音シートは近隣へ騒音や粉じんを拡散させない効果があります。したがって、防音シートを設置しないと、騒音や粉じんが近隣へ広がりやすく、苦情が発生するリスクが高まるでしょう。
騒音は近隣住民に大きなストレスを与え、苦情の大きな原因になります。粉じんは洗濯物を汚すだけでなく、くしゃみや鼻水などの症状や呼吸器系の疾患を引き起こすおそれがあるため、防音シートや養生シートを使って十分な対策が必要です。
行政から改善勧告・作業停止命令を受ける可能性
防音シートを設置しないことで法律で定められた規定を上回る騒音を出したり、近隣住民の健康に影響を与える量の粉じんを発生させたりした場合は、行政から罰則を受ける可能性があります。
解体現場から常時85dB以上の音が発生し続ける場合、解体業者は工事内容の改善をしなければなりません。また、騒音の大きい工事は1日連続10時間以上の作業や日曜日・祝日の作業は禁止されています。
基準を超えた騒音により周辺住民の生活や健康に被害を及ぼしていると認められると、市町村長は業者に対して改善勧告を行います。
施主・発注者との信頼関係を損なう
防音シートを設置せずに解体工事を行って近隣住民に被害を及ぼした場合、施主と解体業者の信頼関係が崩れる可能性があります。
多くの場合、解体工事に対する近隣住民からの苦情は施主に入ります。もし、苦情に対して適切に対応しなかったり、対策に時間がかかったりすると、施主と近隣住民との関係性が悪化しかねません。その場合、解体工事業者への信頼は損なわれるでしょう。
さらに、行政から何らかの指導や処分を受けたとなると、施主は解体業者が本当に解体工事を適切に実施したのか、廃棄物は適切に処分したのか、不信感を募らせかねません。
このようなことがないように、多くの解体工事業者では、防音シートや養生シート、散水などを行って適切に騒音・粉じん対策を行います。
防音シートの役割と効果を理解しておこう

防音シートは騒音の拡散を防ぐだけでなく、安全のためにさまざまな役割を担っています。
以下に防音シートの目的や種類、性能、設置方法について整理したので、施主としても基本知識を知っておきましょう。
防音シートの主な目的
防音シートは、厚さ0.5〜1mmの銀色または黒色のシートで、騒音を吸収・遮断し、騒音の拡散を抑える目的で使用します。特殊な素材や構造で振動や音波を吸収できるため、周囲に解体工事の騒音が広がることを防ぎます。
騒音を遮断する機能も持ち合わせているため、現場からの騒音の漏れ防止に効果的です。具体的には、防音シートの設置により、解体工事の騒音を10〜20dBほどカットできるとされています。
防音シートの種類と性能
防音シートの性能は大きく吸音タイプと遮音タイプの2種類に分けられます。吸音タイプは音を内部で吸収して拡散することで、音を漏らさないようにする構造です。
遮音シートは音を反射して外部に通さないようにする構造を持っています。吸音機能と遮音機能を併せ持った防音シートも存在し、現場で広く活用されています。
また、マンションやビルなどの大規模な解体工事では戸建て住宅よりも大きな騒音が発生するため、防音パネルが使用されるのが一般的です。
施工現場での設置方法
防音シートはシートの穴(ハトメ)に紐を通して、足場のパイプに結びつけます。シートの防音効果、防塵効果を高めるために、隙間なくたるみなく張ることが大切です。
また、足場の寸法に合った防音シートを使用しなければならず、基本的に1つの現場では全て同一メーカー、同一サイズのシートを使用します。
防音シートは大雨や強風などの悪天候のあとには点検を実施し、シート地やハトメ部分が破損しているものは交換する必要があります。
防音シートの設置を求められるケース

防音シートはとくに静寂が求められる場所での設置が推奨されています。ここでは、防音シートによる防音対策が必要な場所を紹介します。
条件に当てはまっている場合は防音シートが必要である旨、解体業者に伝えておくと安心です。
周辺が住宅密集地の場合
住宅密集地では近隣の建物との距離が近く騒音の影響が大きいため、防音シートを設置して騒音対策をする必要があります。
住宅地は環境省の基準によれば昼間55dB以下、夜間45dB以下が望ましいとされ、それ以上は騒音になってしまいます。
そのため、早朝・深夜の作業は避けるなどの作業時間への配慮、工事車両は徐行で通行する、週に1日の休日を遵守、そして近隣住民への事前の説明が重要です。苦情があった場合には防音シートを追加・変更するなど、速やかに対策しなければなりません。
学校・病院・公共施設が近い場合
学校や病院など、静穏が求められる場所でも、工事の騒音を抑えるため防音シートの設置が不可欠です。
学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホームなどの敷地の周辺はとくに静穏保持が規定されており、建設工事の際に騒音に対して基準値が通常よりも厳しく設定されていることがあります。
時間帯ごとの騒音基準について厳しく条例で定めている自治体も多くあり、防音シートの設置だけでなく、作業時間帯にも配慮しなければなりません。
RC造・鉄骨造など大型構造物の解体
RC造や鉄骨造の建物の解体では重機の使用により、90~110dBという、木造住宅の解体よりも大きな騒音が発生します。そのため、防音シートの設置と同時に工法を工夫する必要があります。
RC造の解体では、油圧ショベルの先端アタッチメントを付け替えて「圧砕工法」または「ブレーカー(破砕)工法」で行うのが主流です。ブレーカー工法は強力な打撃力でコンクリートを破砕しますが大きな騒音と振動が避けられません。
そのため、コンクリートを挟んで砕く圧砕工法を主に使用しながら、どうしても必要な場所だけ短時間に限ってブレーカー工法を使用する、など配慮が必要です。
防音シート設置のコストと業者選びのポイント

ここでは、防音シートの設置にかかるコストと、優良業者を選定するためのポイントを紹介します。
信頼できる業者に依頼すれば適正な費用でご近所トラブルを最小限に抑えた工事ができるので、ぜひ業者選びの参考にしてください。
防音シートの設置費用の目安
防音シートの設置費用の相場は1㎡あたり、約2,000〜5,000円です。一方、通常の養生シートの設置費用は1㎡あたり1,500〜2,000円が目安です。
解体工事では基本的に養生シートが採用され、防音シートはオプションになることが多くあります。防音シートは養生シートに比べて単価が高くなりますが、騒音トラブルを防ぎたい場合に効果的です。
しかし、不必要な場所に設置しても費用が高くなるだけです。そのため、解体工事業者と相談して現場の状況に合わせて最適なものを選びましょう。
見積書で確認すべき項目
解体工事業者から見積書を提示されたら、まずは工事の明細と費用が細かく記載されているかチェックしましょう。「工事一式」などと1行で記載されている業者は何にいくらかかっているのか分からず、追加費用でトラブルが発生するおそれがあるので避けた方が無難です。
解体工事の見積書の品目には以下のように、作業ごとの項目に分けて記載されます。
- 内装解体工事費
- 躯体解体工事費
- 基礎解体工事費
- 養生費
- 付帯工事・門扉撤去工事費
- 付帯工事・植栽撤去工事費
- 重機回送費
- 一般諸経費
解体工事の防音シートの費用は「養生費」「足場養生一式費」などと記載されます。業者によっては「解体工事費」に養生シートの費用が含まれているケースもあるので、聞いてみるとよいでしょう。
信頼できる業者の見分け方
信頼性の高い解体工事業者に依頼するためには、業者のウェブサイトをチェックしたうえで複数の業者から相見積もりをとることが大切です。
まず、気になる業者のウェブサイトで、会社概要に必要事項がきちんと記載されているか、必要な許認可を取得しているか、保険に加入しているかを確認します。つぎに施工実績のページで実績が豊富か、どのような工事を多く手がけているのかをチェックしましょう。
そして、3社程度から相見積もりをとり、見積書の内容、営業担当者とはコミュニケーションが取りやすいか、説明は適切かなどを総合的に見て、1社に決めます。
まとめ

解体工事では騒音トラブルを防ぐために防音シートを設置すると安心です。ただし、必要性が低いのに高額なシートを設置すると依頼主にとって負担になるだけなので、解体工事業者の営業担当者とよく相談して適切なシートを設置することをおすすめします。
また、解体工事中でも、近隣からクレームがあった場合や騒音が気になる場合は、業者に防音シートを追加してもらうなど、臨機応変に対応するとよいでしょう。





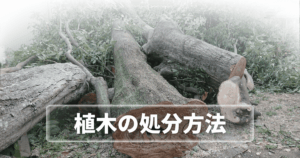
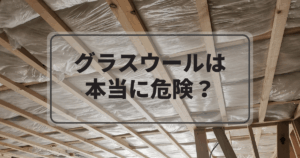
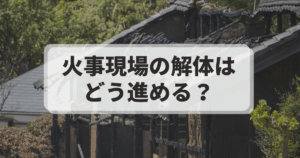

コメント