
解体工事で車両を道路に駐車して作業する際には、通行人やほかの車への安全確保のために道路使用許可が必要です。
取得しないまま作業をしてしまうと罰則の対象となることもあるため、制度についてよく理解し、正しく申請する必要があります。
今回は、解体工事の道路使用許可について、必要性や法律、注意点などについて解説します。
解体工事で道路使用許可が必要なケース

解体工事で道路使用許可を取得しなければならないのは、どのようなケースなのでしょうか。以下に許可が必要な事例を挙げるので、法令に則った工事を依頼するための参考にしてください。
重機や資材の搬入・搬出
解体現場に重機を搬入・搬出する際、工事車両を道路に駐車して行うケースがあります。この場合、道路の一部を一時的に占有し、ほかの車や通行人の交通に影響を及ぼす可能性があるため、道路使用許可が必要です。
解体工事では重機を使って作業を行うのが基本です。重機は公道を走行できるものもあれば、自走できないものもあり、その場合はトレーラーやトラックの荷台に乗せて運搬します。このとき、現場の前に車両を駐車して重機を降ろす必要があります。
そのほか、解体工事では道路にクレーンなどの重機を固定して作業することも少なくありません。この場合も道路使用許可が必要となります。
歩行者の安全確保
道路上への工事車両の駐車により歩行者の通行を妨げる可能性がある場合は、歩行者の安全を確保するため、道路使用許可を取得しなければなりません。
道路使用許可を取得して道路を使用する際には、歩行者の安全に配慮した通路を確保します。歩行者通路の幅員は1.5m以上確保するのが原則です。交通量が少なく作業内容からやむを得ない場合は、幅員0.75m以上で認められることもあります。
また、歩行者通路には土砂や工具、器具などを置かず、常に整理整頓しておかなければなりません。
仮囲いや足場の設置作業
解体工事では仮設足場を設置または撤去するため、足場資材をトラックで搬入・搬出します。足場資材の揚げ降ろしの際に道路にトラックを駐車する場合は、道路使用許可が必要です。
また、土地の形状や土地と建物の位置関係によっては足場の一部が道路にはみ出す場合があります。その場合は歩行者の安全を確保するために道路使用許可と道路占用許可を取得する必要があります。養生シートや仮囲いが道路にはみ出している場合も同様です。
工事車両の駐車
道路に工事車両を駐車する際は、ほかの車や歩行者の交通の妨げとなるため、基本的に道路使用許可が必要です。道路に車両を固定して作業する、資材の搬入・搬出、道路に資材や機材を置くなど、道路をふさぐ場合は許可を取得しなければなりません。
解体工事は基本的に敷地内に車両を停車しますが、敷地の形状や周辺の条件などにより敷地の外に車両を停車しなければならない場合があります。このような場合には道路使用許可が必要です。
交通規制の実施
解体作業中に一時的に通行止めや片側交互通行を実施する場合、道路使用許可が必要です。交通規制できる時間は午前6時30分から午後7時30分までと決められています。
また、道路使用許可を取得する際、多くの自治体でガードマンの配置を求められます。道路を一時的に占有する場合は歩行者や車両を安全かつ円滑に誘導するための措置を取らなければなりません。
ガードマンを配置するかどうかは、工事の場所や規模、内容によって異なります。たとえば交通量の多い場所や通学路での工事は、歩行者の安全を考慮してガードマンの設置が推奨されます。
許可不要な誤認されやすい状況
道路使用許可は、短時間でも本来の道路の目的である「通行」以外の使い方をする場合は必要です。そのため、短時間でもトラックを車道や歩道に一時停止させ、荷物の積み下ろしをする場合には道路使用許可を取得します。
一方で、決められた場所でルールを守って駐車する場合は許可は必要ありません。
そのほか、個人が歩道などでスマートフォンなどを使って記念撮影する程度であれば、交通の妨げにならない限り許可は不要です。ただし、三脚や照明などの機材を使って撮影する場合は許可が必要となります。
そもそも道路使用許可とは

道路では交通の妨げになる行為は禁止されていますが、道路の使用が社会的な価値を有する場合は、道路使用許可を取得することにより、一時的に使用できます。ここでは道路使用許可の基礎知識を解説します。
道路使用許可の種類
道路使用許可は、道路の使用方法により4種類に分けられます。
1号許可
道路で工事または作業をする際に必要です。
- 道路工事
- 解体工事
- 搬出入作業
- マンホール作業
- ゴンドラ作業
2号許可
道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する際に取得します。
- 仮設足場の設置
- 公衆電話ボックス等の設置
- 消火栓の設置
- アーケードの設置
- 立看板、掲示板の設置
3号許可
場所を移動しないで道路に露店、屋台等を出そうとする際に必要です。
- 露店
- 屋台、キッチンカー
- 飲食店の屋外テラス席
4号許可
道路で祭礼行事、ロケーション等を行う際に取得します。
- 祭礼行事
- 撮影
- 寄付金活動
- ビラ配り
- マラソン大会
道路使用許可の許可基準
道路使用許可の許可基準は道路交通法第77条で定められています。
- 申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 申請に係る行為が許可に付された条件に従って行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
上記のいずれかに該当する場合は道路使用許可を取得できます。家屋の解体工事の場合、上記の3の基準が該当します。
道路使用許可の申請手続きとスケジュール

ここでは、道路使用許可の申請手続き方法や押さえておきたいポイントについて解説します。
建物解体工事の場合は、依頼した解体工事業者や建設会社が手続きを代行してくれることがほとんどですが、施主としても流れを知っておくと安心です。
申請先
許可申請は、使用する道路を管轄する警察署の警察署長に対して行います。届出先は、使用する道路を管轄する警察の受付窓口、またはWeb上の警察行政手続サイトです。
2つ以上の管轄にわたる道路使用については、主に道路を使用するエリアを管轄している警察署に申請します。道路占用許可も併せて申請する場合は、道路管理者へ占用許可を申請します。道路管理者は、国道は国交省の国道事務所、県道・市道は各地域を管轄する土木事務所です。
申請するのは原則として道路を使用する者です。解体工事であれば工事関係者、自分自身で引っ越し作業などをする場合は個人で行います。
参考:警察行政手続サイト
必要書類一覧とポイント
道路使用許可の申請に必要な書類は以下の通りです。申請書と添付書類をそれぞれ2通作成して提出します。
- 道路使用許可申請書
- 位置図
- 現況道路及び周辺見取図
- 工程表
- 保安図(断面図含む)
- 交通量調査結果
- 迂回路略図(看板等の位置・内容を含む)
- 広報対策資料
道路使用許可申請書は、各警察署で申請用紙をもらうか、ホームページからダウンロードできます。必要書類は許可の種類によって変わります。
申請から許可取得までの流れ
申請の流れは以下の通りです。
道路使用許可申請をする場合は事前に警察署で相談することをおすすめします。道路によっては使用方法や作業時間に制限が設けられていることがあるため、問題がないか確認しておいた方がよいでしょう。
使用する道路の測量を行い、車道、歩道の幅員、道路の使用範囲を測定します。
道路使用許可申請書に必要事項を記載し、書類を準備します。
道路使用許可申請書と添付資料を各2部ずつ、申請手数料の額面の収入印紙を添えて提出します。
審査に通ると道路使用許可証が発行されます。審査期間は1週間が目安ですが、警察署によって違うので事前に問い合わせておくとよいでしょう。
事前協議をしておくべきケース
道路使用許可の取り扱いに相違が起こらないように、事前に警察署と協議するケースがあります。
以下のような場合には事前協議をしておいた方がよいでしょう。
- 初めて道路使用許可申請をする場合
- 工事日程や作業内容において必要な日数分の許可が下りるか不明な場合
事前協議の目的はどのような理由でどれくらいの範囲、道路を使用する予定なのかを伝え、使用許可を出してもらうことです。許可が下りるか不明な場合は事前協議を行い、1回の申請で許可が下りるようにします。
申請手続きにかかる費用目安
申請費用は解体工事が該当する1号許可の場合、2,500円前後です。都道府県によって費用が異なるため、詳しい金額は各都道府県警察に問い合わせてください。
費用は申請する警察署が所在する県の収入印紙で支払います。多くの場合、警察署で収入印紙が発売されているので、申請時に購入が可能です。
解体業者に許可申請をしてもらう場合、手続きに関する手数料がかかることがあります。費用は業者によって異なるため、見積もりの際に確認しておくとよいでしょう。
また、申請手数料に補助金・助成金制度はありませんが、公共性の高い活動や天災地変等に伴う緊急復旧作業などは手数料が免除されることがあります。詳しくは管轄の警察署で確認してください。
申請後・工事中の現場で気をつけるべきポイント

道路許可申請を取得し、工事を開始してからも施工会社の作業スタッフはさまざまな点に注意して作業を行わなければなりません。
ここでは、道路を使用して作業を行う際の注意点やリスクについて解説します。
近隣・通行者への対応
道路使用許可を取得して道路上で作業する場合は、通行者や近隣住民への配慮が不可欠です。近隣住民がいつも通り道路を利用できなくなるうえ、工事の騒音や粉じんが発生するので、迷惑をかけてしまいます。
そのため、申請の際に近隣挨拶状の添付を求められるケースがあります。これは警察署が工事前の挨拶の方法、工事内容、期間、迂回路などを確認するためです。工事中は通行者に対して代替ルートの案内表示などでも対応しなければなりません。
また、幅員が狭い道路でやむを得ず全面通行止めにする場合は、町内会長の同意を得る必要があります。
道路の破損
建設作業で道路を使用していると、重機の操作を誤って道路やガードレールを破損してしまうことがあります。その場合、破損させた業者が復旧工事を行わなければなりません。その復旧にかかる費用は、道路使用許可を受けた者またはその施工会社が全額負担します。
道路上で作業をする場合、道路の破損以外にも交通事故や交通渋滞、近隣住民からのクレームなどにより、作業を停止しなければならなくなることも珍しくありません。
トラブルを避けるためにも、安全管理をしっかり行い、周辺環境と通行人への配慮を徹底します。また、罰則を受けないためにも許可取得の際に作業内容を正しく申請することが重要です。
許可期限を超過しそうな時の対応策
工事期間の延長などにより、やむを得ず道路使用許可期限を超えてしまう場合は、改めてその期間分を新規で申請します。このとき、空白期間ができないように早めに手続きすることが大切です。
他方、道路占用許可については、変更と更新があります。やむを得ず延長しなければならない場合、変更許可申請を行い、期間を延長します。更新手続きは、5年・10年といった許可期間が満了する際に行うものです。
無許可で道路を使った際のリスクと罰則
道路使用許可証の交付がないまま公道に車両を停めて作業をしていた場合、道路交通法119条により3か月以下の懲役または5万円以下の罰金を課されます。
道路上に許可なく石碑や看板を設置した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です。
たとえ短時間であっても道路に車両を停めるなどして作業を行う場合は、道路を本来の用途以外で使用することになるので、原則として道路使用許可を取得しなければなりません。
参考:道路交通法 第百十九条
解体工事の道路使用許可に関するよくある質問

ここでは解体工事の道路使用許可に関連した、よくある質問とその回答を紹介します。トラブルを避けるためにも道路使用許可の必要性や道路が使用できる範囲を確認しておきましょう。
荷物の積み下ろしでも道路使用許可は必要?
荷物の積み下ろしでも、公道上で作業したり駐車したりする場合には道路使用許可が必要です。一方、トラックを住宅などの敷地内に駐車し、作業をすべて敷地内で完結させる場合には、許可は不要となります。
つまり、以下の場合には、許可が必要だと考えておけばよいでしょう。
- トラックを敷地内に駐車せず、車道や歩道上に一時的に駐車する
- ・荷物の積み下ろしにより一時的に歩道に荷物を置く、歩道や車道で積み込み作業をする
道路使用許可で全面通行止めにできる?
道路使用許可で全面通行止めにすることは可能です。ただし、上でもご紹介した通り、町内会長、自治会長の同意が必要です。町内会長、自治会長の連絡先は、市町村の窓口に事情を説明すれば教えてもらえます。
全面通行止めにする場合は周辺住民の安全を考慮して、ガードマンの配置や看板などによる周知も必要です。迂回経路も申請の際に提出しなければなりません。
一方、片側通行止めにする場合は、町内会長の同意や迂回経路の提出は不要です。
まとめ

解体工事で車両や重機を道路上に駐車する場合、道路使用許可が必要です。そのため、見積りの際は見積書に道路許可申請の手数料などが含まれているか確認しましょう。
解体工事では道路使用許可だけでなく、建設リサイクル法に基づく届出やアスベストの事前調査など、さまざまな手続きが必要です。
業者選びの際は料金だけでなく、必要な手続きを行っているか、アフターサービスが充実しているかなどさまざまな観点から業者を選ぶようにしましょう。




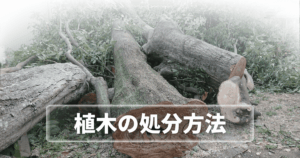
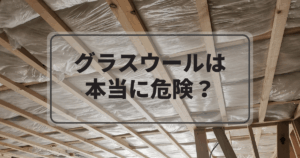
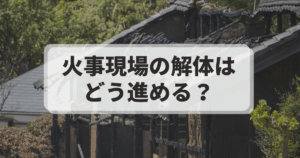
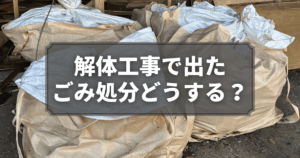

コメント