
解体工事で発生したごみは産業廃棄物として業者が適切に処分しますが、ごみの種類によっては自分で処分したほうがコストを抑えらえるケースもあります。
今回は、解体工事で発生するごみの種類と処理方法や、解体費用を抑えるために施主ができる処分方法、廃棄物をめぐって起こりやすいトラブルやその回避方法について解説します。
解体工事で処分が必要なごみの種類

ごみは、法律により一般廃棄物と産業廃棄物に明確に分けられており、種類に応じて正しく処分されなければなりません。まずは一般廃棄物と産業廃棄物の定義について解説していきます。
一般廃棄物
一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しないごみのことです。一般廃棄物は以下の3つに分類されます。
- 事業系一般廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないごみ
- 家庭系一般廃棄物:一般家庭から出たごみ
- 特別管理一般廃棄物:爆発性、毒性、感染性など、人々の健康や生活に被害を及ぼすおそれがあるごみ
一般廃棄物は市町村に処理責任があり、原則として市町村内で処理されます。
産業廃棄物
産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物で廃棄物処理法で定められた20品目のごみのことです。
具体的には以下の20種類となります。
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動植物性残さ
17.動物系固形不要物
18.動物の糞尿
19.動物の死体
20.コンクリート固形物等、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
産業廃棄物は事業者に処理責任があり、都道府県をまたがった廃棄物処理施設で処分することもできます。
解体工事で発生したごみの処分方法

解体工事で発生したごみは、それぞれどのように処理されるのでしょうか。
以下に解体工事で発生する廃棄物の種別ごとの処分方法を解説するので、業者に依頼するか自分で処分するかの判断材料にしてください。
紙・布製品
解体工事で発生した紙類や布製品はリサイクルできないケースも多くあり、産業廃棄物として処分されます。そのため、自分で市町村のゴミ収集に出したほうが割安です。
紙くずは、全てが産業廃棄物として扱われるわけではありませんが、解体工事をはじめとした建設業、パルプ製造業など特定の業種で排出されたもの、あるいはポリ塩化ビフェニルが染み込んだものは産業廃棄物となります。
これらの処分方法は大きく分けて再資源化、焼却処理、埋立の3つです。
建設業から生じた布も同様、繊維くずとして産業廃棄物扱いとなります。繊維くずはそのまま原料としてリサイクルされたり、繊維の原料として再利用されたりするほか、固形燃料に加工されたりします。
カーペット
絨毯やカーペットは産業廃棄物の廃プラスチック類に分類されるため、自分で普通ごみや粗大ごみに出すよりもコストが高くなる可能性があり、注意が必要です。
ナイロンやアクリルなどの合成繊維でできたカーペットは、廃プラスチック類として別のプラスチック材料にリサイクルしたり、化学原料として再生したり、熱源として利用したりします。
なお、天然繊維でできた絨毯・カーペットは繊維くずに分類されます。
陶器類
食器や瓦などの陶器類はリサイクルが難しいため、解体業者は産業廃棄物として分類します。
そのため、できるだけ燃えないごみとして自治体が指定した収集日に出すか、きれいなものはリサイクルショップに買い取ってもらったり、フリマアプリを利用して売却したりするほうがよいでしょう。
産業廃棄物として排出された陶器は、ガラスぐず、コンクリートくず及び陶器くずに該当し、破砕して道路工事の路盤材や再生砂としてリサイクルされますが、リサイクルに不向きなものや再利用できないものは粉砕後に埋め立て処理されます。
調味料
調味料は中身と瓶の仕分けなど、分別に非常に手間がかかるため、解体業者に依頼すると費用が高額になる傾向があります。
解体工事前までに自分で使い切ったり、中身を捨てて容器は燃えないごみやびん・缶の日に出すなどして対応したほうが費用を安く抑えられます。
捨てるときは新聞紙などで調味料を包んだものをビニール袋に入れて口を結び、燃えるごみとして捨てましょう。一部の自治体では廃食用油の回収を行っているケースもあるので、ルールにしたがって回収拠点に油を持ち込む方法もあります。
鉄類・木製品
鉄類や木製品は解体業者が買取やリサイクルに回すため、解体業者に処分を任せた方がお得です。
鉄くずは買取業者に売却できるため、無料で引き取ってくれるか、買取の際の査定額を解体費用から差し引いてもらえることもあります。
木材も同様、建設資材として活用したりリサイクルしたりすることが可能なので、無料で引き取ってくれるケースも少なくありません。
解体工事で発生した木材はおよそ9割が木質バイオマス燃料の原料としてリサイクルされます。木製の家具や木製製品がある場合は解体業者に相談してみましょう。
カーテン
カーテンもほかの布製品と同様、産業廃棄物として処分されるため、処分費用が割高になる可能性があります。そのため、自分で処分したほうがお得です。
家庭からでるカーテンは、多くの自治体で燃えるごみとして指定されています。大きいカーテンは小さく切ってからビニール袋に入れて出します。
自治体によってはカーテンは資源ごみとして回収されているケースもあるので、事前に確認が必要です。
また、カーテンのフックは金属製の場合は小さな金属類、プラスチック製の場合は燃えるごみなど、分別して処分します。
家電製品
家電製品も業者に依頼すると、産業廃棄物として処分されるため、自分で処分したほうがお得です。
家電製品のなかでもとくにエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目は、購入した店舗に引き取ってもらう、指定の引き取り場所へ持ち込むなどの方法でリサイクルに回さなければなりません。
解体業者に処分を依頼すると想定以上の費用がかかる可能性があるため、できるだけ自分で手配しましょう。
アイロンやオーディオプレイヤー、プリンターのような小型家電は粗大ゴミに出して処分できますが、小型家電リサイクル法により、無料または安価で回収してもらえることもあります。回収方法については自治体に問い合わせておくと安心です。
パソコン
パソコンはPCリサイクル法に基づき、確実にデータを消去して処分する必要があるため、自分で処分しましょう。
PCリサイクル法に基づいて処分しなければならないのは以下の製品です。
- デスクトップパソコン
- ノートパソコン
- 液晶ディスプレイ
処分方法は、パソコンメーカーの回収サービスを利用する、パソコン回収業者に依頼する、自治体の回収ボックスに持っていくなどがあります。
上記以外のプリンタやスキャナー、キーボードなどの関連機器は燃えないごみや粗大ごみとして処分できます。
その他のおすすめのごみ処分方法

まだ使える電化製品やきれいなものなどは、ごみとして処分せずに必要な人に譲り渡したり売却して収益を得ることができます。
以下におすすめの不用品の手放し方を紹介するので、自分に合った方法で処分しましょう。
友人や知人に譲渡する
友人や知人など、周囲で欲しい人がいる場合は、譲るのも一つの方法です。新品に近いものやきれいなものがある場合は欲しい人がいるか聞いてみるとよいかもしれません。
人に譲渡する場合は、無償で譲渡したほうがトラブルを防ぐうえでも無難です。もし、相手に購入すると言われた場合でも、最低限の金額のみを受け取るようにしましょう。
また、相手に不用品を送付する場合は、送料をどちらが負担するか、あらかじめ決めておくとスムーズです。
リサイクルショップへの売却
不用品の量が多い場合、種類が多岐にわたる場合はリサイクルショップに買い取ってもらうと一括で処分でき、買い取り料金が解体費用の足しになることもあります。
リサイクルショップは、家具や家電のほか、パソコンやスマートフォン、カメラ、食器、衣類、おもちゃなど、あらゆるものを買い取ってくれます。
量が多い場合は出張買取に対応してもらえるケースもあり、持ち込む手間を省けるので問い合わせてみるとよいでしょう。
オークションやフリマアプリの活用
ネットオークションやフリマアプリを活用すればリサイクルショップや不用品回収業者に売却するよりも高額で売却できる可能性があります。
フリマアプリなら自分で価格を決められるため、手放そうか迷っている品物がある場合には有効です。
フリマアプリのデメリットは販売に手間がかかることです。自分で商品の画像を撮り、出品し、売れたら梱包して発送しなければなりません。
商品がすぐに売れるとは限らず、売れるまでは保管しておかなければならないため、手間をかけられて、かつ自宅に保管場所がある場合に向いています。
ごみ処分で起こりやすいトラブルと回避策

ここでは、解体工事の残置物処分で発生しやすいトラブルと、回避策を紹介します。解体工事の廃棄物をめぐるトラブルは契約前に回避できるケースも多いので、起こりうるトラブルを把握して事前に対策しておきましょう。
見積もり後に追加費用が発生するケース
見積もりをとったにもかかわらず残置物の処分で追加費用が発生する理由は、想定外の荷物の量だった、搬出が困難な立地だった、などです。
多くの場合、現地調査をしっかり行っていれば荷物の量や搬出経路をシミュレーションできるため、追加費用の発生を回避できます。
ただし、瓦やコンクリート片などが地中に埋められていた場合などには解体作業が始まってからその存在が判明し、追加費用になることがあります。
追加費用の発生を防ぐためには、必ず業者に現場に来てもらい、残置物の内容を確認してもらったうえで見積もりを出してもらうことが大切です。
荷物の内容について施主から担当者に詳しく説明しておくことも、追加費用を防ぐために役立ちます。
不法投棄・無許可業者によるトラブル
産業廃棄物の処分にはコストがかかるため、まれに不法投棄をする悪質な業者がいます。
解体工事で発生した廃棄物は、解体工事業者が適切に処理を行わなければ罰則の対象となります。その責任は廃棄物の排出者が負うため、依頼した施主が罰せられることはありません。
ただし、業者が不法投棄を行っていると知りながら発注を行うと責任を問われるおそれもあるので、十分注意が必要です。
産業廃棄物を取り扱う許可に産業廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物処分業許可がありますが、業者は必ずしも許可の取得は必要ではありません。
これらの許可を持っている業者は、ハウスメーカーと提携していたり経営状況が安定していたりするので、ある程度信頼のおける業者といえるでしょう。
契約時に確認しておくべきポイント
解体工事の廃棄物処分でトラブルを回避するためには、見積書の内容を確認することが大切です。
見積書の中には産業廃棄物の品目別に処理費用が書かれています。これはコンクリートや木材など、品目によって廃棄物の処理方法や費用が変わるためです。
もし、廃棄物処理費用が品目別ではなく、一括で書かれている場合や、廃棄物処理費の項目がない場合は確認したほうがよいでしょう。
また、解体費用が相場よりも極端に安い場合もあとで高額な追加費用を請求されるリスクがあるため、作業内容についてしっかり確認しておきましょう。
信頼できる解体業者を選ぶ方法

解体工事でトラブルを防ぐためには信頼できる業者に依頼することが大切です。
ここでは、優良業者を選ぶためにとくに大切なポイントをお伝えするので、業者選びの参考にしてください。
許可証・実績・口コミを確認する
解体工事業者を選ぶ際は業者のウェブサイトなどで必要な許可を取得しているか、実績がどれくらいあるかを確認しておくと安心です。
解体工事を行うためには「建設業の許可」または「解体工事業登録」のいずれかが必要です。具体的には請負金額が税込み500万円以上の解体工事を行う場合は建設業許可、500万円未満の解体工事を行う場合は解体工事業登録を取得していなければなりません。
業者の実績はウェブサイトで確認できます。実績が写真とともに多数掲載されているか、地元で長く営業している業者かチェックしておきましょう。
さらに、ウェブサイトにお客様の声が掲載されていれば目を通しておくと、実際に依頼した人の生の声を確認できます。
見積もりの内訳説明が丁寧か
解体業者業者の良し悪しは、見積もりの際にもチェックできます。見積もりの内容や作業方法について詳しい説明があるか、質問に対して丁寧に回答してくれる業者かどうか確認しましょう。
優良業者を見極められるのは見積もり時だけではありません。問い合わせの際の電話やメール対応、現地調査では約束の時間を守るか、などを見ておくときちんとした業者かどうかを、ある程度判断できます。
業者選びの際は、料金の安さだけでは選ばず、担当者とスムーズにコミュニケーションが取れるか、時間や書類作成などがきちんとしているかなど、総合的に見て判断することが大切です。
解体工事のごみ処分に関するよくある質問

ここでは、解体工事で発生する廃棄物の処分に関してよくある質問とその解答を紹介します。家屋の解体工事を検討している場合は、廃棄物に関する疑問を解消しておきましょう。
自分で解体したものは産業廃棄物になる?
自分で何らかの構造物を解体した場合に出た廃棄物は、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となります。したがって、地域のルールに則ってゴミとして処分します。産業廃棄物とは異なり、費用は無料または低額で処分が可能です。
一方で、同じ物を解体する場合でも、解体業者が解体すれば産業廃棄物となり、処分費用もかかります。
注意点は、運搬コストや時間的なコストを考えると、解体業者に依頼したほうが安いケースもあることです。廃棄物の量や種類を考慮し、適切な方法を選びましょう。
工事で出た廃棄物は誰の負担で処理するの?
解体工事で発生した産業廃棄物の処理責任は解体工事業者にあり、その費用負担も解体工事業者が行います。
廃棄物は排出事業者である解体業者が責任を持って適切に処理することが求められ、業者はマニフェスト制度を利用して廃棄物の流れを管理し、施主も処理が適切に行われているかを確認できます。
一方で、建物にある残置物は所有者である施主が費用を負担し責任を持って処分する必要があり、地域のルールに従って廃棄するか、一般廃棄物処理業の許可を持つ業者に委託して処理します。
まとめ

解体工事で発生した廃棄物は、業者の責任で中間処理施設や処分場へ運搬し、適切に処分されます。ただし、自分で一般ごみとして出したほうが安くなるケースも少なくありません。
解体費用をできるだけ抑えたい場合は、業者と相談して自分でできる分は無理のない範囲で処分したり、売却したりするとよいでしょう。





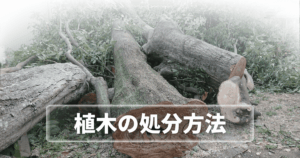
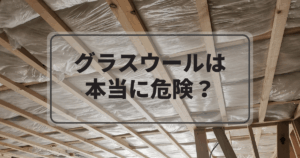
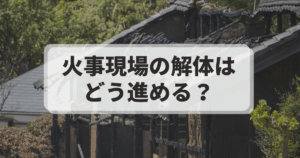

コメント