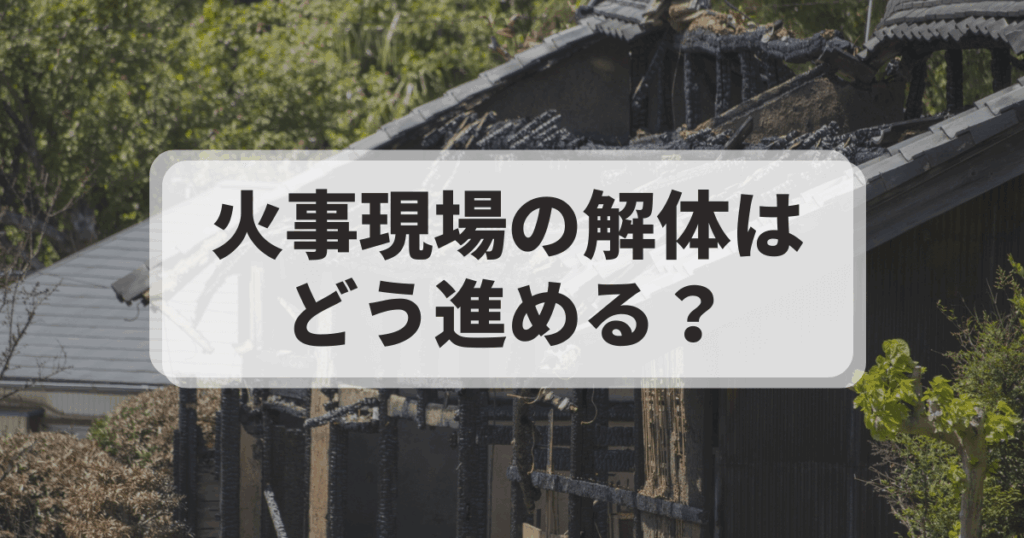
火災で自宅が燃えてしまった場合は、建物を解体する必要があります。しかし、すぐに解体してよいわけではありません。
必要な手順に従って解体工事に着手することで、保険金や補助金を適切に受け取れたり、かかる費用が免除されたりします。
この記事では、火事現場の解体の流れや費用、解体費用を安くするためのポイントを紹介します。
火事現場の手続き・解体の流れ

まずは火事の被害に遭った場合に行う手続きから解体工事までの流れを紹介します。
順番を間違えると保険金が正しくおりない可能性があるので、流れを間違えないようにしなければなりません。
被害状況の記録・撮影
火災が鎮火し、現場検証が終わって現場に立ち入ることができるようになったら、被害の状況を写真に記録します。写真は、火災保険の申請や罹災証明書を取得するための重要な資料です。
建物全体、損壊した箇所、焼けた家財道具など、広範囲を細かく撮影します。写真にメモを付け加えておくことも大切です。被害に遭った物や財産はリストにしておくと申請手続きに役立つはずです。
時間が経過すると記憶が曖昧になったり、火災の状況によっては直後の状態を維持しにくかったりします。早めに現場に足を運び、詳細に記録をとるようにしましょう。
近所へご挨拶
近所に心配をかけてしまったこと、お騒がせしてしまったことをお詫びに伺います。
火災が故意または重大な過失が原因でなければ法律上の賠償責任を負うことはありません。とはいえ、近隣住民は怖い思いをしたり、煙の被害を受けたりした可能性が高いため、挨拶は必要です。
挨拶回りの際はタオルや洗剤、菓子折りなど、2,000〜3,000円程度の品物をを持って訪問することをおすすめします。
貴重品の回収
火災現場は日中は消防署や業者などが出入りしますが、誰もいなくなった夜間に盗難被害が発生しやすくなります。そのため、貴重品や大切なものは早めに回収しましょう。
ただし、現場に勝手に立ち入ることはできません。消防署による調査が完了し、立ち入り許可が出てから入るようにしてください。
また、火災現場は建物の一部が倒壊していたり、有害物質が発生したりするなど、危険な状態です。回収は片付け業者に依頼するか、自分で回収する場合はマスク、手袋などを着用して安全に配慮したうえで行ってください。
貴重品には通帳、印鑑、健康保険証、運転免許証、保険証券、クレジットカードなどがあります。焼失した場合は再発行の手続きをしましょう。
罹災証明の取得
罹災証明書とは、火災などの災害状況を証明するための公的な書類です。市町村が被害の状況を調査し、全壊・大規模半壊・半壊というふうに被害の程度の認定や災害状況を証明することで、保険金の請求や各種支援を受けられるようになります。
罹災証明書の対象者は被災した住宅に住んでいる世帯主または所有者です。同じ住所に複数の世帯が暮らしている場合は、それぞれの世帯主が申請できます。賃貸住宅の場合は居住者が申請できます。
罹災証明書を取得する手順は以下の通りです。
- 被害状況の確認・記録
- 市町村の窓口に申請書を提出
- 現地調査・認定
- 罹災証明書の発行
罹災証明書の発行は申請から1~2週間です。
保険会社への連絡
罹災証明書を取得したら、加入している火災保険会社に連絡します。火災保険への加入は、法律上は任意ですが、住宅ローンを組む場合は必須となるので、ほとんどのケースで加入しているはずです。
保険会社に連絡すると、火災保険会社から現地調査についての案内があります。火災保険で解体費用や残存物の片付け費用を補償してもらえることがあるため、契約の補償内容について確認しておきましょう。
保険会社は火災に遭った建物を現地調査し、被害の状況を把握したうえで保険金を算出します。
重要なのは、解体作業が始まってしまうと保険金が支払われなくなってしまう可能性があるため、保険会社の損害鑑定が終わるまでは解体に着手しないようにすることです。
解体業者への連絡
解体業者に連絡して、見積もりを依頼します。解体作業には残存物の撤去も伴うので、残存物の処分も請け負ってもらえるか確認しておくとよいでしょう。
火災の被害に遭った建物の解体費用は、一般的な建物の解体よりも費用相場が高い傾向がある点は知っておいてください。
火災に関する補助金制度に詳しい解体業者だと安心です。見積もりは複数の業者から相見積もりをとり、内容を比較して選ぶのがおすすめです。
仮住まい・ライフライン停止の手配
仮住まいの確保も忘れてはいけません。仮住まいは自治体に相談すると市営住宅に入居させてもらえる可能性があります。
また、火災保険会社が補助金を出してくれることもあるので、自治体、火災保険会社の窓口に相談しながら住まいの確保を進めていきましょう。
火災に遭った住宅のライフライン停止も速やかに行います。消火活動が行われた際、ガス漏れによる爆発を避けるために消防署からガス会社に連絡し、ガスの供給をストップするのが一般的です。
一方で、電気や固定電話などについては連絡を入れない限り停止されず、基本料金を支払い続けることになるので、早めに連絡しましょう。
火災物件の解体工事
各種手続きが終わったら解体工事を開始します。解体工事では騒音、振動、粉じんの発生や、車両の出入りで近隣住民に迷惑をかけることがあります。
トラブルを防ぐために、解体作業の着工1週間ほど前にあいさつ回りをしておくとよいでしょう。
30坪の木造住宅であれば2週間程度で解体作業は完了します。工事が完了したら解体工事業者から完了報告書を受け取ってください。完了報告書を自治体に提出すると、多くのケースで災害見舞金が支給されます。
火災物件の解体費用相場・目安

火災物件の解体費用は一般的な住宅の解体に比べて費用は変わるのでしょうか。ここでは、火災で損傷した建物の解体費用の相場や、利用できる補助金制度について解説します。
火災現場の解体費用が通常より高くなる理由
火災現場の解体費用の坪単価の目安は構造別に以下の通りとなり、通常の解体工事よりも高額になる傾向があります。
- 木造:31,000~44,000円
- 鉄骨造:34,000~47,000円
- RC造:35,000~80,000円
費用が高額になるのは、通常の家屋より解体や廃棄物の分別に時間と手間がかかるためです。解体工事では廃材を定められたルールに基づいて分別し、正しく処分しなければなりません。
分別は作業員が確認しながら行いますが、火災により焦げて損傷しているため分別に時間を要し、人件費が余分にかかります。
火事による建物や家屋の解体費用内訳
住宅の解体費用は以下のような内訳です。
- 解体費用
- 廃棄物処分費用
- 整地費用
- 必要諸経費
解体費用は住宅本体、ブロック塀などの外構を解体する付帯工事費用などの作業費のほか、重機使用料や足場を設置するための仮設工事費用などから成ります。
解体作業で発生したがれきは産業廃棄物に該当するため、処分費用がかかります。そのほか、土地を次の使用用途に合わせて整地する費用、工事車両の駐車料金や水道代などの諸費用で工事の総額が構成されるのが一般的です。
火災残骸処理費用の補助金制度
解体工事で発生する一般廃棄物の処理費用を支援する火災残骸処理費用の補助金制度は、一般廃棄物処理費用減免制度が代表的です。
この制度を利用すれば火災で発生した廃棄物の処理費用が無料または割引され、被災者の経済的不安を軽減する役割があります。
減免を受けるためには罹災証明書を用意のうえ、市町村の窓口で申請が必要です。減免制度の詳細は自治体によって異なるため、内容や条件については窓口で確認しておくと安心です。
火事にあった場合の解体業者の選び方

火事に遭った住宅の解体業者はどのように選べばよいのでしょうか。火災の被害を受けた住宅の解体は通常の解体工事よりも費用が高いため、慎重に選びたいものです。
以下に業者選定のコツを紹介するので、参考にしながら優良業者を見極めるようにしてください。
火災現場の実績・有害物質対応の有無
火災の被害を受けた建物の解体は、経験豊富な業者に依頼することが大切です。建物の構造が不安定になっていたり、現場にガラス片が散乱している可能性があるためです。
また古い建物では、建材にアスベストが使用されている可能性があり、その場合は決められた方法で処理しなければなりません。
このような作業を適切に行うためには、火災現場の解体実績やアスベストの対応ができる業者に依頼する必要があります。
業者のウェブサイトを見て対応できるかチェックしたり、メールや電話で問い合わせを行い、実績について確認しましょう。
複数業者への見積もり
解体工事を依頼する際は、複数業者に相見積もりを依頼すると失敗を防げます。解体工事には定価がないため、費用相場が明確ではありません。
とくに火災現場の解体は、被害状況や残存物の量などにより費用が大きく変わります。複数の業者から見積りをとることで費用相場を把握でき、不当に高額な費用を請求する業者を避けられます。
火災現場の解体工事は現場の状況をしっかり確認したうえでかかる費用を算出してもらわなければなりません。そのため、必ず現地調査をして見積書を提示してもらうようにしてください。
火災保険の適用
住宅が火事に遭った場合、火災保険で解体費用を補償できる場合があります。契約内容によって費用の上限が設けられていたり、残存物の片付け費用が補償対象となっているケースもあるため、まずは契約内容を確認することが大切です。
注意点は解体工事に着手する前に保険会社に連絡することです。解体工事が始まってから連絡しても保険金の対象にならない場合があります。
解体工事を依頼する前に、まずは保険会社に連絡を入れて補償内容を確認してもらいましょう。
火事にあった建物を放置するリスク

火災の被害にあった建物をそのままにしておくとさまざまなリスクが増加します。地域の住民に危険を及ぼすおそれがあるため、早めに解体するようにしましょう。
ここでは、建物を放置すると起こりうるリスクを紹介します。
倒壊の危険性
火災後の家屋を放置した場合に最も危惧されるのが建物の倒壊です。焼損により木材は炭化し、コンクリートは爆裂により壁面が不安定化、金属部も熱で変形しているため、建物に必要な強度は失われていると考えられます。そのため、悪天候や地震などで倒壊するリスクが高まります。
倒壊リスクの高い建物を放置していると、近隣住民に危険が及ぶ可能性も否定できません。万が一近隣に損害を与えた場合、損害賠償請求されるおそれもあるため、早めに解体・撤去しましょう。
悪臭や害虫の発生
火災現場をそのままにしていると悪臭や害虫の発生により近隣に迷惑をかけてしまうことがあります。
火災現場で起こりうる悪臭は、煤や灰などの悪臭のほか、雨水や消火水が滞留することによる害虫やカビ、汚泥などによる腐敗臭です。また、空き家状態で放置していることにより、害獣の住処となることもあるでしょう。
臭いだけでなく、黒焦げの外観のまま放置していると景観が悪化して近隣住民に不快感を与えてしまいます。このような影響を防ぐためにも速やかに建物解体を実施し、ゴミを撤去して土地内の美観を維持しなければなりません。
火事解体費用の増加
火災で燃えた建物を長期間放置すると解体作業の費用が高額になるおそれがあります。劣化した建物は解体作業が複雑になるうえ、倒壊の危険性に配慮した安全対策などのコストが増大するためです。
火災で焼けた家具などは再利用が難しく、長期間放置した状態では腐食が進んでいるケースもあり、廃棄物の分別にも時間がかかります。そのため人件費が増大し、廃棄物の処理費用が増加しやすくなります。
解体費用を安く抑えるコツ

火事で焼損した建物の解体工事は通常の建物解体工事に比べて費用が高額になりがちです。
では、少しでも費用を抑えるにはどのようにすればよいのでしょうか。以下に、解体コストを抑える方法を紹介します。
自分での残材・可燃ゴミ処分を行う
廃材を自分で片づけることで費用を抑えられる可能性が高まります。解体工事で発生するゴミは産業廃棄物として扱われるので、処分は有料です。業者が責任を持って処分場または中間処理場へ持ち込み、その費用は解体工事の依頼主が支払います。
一方で、個人が捨てるゴミは一般廃棄物となり、無料または安価で処分が可能です。つまり、自分で残存物を分別し、粗大ごみや一般ごみとして回収または持ち込みをすれば費用を大幅に抑えられます。
ただし、火災現場は非常に危険なため、作業を行う場合は安全に配慮が必要です。解体工事業者と話し合い、できる範囲のみ自分で行い、少しでも難しい作業は業者に任せた方が安全です。
自治体からの補助金を受ける
自治体は火災などにより被害を受けた場合に、補助金制度で生活の再建をサポートしています。条件に合うものがあれば申請して活用すると、金銭面の負担が軽くなるでしょう。
代表的なものに災害見舞金制度というものがあります。これは災害後の生活を支援するための一時的な見舞金です。支給額は被害の状況や災害の種類によって変わるので、自治体窓口に相談するとよいでしょう。
また、固定資産税が減免されるケースや、確定申告で雑損控除の申告をすると所得税や住民税が軽減される場合もあります。こちらも被害の状況によって減免内容が異なるため、詳細は自治体に確認しておくと安心です。
解体前に売却を検討する
今後その土地に住む予定がない場合は、火災保険を受け取ったら売却してしまうのも一つの選択肢です。この場合、建物に評価額がつくことはなく土地のみの値段で売却することになりますが、解体工事は土地を買い取った不動産業者が費用を出して行うため、売主の負担はなくなります。
火災後一定期間が経過すると、仮住まいで生活が始まっているはずです。今後の生活についても長期的に考えて、自分で解体して何らの用途で使用するのか、売却して解体費用の負担を抑えるのか決めるとよいでしょう。
火事現場の解体に関するよくある質問

ここでは、火事で被災した家屋の解体に関してよくある質問とその回答を紹介します。
火災後は行わなければならない手続きが多く、分からないことも多いはずなので、以下をチェックして少しでも疑問を解消しておきましょう。
火災現場の解体で出た廃棄物はどういう扱いになる?
火災現場の解体で発生した廃棄物は産業廃棄物となり、業者の責任で分別し処分場または中間処理場に運ばれます。
産業廃棄物の処理費用は原則として解体工事費用に上乗せされます。あらかじめ現地調査で発生するごみの量を予測し、見積もり金額を提示するのが一般的です。
一方で、火災現場に残った家財や衣類などを自分で処理場に持ち込んだり、自治体に回収してもらう場合は火災ごみ、罹災ごみとよばれる一般廃棄物の扱いとなります。
一般廃棄物は自治体の補助制度を活用すると廃棄物処理にかかる料金を抑えられます。そのため、できる限り自分でごみを処分すると費用の節約につながるはずです。
火事で発生した解体費用は誰が払う?
火災で発生した建物の解体費用は、火災の責任が誰であるかにかかわらず、原則として建物の所有者が負担します。たとえ隣家からの延焼で自宅に損害が出ても、火元の住民に重大な過失がない限り損害賠償請求はできないためです。
ただし、火災保険や自治体の補助金制度を利用できる場合があります。慌てずに罹災証明書を用意したうえで保険会社に補償内容を確認する、さらに自治体に補助金の条件について相談するようにしましょう。
まとめ

火災の被害を受けた建物は、必要な手順を踏んで解体する必要があります。解体費用を抑えるには、手続きの順番を間違えないこと、補助金については市町村の窓口に相談し、活用できる補助金制度とその条件について理解しておくことが大切です。
火災現場の解体工事は実績の豊富な業者に任せると安心です。事前に業者に問い合わせたり、現地調査の際に質問して、丁寧に回答してくれる業者に依頼するようにしましょう。









コメント