
原材料価格などの高騰を受け、近年では食品やサービス、光熱費などさまざまなもので値上げの動きが広がっています。このような環境下で、解体工事の費用も値上がりしているのをご存じでしょうか。
解体費用の高騰は、空き家を解体したいと考えている方にとっては大きな問題といえるでしょう。
この記事では、解体費用が値上がりした理由や費用を抑えるための対策を解説します。
解体費用の値上がり理由

解体費用の値上がりは、さまざまな原因が絡み合っており、今後もこのような状況は続くと考えられています。
なかでも解体費用を押し上げているのは人件費や廃棄物処理に関する費用です。
人件費の高騰
解体業をはじめとした建設業界では人件費が高騰しており、これが工事費の値上げにつながっています。
近年では建設業界に進む若い人が少なくなっているため、職人の高齢化が進み、長年にわたって人手不足がつづいています。
これらを改善しようと業界で働き方改革を進めていることも工事のコストを押し上げている原因のひとつです。
労働時間が長く休日労働が多いイメージから脱却しようと労働環境の整備が推進された結果、労働時間が減少して工期の長期化が進み、工事の労務費が増加しているのです。
産業廃棄物処分費用の高騰
解体費用の多くを占める産業廃棄物処理費用の高騰も解体工事の価格に大きく影響しています。
廃棄物の最終処分場の処理費用は、自然災害による廃材の増加や国内の産業廃棄物処理施設の処理が追い付いていないことで値上げが避けられない状況です。
さらに、不足している産業廃棄物処理施設を新設しようにも、地域住民の反対により施設の建設が難航するなど、処理施設のパンク状態が続いていることが費用高騰につながっています。
中国の資源ごみ輸入禁止
国内の廃棄物処理施設のキャパシティが限界になっているのには、中国が資源ごみの輸入禁止に踏み切ったことも関係しています。
中国は1980年代頃から原料不足解消のために世界から廃棄物を輸入してきました。しかし2010年頃から環境問題が深刻化したことで規制強化へと向かい、2017年には外国からのごみの輸入禁止の方針を打ち出しました。
これにより、解体工事で発生する木材や廃プラスチックなどの資源ごみが行き場を失っており、高騰したコストが解体費用に上乗せされているのです。
アスベスト規制の強化による影響
2021年の大気汚染防止法の改正に伴い、アスベスト(石綿)の規制が強化されたことで、アスベストを含有する建物の解体作業の工程が増え、工事費用の高騰につながっています。
規制強化により、一定規模の解体工事では原則としてすべての建物でアスベストの事前調査と報告が義務付けられました。また、アスベストが使用されている建物の解体は養生して粉塵が飛散しないようにし、がれきはルールに則って処理しなければなりません。
建物にアスベストが含まれている場合は上記の工程にかかる費用に加えて処分費用が加算され、解体工事の金額が高額になります。
建物や立地による値上げ要因

ここまで、近年の国内外の事情や規制による解体費用の高騰を紹介してきましたが、建物の条件により、解体費用が高額になることもあります。
次に挙げる要因を見て、解体を検討している建物が該当していないかチェックしてみましょう。
地中埋設物がある
敷地内に地中埋設物がある場合、撤去費用がかかるため、解体費用が高くなる傾向があります。
井戸や浄化槽は事前に図面で分かることが多いですが、石や岩、以前の住宅を解体した際に埋められた廃棄物は、解体工事が始まってから見つかるケースが少なくありません。その場合、付帯工事による追加費用を請求される可能性があります。
とくに以前建っていた建物の地中杭の存在が判明した場合、追加費用が高額になるおそれがあるため注意が必要です。
地下室など地上以外に構造がある
地下室のような地階に空間がある建物の場合は、解体工事が高額になります。地下室には防水層や断熱材が施してあるので、これらの資材をすべて撤去しなければなりません。
さらに地下室は埋め戻しが必要で、地盤沈下しないように転圧して締め固めながら埋め戻していきます。
地下収納のようなスペースであれば解体費用に50万円ほどの上乗せで済みますが、6畳程度の1部屋の地下室の場合、構造によって変化するものの、およそ100~300万円ほどの料金が上乗せされると考えておきましょう。
周辺住宅が老朽化している
解体工事の現場周辺の住宅が老朽化している場合もコストが余分にかかるケースがあります。
解体工事では振動の発生がつきものです。周辺の家屋や建物が老朽化していると、振動により外壁にひびが入ったり建物が傾くなど、損害を与えてしまう可能性があります。そのようなことが起こらないように、周辺住宅に対して家屋調査を実施する場合はその分の費用がかかります。
通常、解体工事により近隣の建物が損傷してしまった場合は業者に賠償責任があるため、補修費用は業者が負担するのが基本です。
しかし施主の指図によって問題が発生した場合や、反対に施主が指示をしなかったために隣家を損壊させた場合は、施主に賠償責任が生じるので注意しましょう。
狭小敷地・密集住宅地の場合
解体現場に工事車両や重機が入れないほど道が狭い場所や、現場の敷地が狭小の場合は費用が高くなりやすいといえるでしょう。
解体工事で発生したがれきや建築資材はトラックに載せて搬出しなければなりません。その際に敷地の前にトラックが進入できないと、トラックまで作業員が建材を運ぶことになり、工期が長くなる可能性があります。その分人件費がかかり、建物解体の費用に上乗せされます。
解体工事では仮設足場を設置しなければならないので、足場設置費用も高額になるでしょう。
重機が入れないほど狭い場合も同様です。解体作業が手作業となり、解体費用が高額になる傾向があります。
周辺の道路事情が悪い
周辺道路の条件も解体費用に影響するので注意が必要です。現場が狭い道路に面しているときは、車両通行止めが必要になる場合があります。このとき、所轄の警察署で道路使用許可を取得し、車両通行止めをします。道路使用許可の申請費用は2,500円程度が目安です。
通行止めが必要な場合はさらにガードマンを配置しなければなりません。その場合、1名あたり約2万円ほどの費用がプラスとなります。
敷地に面した道路の通行量が多い場合もガードマンが必要なケースもあるので、追加費用にならないよう、現地調査の際に業者に道路事情について説明しておきましょう。
解体費用を抑える工夫と対策
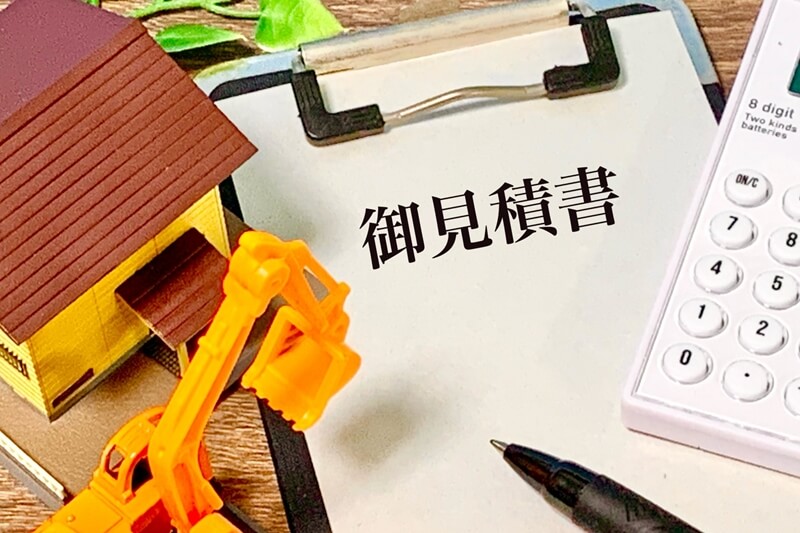
解体費用は少しの工夫で安くすることができます。
ここでは、施主ができる解体費用のコストを下げる方法を紹介するので、業者と相談して取り入れられるものを取り入れ、お得に解体工事を実施しましょう。
できるだけ早期に解体する
解体工事費用を安く抑えたいなら、できるだけ早く解体することが大切です。解体工事は値上がりを続けており、今後もこの状況は続きそうです。
それだけでなく、空き家を放置して特定空家とみなされてしまうと、固定資産税の住宅用地特例の優遇措置が解除され、固定資産税が6倍になってしまうなど、大きなコストがかかるようになってしまいます。
空き家をそのままにしていると結果的に多額の費用を支払うことになるので、解体、更地にして売却、リフォームなど、早期に適切な土地活用方法を検討しましょう。
残置物を極力減らす
敷地内に家具や家電などの残置物が多く残っていると、工事費用が高くなるのでできるだけ自分で片付けておきましょう。
とくに家電製品のなかには家電リサイクル法に基づいて処理しなければならないものがあり、処理費用によって工事費用が高くなる場合があります。
しかし自分でこれらの残置物を適切に処理しておけば、解体費用を抑えられるはずです。
とはいえ、自分で廃棄物処理場に持ち込んだり、不用品回収業者に回収を依頼したりするのは、手間がかかるだけでなく、かえってコストがかかるケースもあるでしょう。
事前に解体業者の処理費用と、不用品回収業者などほかの業者に依頼した場合の費用を比較して検討すると費用を節約できます。
廃棄物を厳密に分別する
産業廃棄物の処分費用高騰に対応するため、廃棄物の分別を厳密に行うことも大切です。木造住宅なら木くず、鉄骨造の建物ならコンクリートや金属くずを分別します。
そのほか、廃プラスチック、ガラスなどをきちんと分け、混合廃棄物をできるだけ減らして費用を抑えます。
分別処理については解体業者が行うので、廃棄物を適切に処理している業者に依頼しましょう。
信頼できる業者を選ぶには、業者が建設業許可または解体工事業登録を取得しているか、さらに産業廃棄物収集運搬許可を取得しているかを確認しておくと安心です。
自治体の補助金や助成金を活用する
空き家の解体では自治体の補助金や助成金を利用できる場合があります。解体工事は高額なため、条件を満たしている場合は利用すると費用を抑えられるでしょう。
空き家解体に対して支給される補助金の上限は、多くの市町村が20~100万円を上限としています。各自治体で上限金額に差があるため、事前に確認が必要です。
また、補助金の支給対象と条件、手続き方法は自治体によって異なるので、自治体の窓口に相談しておきましょう。
解体業者の繁忙期を避ける
解体工事は繁忙期に依頼すると工事が高くなる傾向があるので、できるだけ閑散期に依頼するようにしましょう。
解体工事の繁忙期は12~3月です。12月は年内に工事を終わらせたい人のニーズが高い時期であり、2~3月は企業の決算月が集中するため、企業からの依頼が殺到しやすく人件費や重機の回送費用などが高騰します。そのため、解体業者が安く工事を請け負うのは難しい時期といえます。
一方で、4~9月は閑散期となり、費用が安くなる傾向があるだけでなく、希望した日に作業を依頼しやすい時期です。
ただし、6月は梅雨で雨が降ると作業ができない日が多くなり、8月は業者がお盆休みに入るため思うようなスケジュールで工事ができない場合があります。
複数業者からの見積もりを取る
解体工事を適正な金額で依頼するには、複数の業者から相見積もりをとりましょう。
相見積もりをとると、坪単価など工事の費用相場を把握しやすく、不当に高い料金で工事を依頼するといった失敗を防げます。
相見積りの際は費用の安さだけで判断せず、見積書に詳細な工程と費用の明細が記載されている、質問に対して営業担当者が丁寧に明確に回答してくれる業者に依頼すると後悔のない工事を依頼できるはずです。
まとめ

解体費用はさまざまな原因で年々上昇しており、今後も値上がり傾向は続くことが予想されます。
そのため、不動産相続した場合や所有している家屋の解体工事を予定している場合は、できるだけ早めに依頼した方が負担額が少なく済む可能性が高いといえるでしょう。
また、費用を安く済ませる方法や補助金については、解体工事業者に相談してアドバイスをもらうのがおすすめです。









コメント