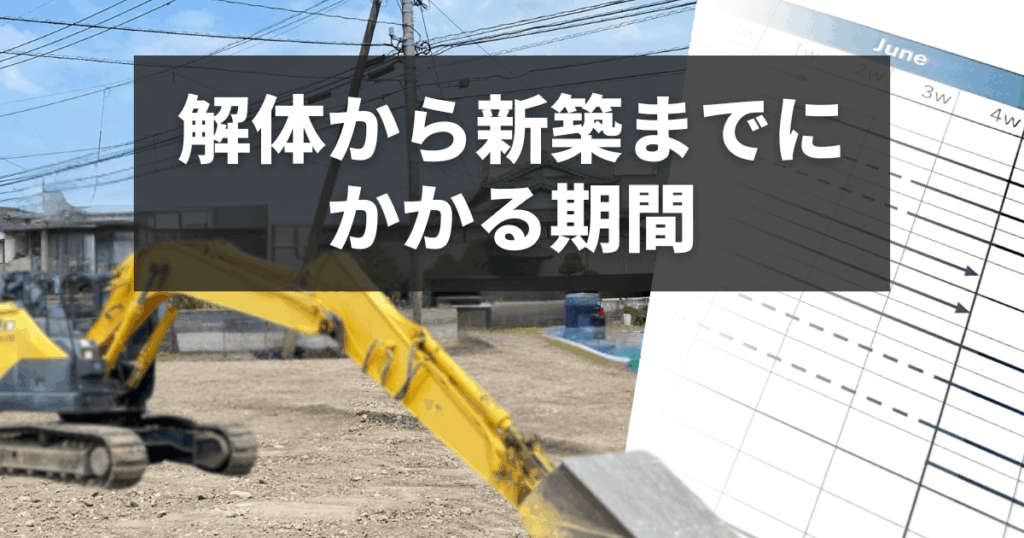
住宅の建て替えは、解体工事と新築工事の二段階で行われるため、工事期間も長くなります。住宅の規模や構造によって工事期間も変わるので、事前にどれくらいかかるのか把握しておくと安心です。
この記事では、住まいの解体から注文住宅の新築工事までの期間の目安や、建て替え工事期間中の注意点などについて解説します。
解体から新築までにかかる全体の期間目安

住宅の建て替えは、解体工事と新築工事を合わせると8か月〜12か月半ほどかかります。解体から新築住宅が完成するまで施主がすることも多いので、まずは大きな流れを押さえておきましょう。
解体工事から新築完成までの流れ
解体工事から新居が完成するまでの流れは以下の通りです。大まかにイメージしておくだけでも工事の計画を進めるうえで役立つので、まずは全体の流れを把握しておきましょう。
- 建築工事を依頼する建設業者を探す
- 設計プラン・希望・予算の打ち合わせ
- 工事請負契約を交わす
- 住宅ローン申し込み
- 解体工事業者を探す
- 仮住まい探し・契約
- 解体工事
- 地盤調査・地盤改良工事
- 新築工事
- 外構工事
- 引き渡し・登記登録
木造・鉄骨・RCなど構造別にかかる期間の違い
解体工事や新築工事の期間は、建物の構造に影響されます。構造別の工事期間は以下の通りです。
木造:3~10日
鉄骨造10~20日
鉄筋コンクリート造:2週間~1か月
木造:4~6か月
鉄骨造:5~7か月
鉄筋コンクリート造:7~10か月
注文住宅の建築は業者によって工事期間が変わります。とくにハウスメーカーと工務店では工期に差が生じやすいといえるでしょう。
ハウスメーカーは独自の部材のルートやマニュアルが整備されているため、工期が安定しやすい点がメリットです。一方で、工務店は地域密着型で柔軟な対応に長けている会社が多く、こだわりの住宅を実現しやすいというメリットがあります。
解体工事にかかる期間と準備

では、解体から新築までの工程は、それぞれどれくらいの期間がかかるのでしょうか。まず、ここでは建物の解体工事にかかる期間と、施主がしておく準備について解説します。
見積もり・業者選定
まずは解体工事を依頼する業者を選びます。業者を選ぶ際は3社程度から相見積もりを取り、見積書の内訳などを比較して決めましょう。相見積もりを取ることで費用相場を把握でき、不当に高額な金額を提示されることを防げます。
見積もりの際は、現地調査が必要です。現地調査をせずに見積もりを取ると、追加工事の発生など、トラブルの原因となります。
現地調査の所要時間は1時間程度です。その後、見積書提示まで1〜2週間かかると考えておきましょう。
解体工事にかかる日数
一般住宅の解体工事にかかる日数は、約25坪の木造建築で3〜10日が目安です。建物の構造により工期は変わり、同じ25坪の住宅でも鉄骨造の場合は10〜20日ほどかかります。
また、延べ床面積が広ければその分工期が長くなると考えておきましょう。
工事期間は上記の通りですが、実際には業者選定、道路許可の申請、近隣挨拶、解体作業後の整地などを含めると、2か月程度かかるのが一般的です。
解体後に行う整地・地盤調査などの期間
解体後に行う整地作業は2〜5日程度かかります。整地作業は解体工事後に新しい住宅を建てるために土地を平らに整える作業です。
地盤調査にかかる期間は1週間程度を目安として考えておいた方がよいでしょう。調査自体は1日で終わることがほとんどですが、結果が出るまでに1週間ほどかかります。
地盤調査の結果、地盤改良工事が必要な場合は新築の着工前に行います。地盤改良工事は敷地の表層部分を改良するか、地中に杭を打って補強しますが、どちらを選ぶかは地盤調査の結果次第です。
建て替えに向けた事前準備期間

次に新築住宅の建築に向けた準備の内容とその期間を紹介します。施主が行わなければならない手続きや資金計画などがあるので、スケジュールが遅れないよう、早めに準備しておきましょう。
建築会社者の選定・契約
建築会社の選定期間は1か月〜1年と、施主のスケジュールや業者選び、打ち合わせの内容によって幅があります。
新築する家のおおまかなプランや希望が決まったら、解体工事のときと同様にまずは複数の建築会社に見積もりを依頼しましょう。
同じように要望を出しても、建築会社によってプランや費用が異なります。こだわりたい部分や家族のライフスタイルを担当営業者にできるだけ具体的に伝え、プランを出してもらってください。
業者選びの際は費用だけで決めるのではなく、担当者とのコミュニケーションやアフターサービスなど、総合的に見て判断すると、長期的に安心して家のことを任せられます。
住宅ローン仮審査や資金計画
住宅ローンの審査にかかる期間は、1か月ほど見ておくとよいでしょう。とくに借入金額が高額の場合や、完済時の年齢が高い場合、金融機関が繁忙期の場合は審査が長引く可能性があります。
建て替えのプランや費用が決まってきたら、金融機関に住宅ローンの仮審査を申し込みます。仮審査では書類をもとに金融機関が借入可能額や金利の条件を提示するのが一般的です。仮審査を通過すると、本審査に進みます。
本審査は、ハウスメーカーとの工事請負契約書の写しを提出し、詳細な審査を行います。本審査を通過すると融資の決定です。
建築確認申請や行政手続きにかかる期間
建物を新築したり増改築したりする場合に行う建築確認申請は、審査が完了するまでに1~3週間かかります。混雑状況や建物の規模によっては1か月以上かかることもあるため、注意が必要です。
申請は本来施主が行いますが、実際には施主に代わって業者や建築士が行います。
また、請負金額が税込み1500万円以上、または延べ面積が150㎡以上の建築一式工事を請け負う業者は、「建築一式工事」の建設業許可が必要です。
これは施主が手続きする必要はありませんが、法令に従って施工している業者を選定するためにも、業者選びの際にホームページで許可を取得しているかチェックしておくと安心です。
建て替えの新築工事にかかる期間

建て替えの新築工事の工期は、建物の構造や工法の種類によって変わります。
ここでは、住宅で用いられる建築工法別の工事期間と工法の特徴を紹介するので、計画している工法ではどれくらいの期間がかかるのか、目安を把握しておきましょう。
在来工法
在来工法の住宅の建築期間は、約4〜5か月が目安です。在来工法は在来軸組工法とも呼ばれる日本の伝統的な木造建築工法で、柱と梁で骨組みを組む工法です。
この工法は日本古来の工法を基礎としながら、現代の構造力学的な観点を取り入れ、筋交いや耐力壁で補強して地震や台風に耐えられる構造になっています。
間取りの自由度が高く、広い空間や大きな開口部をつくりやすい点が特徴です。
2×4工法(ツーバイフォー工法)
2×4工法の工期は在来工法に比べて短く、約2〜4か月で住宅が完成します。
2×4工法は、木造枠組み壁工法とも呼ばれる、面で建物を支える工法です。2インチ×4インチの木材で枠組みをつくり、この枠組みに構造用面材を接合して、耐震性のある頑強な六面体構造を形成します。
2×4工法は、部材の規格や施工手順が細かく決められているため、職人の経験や技術に左右されずに安定した品質の建物を建築できる点が特徴です。
地震や風などの揺れをバランスよく分散させるため、耐震性は在来工法のおよそ1.5〜2倍あると考えられています。
軽量鉄骨造
軽量鉄骨造の住宅の工期は、一般的に5〜7か月、プレハブ工法であれば約2〜4か月で完成します。
軽量鉄骨造(S造)は、柱や梁などの骨組みに厚さ6mm未満の鋼材を使用した構造です。軽量鉄骨造の住宅は、工場で生産した部材を現場で組み立てるプレハブ工法で建築するのが一般的で、木造に比べて工期が短く耐用年数が長い点が大きな特徴です。
重量鉄骨造との違いは、構造に使用する鋼材の厚さです。軽量鉄骨造が厚さ6mm未満の鉄骨を使うのに対し、重量鉄骨造では厚さ6mm以上の鉄骨を使います。一般的に軽量鉄骨造は戸建て住宅で多く採用され、重量鉄骨造はマンションやビルで採用されます。
鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造の住宅の建築期間は約7~10か月間が目安です。鉄筋コンクリート造(RC造)は、建物の柱、梁、壁などに鉄筋を組み込み、周囲をコンクリートで固めてつくる構造です。
鉄筋は引っ張る力に、コンクリートは圧縮に強いという双方のメリットを組み合わせて強度を高めているのが特徴で、耐火性、耐久性、防音性に優れており、マンションやビル、公共設備などで広く用いられています。
木造や軽量鉄骨造に比べて、コンクリートを流し込む作業がある分工期が長くなり、コストも高くなります。
期間が延びてしまう主な要因
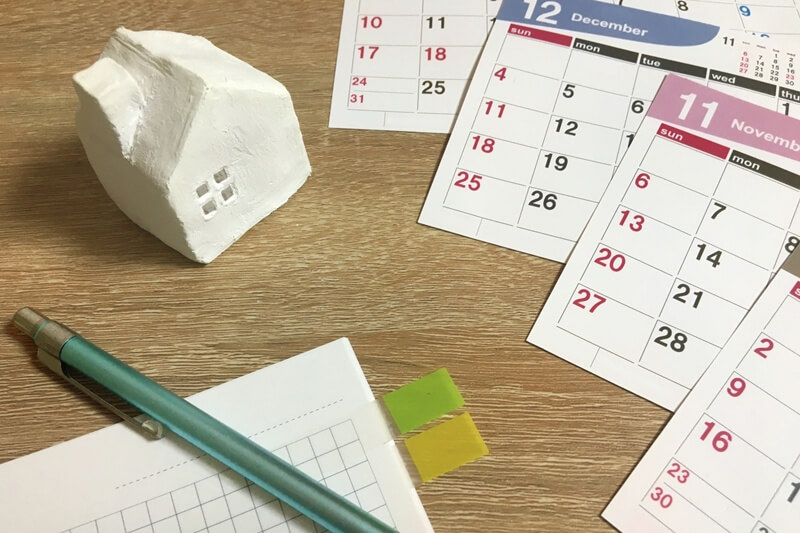
建て替え工事の期間が伸びてしまうのには、どのような原因があるのでしょうか。
以下に代表的な工期延長の要因を挙げるので、事前に把握しておき、スケジュール変更に柔軟に対応できるようにしておきましょう。
天候や季節による工期遅延
大雨や台風など悪天候で作業が中止になり、引き渡しが遅れることがあります。
基本的に解体工事は雨の日でも実施しますが、大雨や台風など安全を確保できない場合は中止となります。
新築の基礎工事も雨は問題ありませんが、基礎コンクリートの打設中に土砂降りの雨が降った場合はコンクリートの強度に影響を与えるため、大雨が予想される日はコンクリートの打設を見送るのが一般的です。
そのほか、屋外工事や外構工事は雨天時に作業が中止となります。その場合、内装工事や室内工事など、天候に左右されにくい作業を行うなどして、遅れを最小限に抑えます。
地中埋設物による影響
解体工事中に地中埋設物が発見された場合は、除去作業が発生するため、工期が延びることがあります。地中埋設物の多くは、瓦やコンクリートガラなどの建築廃材です。そのほか、建物の杭や基礎、石、浄化槽などがあります。
解体工事では地中埋設物は全て取り除くのが基本です。見積もりの時点で地中埋設物があることが分かっていれば、スケジュール通り除去作業を行いますが、工事の途中で地中埋設物の存在が発覚するケースも少なくありません。
その場合、追加工事となり、除去作業の分だけ工事期間が延長し、追加費用もかかります。
近隣トラブルによる遅延
工事の騒音などが原因で近隣住民から苦情を受けてしまい、工事が遅延するケースもあります。とくに解体工事は騒音・振動・粉じんの発生がつきものです。解体工事業者も十分配慮して作業を実施しますが、注意していてもクレームが発生しやすいのが現実です。
新築工事も解体工事ほどの大きな音は出にくいですが、騒音が発生することは避けられず、長期間工事車両や作業員が出入りすることになるので、クレームにつながる可能性があります。
クレームを避けるためには工事前に挨拶回りを行い、工事について説明し理解してもらうことが大切です。もし、苦情が発生したら防音シートを追加する、作業時間帯をずらすなどして対応します。
設計変更や追加工事による工期延長
解体工事で追加工事が発生したり、新築工事の設計変更により着工が遅れた場合、工期が想定以上に長くなる点に注意が必要です。
解体工事の追加工事には残置物撤去や地中埋設物の撤去などがあります。建物の中に家具や家電が残っていると分別して処分するのに手間がかかります。
また、解体作業中に家の下から井戸が出てきたり、庭に埋められた石が大きい場合は撤去作業も大がかりになり、時間もかかるのが一般的です。
設計変更は、設計ミスの発覚などの業者側の責任による遅れのほか、施主が要望や希望条件を繰り返し変更することにより、設計作業に時間が費やされ、着工が遅れるケースがあります。
仮住まいの選び方のポイント

家の建て替え中には、新居が完成するまで仮住まいで生活することになります。そのため、住宅の建築工事の準備と並行して、仮住まいの準備も行わなければなりません。
ここでは、仮住まいの選び方や費用を安く抑える方法を紹介します。
着工の2ヶ月前から探し始める
仮住まい探しは、一般的に着工の2か月前から探し始めます。仮住まいが必要な期間は約4か月~1年半程度です。期間が短いため、定期借家契約を用います。定期借家契約ができる物件は少なく、荷物の量やペットの可否で条件に合った部屋がなかなか見つからない場合もあります。
家賃も希望通りの物件が見つかりにくいため、着工が迫っていて妥協して契約したということのないように、早めに見つけておくことが大切です。
仮住まいへの引っ越しの際は水道や電気、ガス、郵便物の転送など、各種手続きも必要です。引っ越しのタイミングでスムーズに手続きできるよう準備を進めておきましょう。
子どもの学区を考慮する
子どもの学区を考慮するなら、早めに仮住まい探しを始めましょう。短期で借りれる物件は少ないうえ、エリアを絞るとさらに難易度は上がります。
余裕を持ったスケジュールで物件探しを開始し、場合によっては物件の広さや間取りなどの条件を緩和しましょう。
学区のエリア外であっても、仮住まい期間中は現在の学校に引き続き通学できる場合もあります。まずは学校に相談して、可能であれば学区外も視野に入れて仮住まい探しをするとよいでしょう。
仮住まい費用を減らす方法
建て替え工事中は工事費用だけでなくさまざまな諸費用がかかるため、できるだけ仮住まいの費用を安く抑えたいでしょう。その場合は実家を間借りする、マンスリーマンションを借りるなどの方法があります。
最も費用を抑えられるのは実家です。マンスリーマンションは敷金・礼金・仲介手数料がかからない物件が多く、短期で賃貸を借りるならお得です。ただしファミリータイプの物件は少ないため、条件に合った部屋がないケースもあります。
そのほか、仮住まいが見つかりにくい場合は、自治体の住まいの相談窓口を利用してみるのも一つの手です。また、建て替え工事費に一部補助金を活用できる場合もあるので、活用すればお得に工事を実施できます。
解体から新築までの期間に関する注意点

建て替え工事では、打ち合わせや申請手続きなどで施主も忙しく動くことになります。
ここでは、マイホームの建て替え中にとくに注意しておきたいことを紹介するので、業者と協力して進めていってください。
近隣住民への挨拶と騒音・粉じん対策
解体工事では騒音や振動、粉じんで近隣住民に迷惑をかけてしまいます。トラブルを避けるためには工事開始前までに挨拶回りをし、工事について説明をしておくことが大切です。
挨拶回りは業者が行ってくれますが、施主も直接挨拶に伺うことで心証が良くなり、クレームを防げます。
解体業者は騒音や粉じんを防ぐために養生シートの設置や散水をしますが、完全に騒音や振動、粉じんを防げるわけではありません。近所に配慮して防音シートの追加を検討したり、業者に近隣の環境について情報を共有しておくことをおすすめします。
ライフライン関連の手続き
解体工事が始まる前までに忘れてはならないのがライフラインの停止手続きです。電気、ガス、電話、インターネットなどの各事業者に連絡して停止手続きをします。
とくに電気やガスが通ったまま解体工事を行うと爆発などの大事故につながるおそれがあるため、確実に供給を停止しなければなりません。事業者に連絡する際は必ず解体工事を行う旨を伝え、ガスや電気の供給を遮断します。
なお、工事中は水を使用するため、水道は停止しません。誤って停止しないようにしましょう。
まとめ

住宅の建て替え期間はおよそ1年間ですが、とくに計画から着工までの準備期間はさまざまな手配や手続きで施主も忙しい時期が続きます。
やらなければならないことも多いので、忘れることのないよう、業者と協力してスケジュールを管理していくと安心です。そのため、コミュニケーションをしっかり取れる業者を選択することも理想の住まいづくりには重要なポイントとなります。









コメント