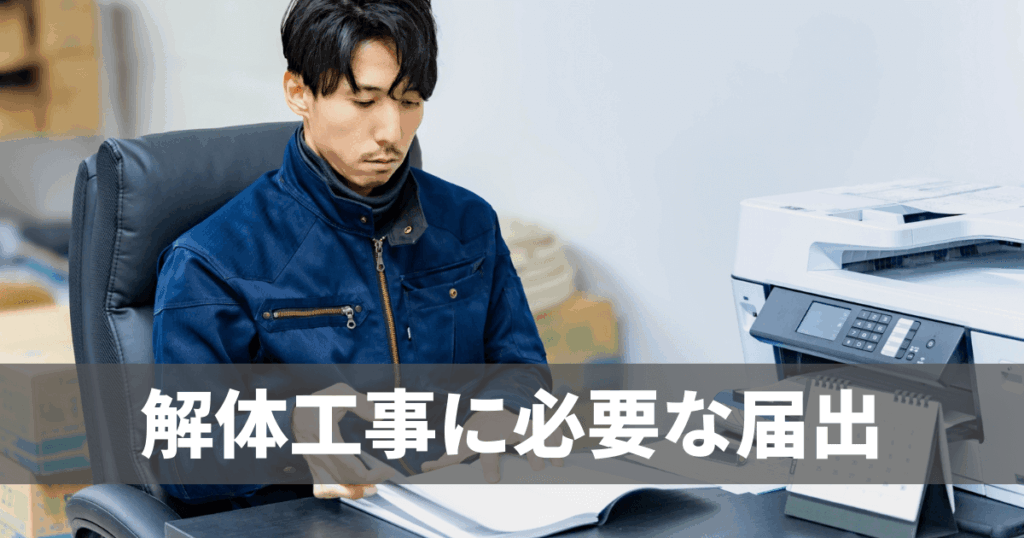
解体工事ではさまざまな届け出が必要です。届け出を怠ると罰金や懲役などの対象となるため、漏れのないように行わなければなりません。
そこで今回は、解体工事の際に必要な届出の種類、手続き方法、手続きをしなければならなないのは誰か、などについて解説します。事前に必要な手続きを把握しておき、スムーズに工事の準備を進めましょう。
解体工事に必要な届出

ここでは解体工事で必要な届出の代表的なものを紹介します。届出の種類のほか、手続きを施主が行うのか、業者が行うのかにも注目して、業者と確認しながら申請手続きを進めることが大切です。
アスベスト除去の届出
解体工事や改修工事を実施する前には、建設資材に含まれるアスベスト(石綿)の有無についての調査が義務付けられています。事前調査は原則としてすべての解体工事について必要ですが、80㎡以上、請負金額100万円以上の工事については報告義務が課せられています。
調査は厚生労働大臣が定める有資格者が行わなければなりません。調査対象が一戸建ての住宅・共同住宅の住戸の内部を除く建築物では「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」が行い、一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部の場合は「一戸建て等石綿含有建材調査者」が行います。
建材にアスベストが含まれていることが調査結果で明らかになった場合は、アスベストのレベルに応じて適切に除去する必要があります。
ライフライン設備の撤去
解体工事の前にはライフラインを確実に停止しなければなりません。電気やガスが通ったまま解体工事を行ってしまうと、爆発などの大事故につながるおそれがあります。ライフラインは工事開始前までに施主が責任を持って停止手続きをしなければなりません。不安な場合は解体業者と情報を共有して、確認しながら停止手続きを進めていきましょう。
停止するのは主に、以下のとおりです。
- ガス
- 電気
- 電話
- インターネット・ケーブルテレビ
解体工事の際、水道は停止も撤去もしません。水道は解体作業で発生する粉塵の飛散を防止するために使用します。
作業で使う水道代は施主側が払うか、業者が払うかは業者によって異なります。業者が水道代を負担する場合は、工事前に水道局に連絡し、水道料金の清算をしておきましょう。
建築リサイクル法の届出
床面積80㎡以上の建築物解体工事では、建設リサイクル法の対象となり、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に届け出を行わなければなりません。
建設リサイクル法は、建設工事により廃棄されるコンクリート、アスファルト、木材等の廃棄物が産業廃棄物全体の排出量・最終処分量のおよそ2割を占めることから、廃棄物の再資源化を目指すために制定された法律です。
対象の建設工事では廃棄物を種類ごとに分別して解体すること、さらに適正な解体工事を行うために解体業者は着工前に解体工事の計画を届け出る必要があります。
建設リサイクル法の届出義務は施主にあります。ただし、通常は解体業者が代行するので、施主は委任状を作成すれば問題ありません。
建物滅失登記申請
建物を解体した場合は法務局に建物滅失登記を申請します。滅失登記は建物の所有者または所有権がある登記名義人が、建物がなくなった日から1か月以内に申請しなければなりません。建物が共有財産の場合は、共有者のうち一人が単独で申請できます。解体時点で所有者が死亡している場合は、相続人が申請します。
必要書類は、以下のとおりです。
- 建物滅失登記申請書
- 建物滅失証明書(取壊証明書)
- 解体業者の資格証明書(登記事項証明書など)
申請は自分でもできますが、所有者が死亡している場合や手続きを急いでいる場合は、土地家屋調査士に手続きの代行を依頼できます。
建物滅失登記をしていないと、建物の固定資産税を支払い続けたり、土地の売却ができない、10万円以下の過料の対象となったりするなど、さまざまな不具合が生じるので、住宅を解体したら速やかに手続きするようにしましょう。
参考:不動産登記法 第五十七条
建築物除去届
建築物除却届は、建て替えを伴わない、床面積10㎡を超える建築物を解体したり除却したりする場合に提出する書類です。建て替えを伴う場合は建築工事届に除却工事を記入すればよいので、提出の必要はありません。
建築物除却届の目的は、国土交通省が国内にどれくらいの建物があるのか、統計を取るためです。国が年間に除却される建物の数を把握するために提出を求められています。
建築物除却届は、建物の一部を除却する場合でも、除却する部分の床面積の合計が10㎡超の場合は届出が必要です。
建築物除却届は、解体工事業者が解体工事実施の前日までに都道府県知事に届け出ます。
参考:建築基準法 第15条1項
道路の使用許可申請
解体工事で一般道路に工事車両や重機を停車する可能性がある場合は、道路使用の許可申請が必要です。道路使用許可には1号許可から4号許可まで4種類ありますが、建設工事等で道路を工事したり、道路に車両を駐車するなどする場合には1号許可が必要です。
道路使用許可は解体工事業者が警察署に申請します。申請は一般的に工事開始2週間前までに行い、許可が認められた期限を守って道路を使用しなければなりません。
申請時には、申請費用として約2500〜2700円かかり、解体工事費用と共に請求されます。見積もりの際には見積書に道路使用許可の申請費用が記載されているかチェックしましょう。
なお、解体工事の足場が敷地外にはみ出す場合は、道路占用許可も必要です。
フロン製品の有無の確認
解体工事の際にはフロン製品の有無も確認しなければなりません。
フロンは冷媒として冷蔵庫やエアコンに使用されてきましたが、大気中に放出されると地球のオゾン層を破壊したり地球温暖化の原因になったりするなど、環境に悪影響を及ぼすことが分かっています。そのため、環境を守るために、フロンを使用した製品の処分に対して実施されるのがこの規制です。
施主は解体業者からフロン製品の有無を確認されるので、正しく伝え、フロン製品の回収や再生にかかる料金を支払います。
解体工事業者は建物内のフロン製品の有無を確認し、事前確認書を作成し、フロン類充填業者に委託確認書を提出しなければなりません。事前確認書と委託確認書は3年間の保存が義務付けられています。
届出と同時に行うべき準備

解体工事を実施する際には、届出のほかにいくつか準備しなければなりません。ここではとくに重要な二つを紹介するので、忘れずに対応できるように業者と打合せしておきましょう。
近隣住民に対する事前説明
解体工事前には近隣住民にあいさつ回りをして工事に関する説明や、迷惑をかける旨を伝える必要があります。
解体工事は業者がどれだけ気をつけていても騒音や粉塵、振動、工事車両の通行などで迷惑をかけてしまいます。事前に挨拶があるのとないのとでは、近隣住民への印象も大きく変わるでしょう。
挨拶は工事開始1週間前に行います。挨拶回りは、両隣、向かい、裏、斜め向かいには最低でも行いましょう。そのほか、車の通行などで迷惑をかけそうな住宅にも挨拶しておくと安心です。挨拶は解体工事業者も行ってくれますが、施主が自ら訪問したほうが印象がよくなります。
騒音・粉じん・振動の対策計画
解体工事で発生する騒音・粉塵・振動については、解体工事業者でも対策してくれますが、施主も近隣についての情報を共有し、業者と協力することでトラブルを最小限に抑えられます。
工事中は養生シートを設置し、がれきの飛散を防ぎ、安全対策を行います。作業中には散水を行って粉塵の飛散を防ぐのが基本です。騒音対策としては夜間や早朝の作業は控え、騒音に敏感な時間帯に配慮します。
施主としても、昼食どきは作業を避けたほうがよい、追加で防音シートを設置したほうがよいなど、業者に要望を出して、できるだけ近隣に迷惑がかからないよう配慮するとトラブルを防げます。
そもそも家を取り壊す手続きとは?

解体工事を行う前にはさまざまな手続きが必要ですが、忘れてはならないのが上でも紹介した建設リサイクル法に基づいた「解体工事届出」の手続きです。ここでは、解体工事届出について詳しく解説します。
手続きの届け出先
解体工事届出書は、工事着工の7日前までに自治体に提出します。自治体の提出窓口は建築課、環境課等となり地域によって担当部署が異なり、細かいルールも異なるため、事前に要綱の確認が必要です。
届出に必要な書類は、以下のとおりです。
- 届出書(様式第1号)
- 分解解体等の計画
- 案内図
- 設計図または写真
- 工程表
- 委任状(業者に委任する場合)
手続きは発注者の施主が行うのが基本ですが、一般的に解体工事業者が代行してくれます。施主は委任状を作成し、業者に任せれば問題ないでしょう。
手続きや届出が不要な場合
解体工事届出は一定の条件以上の解体工事をする際に必要な申請です。具体的には床面積80平方メートル以上の家を取り壊す際に必要です。つまり、床面積80㎡以下の場合は手続きは不要となります。
一方で、床面積80㎡以上の住宅であるにも関わらず、届出を行わずに工事を実施した場合、行政指導の対象となります。行政指導にも従わないと最大20万円の罰則の対象となるため、解体工事業者がしっかりと手続きを済ませているか、確認しておくと安心です。
家を取り壊した後の注意点

家を取り壊すと、税金面や土地の活用方法などで気を付けなければならないことがあります。ここでは住宅の解体後に気をつけておきたいことを挙げるので、事前にしっかりチェックして、後悔のない解体工事を実施してください。
固定資産税が増額される場合がある
住宅を解体すると、建物にかかっていた固定資産税はなくなります。しかし、住宅があったときに受けていた特例が受けられなくなり、土地にかかる固定資産税が増額される点に注意が必要です。
土地に建物が建っている場合、「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が1/3~1/6まで軽減されます。建物がなくなることで特例の適用がなくなり、固定資産税が6倍になる可能性があります。
実際には建物の固定資産税がなくなるため、支払額は建物があったときの1~3倍程度になるのが一般的です。いずれにせよ、負担額は大きくなるので、住宅が老朽化していない場合は、住宅の活用を検討してもよいでしょう。
将来の土地活用を考える必要がある
建物を取り壊したあと、土地をどのように活用するのか考えておくと安心です。土地の活用方法としては、以下があります。
- 土地を売却する
- 土地にマンションやアパートなどを建築し賃貸経営をする
- 駐車場にして貸し出す
- 土地を定期借地権で貸し出す
マンションやアパートを建てて賃貸経営すれば、住宅用地の特例が適用されるうえに家賃収入を得られます。コンビニエンスストアや小売店、飲食店など小規模な店舗などの需要がある場所なら、定期借地権で一定期間土地を貸す方法も有効です。
定期的な土地のメンテナンスが必要になる
更地を放置しているとさまざまなリスクが高まったりトラブルが発生したりする原因となるので、定期的にメンテナンスをしなければなりません。
まず、放置された更地では隣家との越境トラブルに注意が必要です。放置された土地では雑草が伸びて隣家に越境してしまう可能性があるため、注意が必要です。
草が大きく伸びると、不審者の隠れ場所になりやすく、近隣に泥棒が入る原因となってしまうこともあります。このようなことを防ぐため、こまめな草刈りは欠かせません。
また、放置された更地は不法投棄されやすく、ゴミが溜まると放火のリスクも高まるため定期的に片づけるなど、きれいな状態を保つ必要があります。
まとめ

解体工事の際にはさまざまな申請手続きが必要です。工事開始前までに手続きが完了していなければならず、違反した場合は罰則の対象になるものもあります。業者と連携して提出期限までに申請を行い、工事のスケジュールが遅れないようにしましょう。
分からないことは業者や管轄の役所の窓口に質問して、疑問を解消しておくと安心です。









コメント