
近所から聞こえる騒音を軽減したい、もしくは家の中で発生する話し声やペットの鳴き声、楽器の音をできるだけ漏らさないようにしたい、と考えている場合、代表的な対策として防音フェンスの設置があります。
しかし「防音フェンスは効果がない」と聞いて設置を迷っている方も少なくないでしょう。
この記事では、防音フェンスの注意点や種類、フェンス以外でもできる防音対策について解説します。
防音フェンスは効果なしって本当?

防音フェンスは効果がない、というのは本当なのでしょうか。音はその性質により、フェンスでは完全に防音できないことがあります。
ここでは、防音フェンスの注意点と特徴を紹介するので、設置を検討する際の参考にしてください。
騒音は通り抜けや回り込みがある
防音フェンスは騒音を跳ね返したり内部に取り込んで音を軽減します。しかし、フェンスを通り抜ける音もあるため、完全には消音できません。
また、音は波状になっており、フェンスを立てていても左右や上から回り込む性質を持っています。
音は波長が短い高い音よりも、波長が長い低い音の方が回り込みが起こりやすいと考えられています。そのため、車の音や室外機の音のような低い音は軽減しにくく、フェンスを立てていてもうるさいと感じてしまうのです。
防音フェンスにはある程度の高さが必要
騒音を遮断するためにはある程度高さのある防音フェンスを設置する必要があります。背が高ければその分、音の回り込みを防ぎ遮音性が高まるのが一般的です。
ただし、高すぎるフェンスは圧迫感を与え、風通しも悪くなるため、防音機能と外構デザインのバランスを考え、適度な高さにすることをおすすめします。
フェンスの適切な高さは騒音がどこから発生しているかでも変わります。例えば駐車場から聞こえる車のエンジン音が気になる場合、音は地面に近いところから発生するので、1.2m程度の高さがあれば十分です。
防音フェンスの構造とは
防音フェンスは金属の内部に樹脂を挟み込むことによって、金属単体のフェンスよりも防音性に優れた構造になっています。
製品によって音の通り抜けを軽減できるタイプ、音を吸収して摩擦により消音するタイプなど、防音のメカニズムが異なり、メーカーによって採用している素材も異なります。
フェンスでの騒音対策を考えている方のなかには、目隠しフェンスでも十分防音できるのではないか、と考える方もいるかもしれません。
しかし、目隠しフェンスと防音フェンスでは構造が異なるため、防音を目的としている場合は防音性能を備えたフェンスを選ぶことをおすすめします。
設置後の変化は10デシベル前後
防音フェンスの騒音の低減効果は音圧レベル差で約10dB(デシベル)程度とされています。10dBというとほとんど変化がないように感じられるかもしれませんが、人の耳ではおよそ半分の差に感じるレベルです。
たとえば、騒音レベル60dB台は、バス、新幹線の車内や、コーヒーショップ、ファミリーレストランの店内などです。50dBは銀行や役所の窓口周辺、書店の店内の騒音レベルなので、10dB低いだけでかなり静かに感じることが分かります。
このように、防音フェンスを立てるだけで騒音によるストレスはかなり軽減できるでしょう。とはいえ、フェンスだけでは限界があるので、植栽、遮音カーテン、二重窓などを併用すると効果的です。
防音フェンスには2つのタイプがある

防音フェンスには遮音タイプと吸音タイプの2種類があり、防音のメカニズムが異なります。
それぞれの特徴を以下で紹介するので、どちらが住まいに適したフェンスなのか、考えてみてください。
遮音タイプ
遮音タイプは、音を跳ね返して音が敷地の内外へ取り抜けることを防ぐフェンスです。
遮音フェンスはアルミフェンス板の内部に樹脂が入っている構造です。アルミの板材が音を跳ね返し、残った音の振動を樹脂が弱めて防音します。
遮音フェンスは採光パネルを使用した製品も存在するため、光を取り入れながら防音が可能です。他方で、音を反射する性質のため、音がある側では反射された音が残ります。
近隣住宅との境界に設置した場合に、音が反響してご近所との関係に問題が発生する可能性があるため、住宅が隣接している場所では設置に注意が必要です。
吸音タイプ
吸音タイプは、音をフェンスの中で熱エネルギーに変換して振動を弱め、音を小さくするフェンスです。
吸音フェンスは、スチール板とパンチングアルミが多孔質の樹脂を挟んでいる構造です。音がフェンスにぶつかるとパンチングアルミの中に入り込み、拡散されます。このとき、フェンス内部の素材と摩擦が生じると同時に内部で振動が起こることで、音が熱に変換されて低減する仕組みです。
吸音フェンスは消音効果があるので、住宅地での防音対策に向いています。
フェンスを設置する上での注意点

フェンスを設置する際にはいくつかの注意点があります。
防音フェンスだけでなく、すべてのフェンスに共通する注意点なので、設置を計画している場合は事前にチェックしておいてください。
基礎は十分な強度とサイズが必要
フェンスは倒壊を防ぐために、安全性が高く十分な大きさの基礎の上に設置しなければなりません。独立基礎でフェンスを設置する場合、現場の風の受け具合や土壌の硬さ、フェンスの高さと形状を総合的に見て、基礎ブロックのサイズを決めます。
基礎ブロックは大きくなればその分安定性が増しますが、単価が高くなるため、外構工事業者が費用と安全性を考慮したうえで最適なものを選択します。
ブロック基礎のブロックの厚さは、ブロック塀の高さが2m以下の場合は厚さ12cm以上、2mを超える場合は15cm以上が推奨されています。
参考:ブロックの厚さ|一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会
隣家への影響を考慮する
フェンスを建てるときは隣家への配慮も必要です。背の高いフェンスは圧迫感を与えるだけでなく、隣家に日陰を作ってしまう可能性があります。
フェンスを設置する前に隣家への日差しや風通しの影響がないか、圧迫感を与えないか十分に検討しましょう。
ある日突然、目の前にフェンスを建てられるのは決して印象がよいものではありません。
フェンスを設置する際は隣家へひと声かける、背の高いフェンスは必要な場所に限定する、防音の必要がない場所は隙間のあるフェンスにする、など工夫することも大切です。
防犯への影響も検討する
フェンスを設置する際は、防犯にも気を配ることが大切です。フェンスは乗り越えにくい高さが理想ですが、あまり高すぎるフェンスはかえって不審者に狙われやすいため注意しなければなりません。
背の高いフェンスは確かに乗り越えにくいですが、一度乗り越えてしまうと外から見えず、不審者が自由に行動できてしまいます。
フェンスの高さは1.5〜1.8m程度にする、縦格子や目の細かいフェンスなど登りにくい形状を選ぶと、エクステリアの防犯性を高められます。死角になりやすい場所には照明で明るくしておくと安心です。
防音フェンス以外の効果的な防音対策

ここでは防音フェンス以外でできる騒音対策の方法を紹介します。防音フェンスが設置できない場所で活用できるだけでなく、防音フェンスと併用することで防音効果を高められるので、上手に組み合わせましょう。
家具の配置変更
室内の家具の配置を変更するだけでも防音効果を高められます。家具のなかには音を吸収しやすいものがあり、音が伝わりやすい側の壁に置くだけでも対策ができるでしょう。
家具による防音対策は、隣の部屋への音漏れや室内の反響を防ぎたい場合にも有効です。
特に防音効果があるとされている家具は、本棚、洋服ダンス、ベッド、ソファです。本棚、洋服ダンスは隣の部屋に面した壁側や、音を遮断したい方向に置くとよいでしょう。
ベッド、ソファは音を吸音しやすいため、室内の音を吸収したり反響音を軽減させたりするのにおすすめです。
屋外では物置の位置を交通量の多い道路に面した場所や隣家のガレージ側に置くなどして騒音に対応することもできます。
防音カーテン
窓から入る音を遮断したり、自分の部屋の音漏れを防ぎたいなら防音カーテンが手軽です。
防音カーテンは、生地の織りを密にしたり、複層にしたりすることで、音の吸収性が高められ、室内外の音を吸音できます。
防音カーテンは空気を通して伝わる空気伝搬音の軽減効果に優れているので、周波数の高い音に効果的とされています。女性や子どもの声、ペットの鳴き声、楽器の中音域から高音域の音を吸収しやすいといえるでしょう。
一方で自動車の音や工事の騒音など、振動による音の軽減効果は低く、あまり音を軽減できません。
また、一般的な防音カーテンは低い音を吸収しにくいため、低音を遮音したい場合は特殊生地を重ねた防音カーテンを選ぶか、サッシを二重窓などにするとよいでしょう。
壁・天井・窓に吸音材や遮音材の活用
壁や天井、窓に吸音・遮音効果のある素材を設置する方法もあります。対策方法にはさまざまなものがありますが、特に空気伝搬音、固体伝搬音両方に高い効果がある方法として代表的なものが二重天井です。
二重天井は既存の天井にもう一層天井を施工して、音の振動が伝わることを防ぎます。また、天井裏に吸音材を充填する方法も遮音効果の向上に効果的です。
これらのほかに、DIYで吸音材を壁に貼ったり、窓用の吸音パネルを設置する方法もあります。防音アイテムがホームセンターなどで多く出回っているので、予算と環境に合った方法を選ぶとよいでしょう。
内窓・二重窓
内窓(二重窓)は、外窓と内窓の間に空気の層ができることによって内外の音を軽減できます。空気の層によって防音効果を高めるので、人の声やペットの鳴き声、楽器の音のような、空気伝搬音を軽減できます。
一方で、工事音や車の通行による音、ドアの開閉、物がぶつかる音にはあまり効果が期待できない点には注意が必要です。
とはいえ内窓は、断熱性の向上、結露対策、防犯対策にも効果的です。内窓はリフォームであとから設置できるため、室内の快適性を高めたい場合は検討してみるとよいでしょう。
生垣などの植栽を活用
生垣は、外構を緑で彩りながら外の騒音を和らげ、室内の会話と生活音を漏れにくくしてくれます。防音効果は防音フェンスに劣りますが、家の前面など、美観を維持したい場所の防音素材として活用できる点は大きなメリットです。
防音効果を得るには背が高く葉が密集している樹木を選ぶようにしましょう。常緑樹は一年中葉が生い茂るので、年間を通して防音効果が変わることなく、落ち葉掃除の手間が少ないためおすすめです。
防音フェンスの効果に関するよくある質問

ここでは防音フェンスの効果や防音対策についてよくある質問とその回答を紹介します。
住宅の新築やリフォームで防音対策を検討している場合は事前にチェックしておき、住まいにぴったりの方法を選択しましょう。
防音フェンスを設置したら費用はどのくらい?
防音フェンスの設置費用は、フェンスの性能やメーカーにより幅がありますが、高さ1800mmのフェンスを6m設置した場合はおよそ80万円が目安です。
同じサイズの目隠しフェンスの設置費用は30万円程度と、防音フェンスは高額なので、カタログの情報や画像だけで決めず、ショールームで実物を見たり、業者にアドバイスをもらいながら選ぶと安心です。
工事を検討している場合は複数の外構工事業者に現地調査を依頼し、工事費用の詳細な見積もりとプランを提示してもらうと失敗を防げます。
ブロック塀は防音効果があるのでしょうか?
コンクリートブロックは、音を遮音しやすい素材です。そのため、ブロック塀を設置すれば一定の防音効果が期待できるでしょう。
ただし、ブロック塀は高さ2.2mまでしか設置できないため、それ以上の高さが必要な場合は防音フェンスを設置することになります。また、ブロック塀の高さが1.2m以上の場合、3.4mごとに控え壁を設置しなければなりません。
控え壁はスペースが必要なうえ、見た目もすっきりしないので、狭いスペースに設置する場合や外構をスマートにしたい場合は防音フェンスがおすすめです。
防音シートを壁に貼って効果はある?
防音シートは空間に適したものを利用すれば、ある程度の防音効果が期待できるでしょう。
防音シートには、シールタイプ、フェルトタイプ、パネルタイプなどの種類が存在します。なかでもフェルトタイプは繊維が密集しており、簡単に防音が可能です。
シートは薄手のものは初心者でも設置が簡単ですが、厚手のものよりも防音性能は劣る傾向があります。扱いやすさと防音性能を照らし合わせて、用途に合ったものを選びましょう。
まとめ

防音フェンスで効果的に音を遮るには、住まいに合ったものを設置することが大切です。設置を検討している場合は、多くの施工事例がある経験豊富な外構工事業者に相談しながら決めると失敗を防げます。
防音のほかにも通行人の視線を遮りたい、多くの植栽を植えてガーデンライフを楽しみたいなど、業者に外構の要望を伝えると、住む人にとって快適な外構に近づけます。
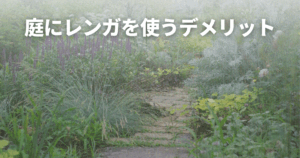
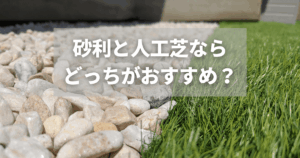
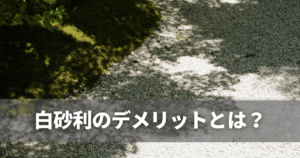
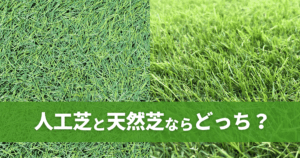
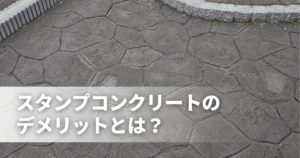
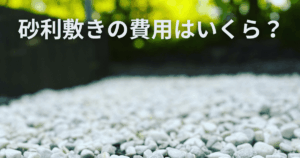
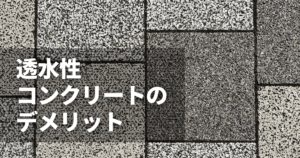


コメント