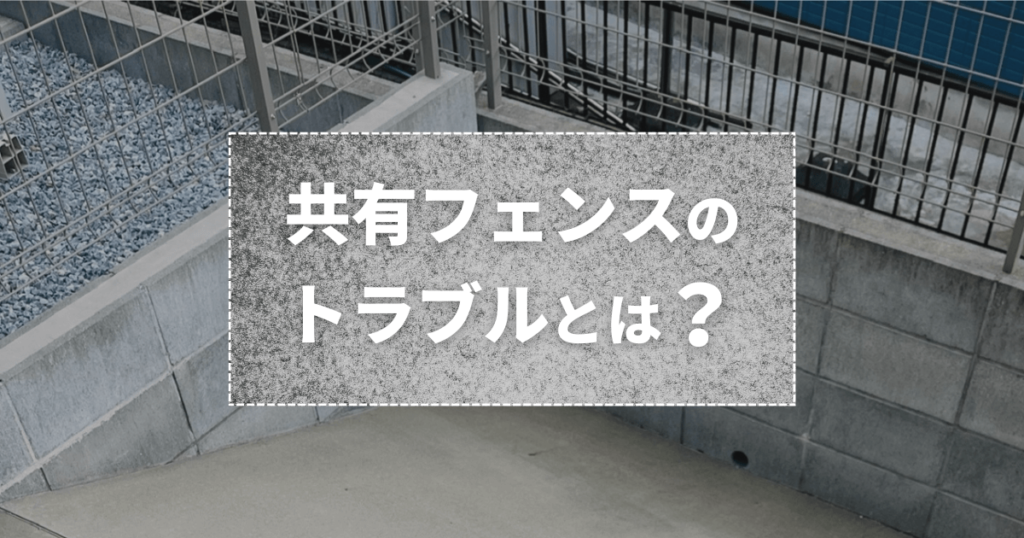
戸建て住宅だけでなく、マンション、アパートでも隣地との境界に境界フェンスを設置します。その境界フェンスを隣家と共有で設置したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、境界ブロックや境界フェンスを共有にすると、後々ご近所トラブルに発展するおそれがあります。
この記事では、共有フェンスで起こりやすいトラブルの内容や、トラブルを回避するためのポイントを紹介します。
共有フェンスのトラブルとは?

共有フェンスではどのようなトラブルが起こりやすいのでしょうか。ここでは、共有フェンスでとくに起こりやすいトラブルや、トラブルを避けるために必要なことを紹介します。
事前にチェックしておき、隣人と揉め事に発展しないように対策しましょう。
売買や相続で所有者が変わるとトラブルに発展する可能性がある
共有フェンスは土地の所有者が変わるとトラブルが発生しやすい傾向があるため、十分注意しなければなりません。
共有フェンスのメリットは、設置費用を隣家と折半するのでコストを抑えられること、土地を最大限広く活用できることです。
しかし一方で勝手に手を加えることができず、撤去やリフォームの際には隣家の了承が必要です。
共有を決めた当事者同士が土地を使用している間は問題がなくても、不動産相続で次の世代が土地を使用し始めた場合、土地を売却して第三者が住み始めた場合はどちらの所有物かどうか分からなくなったり、管理方法で揉めたりすることも少なくありません。
そのため、共有フェンスを建てる場合は、将来のことも考えて決断することが大切です。
撤去・取り替えは共有者の同意が必要
共有フェンスは、一度建てたら撤去や建て替えには共有者の同意を得なければなりません。
関係性が良好だからといって勝手に取り壊したり、電話一本で解体する旨を挨拶程度に伝えたりして協議をおろそかにすると、トラブルに発展するおそれがあるので十分注意が必要です。
解体やリフォームを行いたい場合は、丁寧にフェンスの状況と改修したい理由を直接説明し、納得してもらってから工事を依頼しましょう。
共有フェンスの解体の同意を得た場合、費用の折半を提案することも可能ですが、一般的には解体を申し出た人が全額を負担します。
工事費用を全額負担する場合でも、工事の予定日時や内容については隣人に伝えておくようにしましょう。
修繕についても共有者との話し合いが必要
フェンスの修繕についても同様で、共有者と話し合い、同意を得て工事を依頼します。
費用を折半する場合は、工事を希望した側が業者と契約して費用を立て替えておき、後日隣人から回収することになります。
また、工事費用を全額負担する場合であっても、隣人に工事前の現地調査と工事完了後の点検には立ち会ってもらうと、トラブルを防げるはずです。
工事中に業者が隣家の敷地内を使用したい場合も事前に了承を得ておきましょう。
そもそも共有フェンスとは?

共有フェンスとはどのようなものを指すのでしょうか。
以下に共有フェンスの定義や、設置に関して所有者が負う責任について紹介しているので、自宅のフェンスが共有フェンスに該当していないかチェックしておきましょう。
共有フェンスの定義
共有フェンスとは、隣接する二つの土地の境界線上に設置されたフェンスのことをいいます。
民法229条では、境界線上にある構造物は、共有物とみなされると推定され、通常、境界線の真ん中に設置されたフェンスやブロック塀は隣家との共有となります。
また、民法上では「他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」とされており、勝手に解体したりリフォームしたりすることはできません。
設置費用や管理責任の分担
上でもご紹介した通り、共有フェンスは基本的に設置や撤去、リフォーム費用は隣家との折半となります。そのため、工事をする場合は費用負担も含めて隣人の了承を得なければなりません。
また、フェンスの欠陥や管理不十分により共有フェンスが倒壊するなどして第三者が被害を受けた場合は、民法717条により共有者全員が損害賠償責任を行うことになります。
このとき、共有者はその持分割合に応じて責任を負うものとされており、共有フェンスが隣家との境界線の中央に設置されている場合、お互い半分の50%ずつ負担することになります。
隣地境界のトラブルを避ける方法

境界線のトラブルは境界フェンスを新設する場合にのみ起こるわけではありません。
昔から設置されているブロックでもトラブルに発展するおそれがあるので注意が必要です。ここでは、境界トラブルを避けるための方法について解説します。
古い共有ブロックの境界を明確にする
いつ設置されたのか分からない古いブロック塀がある場合は、境界線を調べ、所有者を明確にしておきましょう。
土地の境界を調べる方法は主に、法務局で土地の情報を確認する方法と、専門家に測量してもらう方法の二つです。
法務局では登記謄本、登記事項証明書、地図、地積測量図などを確認することで、土地の境界を明らかにできます。
地積測量図などでは分からない場合は、土地家屋調査士または測量士に測量を依頼し、隣地境界線を明確にします。
敷地内のブロック塀は境界線から2cm離す
自分の敷地内に単独所有のブロック塀を建てる場合は、境界線ぴったりに立てるのではなく、境界線から2cm程度内側に設置するようにしましょう。
これは基礎となるブロック塀の上にフェンスを設置したとき、厚みのあるフェンスだと越境してしまうおそれがあるためです。
ブロック塀は修理やリフォームで、モルタルを塗ったりタイルを貼ったりしてきれいにすることがあります。
このとき、境界いっぱいにブロック塀を建ててしまっていると厚みが出るモルタルやタイルを貼ることができないため、将来修繕することも考えて2cmの余裕を持っておいた方が安心です。
共有フェンスに関するよくある質問

いざ隣地境界線にフェンスを設置しようと考えた場合、さまざまな疑問が浮かび上がってくるのではないでしょうか。
ここでは、共有フェンスに関してよくある質問とその回答を紹介するので、工事を計画する前に疑問を解消しておきましょう。
共有フェンスにものを勝手にかけるのはあり?
共有フェンスにものを勝手にかけるとトラブルに発展するおそれがあるため、やめておいた方が良いでしょう。
境界線上にフェンスが設置されている状態では、フェンスにものを掛けたときにフェンスの向こう側に行った部分は越境していることになってしまいます。
これは共有フェンスに限らず、植栽や屋根など空中であっても越境してはいけません。
つまり、自分の敷地に建てた単独所有のフェンスでも、掛けたものが隣家の敷地に越境しているとトラブルに発展することがあるので注意が必要です。
どうしてもものをかけたいときは、お隣に一声かけて了承を得るようにし、かける時間もできるだけ短時間にするようにしましょう。
目隠しフェンスを境界線ギリギリに設置して大丈夫?
目隠しフェンスは境界線ギリギリよりも少し控えて設置した方が無難です。確かに、法律的には境界線ギリギリにフェンスやブロックを設置しても問題ありません。
しかし、施工上数ミリ程度の誤差が出ることや、経年や地震による歪みで越境してしまうことがあります。
それだけでなく、ギリギリに設置したことで隣人からクレームが入ることも珍しくありません。トラブルを避けるためにも、ある程度境界線から余裕を持って設置した方が良いでしょう。
近年、ハウスメーカーが分譲住宅を新築する場合は、境界杭の端面に合わせてブロックを積むケースが増えています。つまり、境界杭が6cmの場合、3cm控えて設置します。
実際にどの位置にブロックを設置すれば良いかは、業者にアドバイスを求めると良いでしょう。
目隠しフェンスの高さは法律で決まっている?
目隠しフェンスの高さについて法律ではとくに制限はありません。しかし、ブロック塀の高さが2.2メートル以内と規定されているため、フェンスも2.2メートルを上限とするのが一般的です。
目隠しフェンスは背を高くすれば目隠し効果がアップします。一方で背が高いと圧迫感を与えてしまうため注意が必要です。
相手の土地の高さを考慮しながら、140~200cm程度の範囲で目線を遮れる程良い高さのものを設置したり、格子状のタイプなど圧迫感の少ないタイプを選んだりすると良いでしょう。
境界線以外の駐車場や玄関まわりなどに設置するフェンスも同様に、目的に合った高さとデザインのものを選ぶと住まいを快適にできます。
塀やフェンスの所有者がわからない場合はどうなる?
お隣との境界線に、所有者やその背景が分からないブロック塀やフェンスがある場合は、撤去や建て替えをする前に必ず所有者を確認しましょう。
塀とフェンスは基本的に設置した人が所有者です。誰が設置したのか分からない場合は、境界線を確定させ、どちらの敷地に設置されているかで判断します。
もし、塀が土地の境界線上にある場合は、原則として「共有」となります。境界線が明らかでない場合は、上でもご紹介したように、法務局で境界線を確認するか、土地家屋調査士などの専門家に測量を依頼しましょう。
まとめ

共有フェンスは、取り壊しやリフォーム、不動産相続、土地物件の売却などの際にトラブルが発生しやすい傾向があります。
撤去や建て替えを検討している場合は、隣人との協議は必須となるので、丁寧に事情を説明してトラブルが起こらないようにしましょう。
解体や新設の際は業者にアドバイスを求めるようにし、万が一揉め事に発展してしまった場合は弁護士の法律相談を利用するなど、専門家の助けを得ると安心です。









コメント